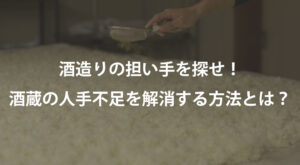うちの蔵を「選ばれる職場」に!労働環境改善のススメ
「最近オンラインショップが好調で、国内だけでなく海外からも注文が入るんだよ!」
「でも…なかなか酒造りの働き手が確保できなくて…」
お酒と料理のペアリングやインターネットを活用した販売手法など、国内・海外からも注目を集める日本酒。
その一方で、酒造業界の悩みの1つは、労働力の確保の困難さです。
少子化による労働力不足、ライフワークバランスや働き方改革といった価値観の変化などを背景として、他の業界においても、事業継続のために、「職場のあり方」を見直して労働力を確保することが重要課題となっています。
限られた労働力のパイを取り合う現状においては、労働環境の改善を進め「選ばれる職場」にしていくことが重要なんです。
今回は、酒蔵の労働環境問題を深掘りしていきましょう。
あなたの蔵は大丈夫?酒蔵の労働環境の課題とは?
「うちの蔵は大丈夫だよ!みんな楽しそうに働いているし…」
「お酒造りって大変なもんでしょう…うちは昔からこの働き方でやってきてるし…」
あなたの蔵、大丈夫ですか?
はじめに、酒蔵の労働環境の現状について探っていきます。
ブラックorホワイト?

昔、マイケルジャクソンの歌に「ブラック・オア・ホワイト」という歌がありましたよね。
この歌は、「肌の色なんてどうでもいいだろう!」という人種差別反対ソング。
今や、「ブラック・オア・ホワイト」と言えば、従業員サイドから見た職場の労働環境のことなんです。
「ブラック企業」とか「ホワイト企業」とか呼ばれ、一度ブラック企業の烙印がついてしまうと、口コミで噂が広まり、働き手が確保できないばかりか、SNSで炎上して企業の信用力が低下してしまうこともあります。
事業者としては、労働力の確保や対外的信用力アップを考え、ホワイト企業を目指す「ホワイト化」への取組を進めていく必要があるのです。
酒蔵の労働環境の課題
「ホワイト化」を目指すためには、酒蔵の労働環境について、どのような課題があるのかを把握しておく必要があります。
労働環境の課題を知るには、現場の声を聞くことが一番。
とある民間企業が行った全国の蔵人を対象にしたアンケート調査結果によれば、以下のような課題が浮き彫りになったのです。
- 長すぎる労働時間
- 安い給与
- 安全面における高リスク
以下、順に確認していきましょう。
労働時間
お酒造りでは、麹やもろみの管理など長時間労働を強いられる作業もあります。
アンケート結果によれば、繁忙期には1日9.5時間以上(中には12時間以上労働も)、ろくに休憩時間もなく、週1日も休みがとれない人も多いようです。
日本酒造りの現場では、長時間労働、連続勤務が問題となっています。
給与
長時間労働時間の割に、給与が安いと回答する人も多かったようです。
早出勤務、残業など時間外労働に対する手当もつかない、または安いといった意見も多く見受けられました。
酒造業の現場では、労働内容と給与が見合っていないという課題が見てとれます。
安全面
お酒造りは力仕事が多く、体力勝負なところがあります。
重い物の持ち運び、不安定な場所や高所での作業、フォークリフトや醸造機器など大きな機械の操作など危険と隣り合わせなことも多い現場。
アンケートに回答したほとんどの蔵人から「安全面で不安がある」「身の危険を感じる」といった意見が出ました。
酒造業の現場では、安全面への対策が欠けているといった課題があるようです。
酒造業と異業種との労働環境の違いとは?

酒蔵での労働環境を見直すにあたって、他業種での労働環境がどのような状況になっているのかも参考に見ていきましょう。
安全面の対策が違う
大きく違っているのは、安全面での対策です。
酒造業界では当たり前に行われてきた作業が実は…。
安全靴を履かず、長靴やサンダルでの作業が常態化していたり、フォークリフトの使い方が荒かったり…
2メートルほどの仕込みタンクの上で足場には幅が狭い角材。数十リットルもあるもろみや水の入った容器を持ったまま、ハーネス(命綱)などもつけずに移動。
かと思えば、2階からクレーンでお米を昇降するときもヘルメットなし。
このような安全面での対策は、法令や社内規程で安全対策が徹底している建設業や他の製造業では考えられないと言われています。
他業種では、「ケガや事故はいつあってもおかしくないもの。労災保険に入っているだけでは、働く人の安全は守られない」という前提が安全対策の基本のようです。
他業種と違いを生む原因は?
労働環境に関して、他業種と違いが出てきてしまうのには、いくつかの要因が考えられます。
1つには、酒造業は歴史が古く、昔からの酒造りの伝統手法が今も継承されていることから、良きにつけ悪しきにつけ、他の業種を参考にすることがなかったこと。
また、休みもとれず長時間労働に耐えられたり、薄給でも働けたりするのは、蔵人が日本酒造りが好きだからということもあるでしょう。
好きなことには条件など関係なく、没頭してしまう、それが当たり前になってしまうといったことが考えられます。
さらに、日本酒の製造免許取得の要件として、年間の最低製造量が決まっていて、3年以上最低製造量を下回ると製造免許取消の措置もあることから、造りを何よりも優先させてきたことなども影響しているでしょう。
他方、他の業種では、労働基準法が適用されるので、法令を意識した労働環境となっているのに対して、酒造業では、かつての「清酒製造は農業と同様の扱いで、労働基準法の労働時間や休日の規定が適用されない」という通達の影響もあります。
しかし、この通達の行政上、法律上の取扱いに関しては、70年前の通達であり、今も同じ取扱いをすべきかという問題や、要件が細かく決まっていて、適用のハードルが高いことなど、グレーゾーンであり、注意をすべきでしょう。
もちろん、人手不足で十分な休日がとれない、給与を上げたくても利益確保がままならないなど経営上の課題も関係しています。
いずれにしても、経営陣の考え方一つで、蔵の労働環境が見直されるかどうかが左右していることに間違いはないはずです。
働きやすい職場には人材が集まる!

お酒造りは、造り手が代々受け継いできた「手法」と「日本酒愛」に支えられています。
日本酒の伝統文化を次世代、次々世代に伝えていくためにも、優秀で健康なサステナブル(持続可能)なお酒造りの担い手を確保する必要があるのではないでしょうか。
今の若者は、「働き方改革」「ワークライフバランス(仕事と人生どちらも充実させる考え方)」などを重視した志向を持っているので、働く場所を決める際には、労働条件をしっかりとチェックする傾向があります。
結果として、働きやすい職場には自然と優秀な人材が集まります。
しかし、社員食堂を充実させたり、勤務地を駅チカにしたりという必要はありません。根本は、「うちの蔵は、働く人たちのことを考えているよ」という経営陣の姿勢や考え方が見えることが大切なんです。
ご参考までに、他の酒蔵の「ホワイト化」取組事例をいくつかご紹介しましょう。
週休2日実現ありき!
「繁忙期に休日を増やす」「週休2日制の実現」という目標を先に掲げた蔵元さん。
土曜日に洗米をせず、仕込みを日曜日に入れないようにしたり、三段仕込みの「踊り」を2日や3日に分けることで、週当たりの仕込みをタンク2本で回したりして、土日に全社員が休みをとる、繁忙期にとれないときは、閑散期に長休みをとるなどの工夫をして、週休2日制を実現しました。
「当たり前は当たり前じゃない!」~固定観念からの脱却
蔵の働き方改革の基本は、「変わることへのアレルギー」をなくすことだという蔵元さん。
「江戸・明治・大正・昭和・平成と5つの時代を通して同じことをやっていては取り残される」という危機感から蔵の改革を決意。
「酒造りはこうあるべき」「これが当たり前」「頑張ればおいしいお酒ができるんだ」などといった固定観念を捨て、「当たり前は当たり前じゃないかもしれない…」と疑うところからスタートするとして、さまざまな改革にチャレンジ。
勤務時間を5時~15時から8時~17時に変更したり、IT課を設立して遠隔でもろみの温度管理をしたり…
「売上倍で給料倍」の目標を掲げて、チャレンジを続けています。
新時代の仕組みを導入
かつて杜氏を他の蔵に引き抜かれたことをきっかけに、「設備と人には金を使え」の自戒の念を忘れず、後継者である息子さんも教えどおり、給与面をはじめとした労働環境の整備を徹底させています。
1年単位の変形労働時間制を採用し、繁忙期こそ週休1日ですが、そのぶん閑散期には週休3日以上を確保。
月の平均残業時間は1人当たり10時間、深夜労働はなし。さらに、勤怠管理アプリを導入して、労働時間の可視化によって業務効率化を実現。
「労働基準法のグレーゾーンを主張して、他の業界に合わせないようなことをしていては人員確保が困難になるばかり」として、一般企業と同水準の労働時間や休日の規定を採用しています。
個人の適性を見極めて評価できる、労働時間に依存しないフェアな人事評価の採用も模索中。
新時代のさまざまな仕組みを積極的に導入しています。
ユースエール認定の取得
「ホワイト化」の証として厚生労働省が与える「ユースエール認定」を取得している蔵元さん。
「優秀な人材を集めるためには、給料を上げて、労働環境を整備する必要がある」との基本概念から、他にもさまざまな取組みを実施。
ジャグジーやリフレッシュ施設の完備、フォークリフトの大量導入、経費の事後決裁システムの導入、通勤用自動車購入費用補助、希望年俸ごとの課題設定、予算編成の社員提案の受入、新規事業を社員を株主にした別会社で行うなどなど…
頑張れば頑張ったぶんだけ、自身の給与に跳ね返る仕組みを採用。
自分で考えられる人材を育成するために1人1人が経営者となる新時代の酒蔵を目指しています。
蔵の労働環境改善手法

蔵の労働環境を改善するためには何をすればいいのでしょうか?
ここでは、蔵の労働環境を改善するために、いくつか参考になる手法をご紹介しましょう。
変形労働時間制の採用
1年の中で繁忙期と閑散期がある日本酒造り。
繁忙期に発生しやすい長時間労働という課題を解決するためには、「1年単位の変形労働時間制」を採用することも選択肢の1つです。
変形労働時間制とは、月単位や年単位など一定期間内での労働時間を柔軟に調整する制度のこと。
繁忙期に増えた労働時間を、閑散期の労働時間と調整して、年間を通じての労働時間や休日を労働基準法の範囲内に納めることが可能となります。
蔵人にとっては、繁忙期に頑張ったぶん、閑散期には時間に余裕ができ、経営側にとっても年間を通して事業計画が立てられるというメリットがポイントです。
労働に見合った給与制度
給与制度を見直してみることも労働環境の課題解決の選択肢の1つでしょう。
給与制度に関しては、蔵ごとに代々受け継いできた慣習や、人事評価の方法などがあり、一概に手をつけることが得策とは言い切れませんが、見直してみること自体は許容範囲ではないでしょうか。
給与制度の見直しに関しては、各従業員の担当の業務や成果などを詳細に分析することが必要となってきます。
可能であれば、従業員のモラール・サーベイ(勤労調査・意見調査)の実施、人事評価制度の構築などもおすすめです。
給与制度には、さまざまな考え方があります。
欧米型の実力に応じた成果給や、日本の従来の伝統的な年功序列制度など、自身の蔵に適した制度を検討してみることが必要でしょう。
給与制度など、社内規程の改定で悩んだら、専門家に相談して、意見を聞いてみるのも1つの手段です。
安全対策は相談ありき
蔵の安全対策に関しては、昔からの慣習があり、なかなか自身で見直すことが難しいのではないでしょうか。
その場合には、専門家や同業者、他業種の人や労働基準監督署などにヒアリングや相談することをおすすめします。
「蔵の労働環境見直し」はじめの一歩
時代の変化に合わせて蔵の労働環境を改善していく取組みには「これが正解」ということはありません。
重要なのは、「酒造りはこういうもの」「これ以外に選択の余地はない」などと決めつけないこと。多様な発想でチャレンジし続けること。
100蔵あれば、100通りの働き方改革があります。
労働環境の見直しのはじめの一歩は、蔵の現状認識から!
客観的にうちの蔵の労働環境を分析してみましょう。
蔵の労働環境を客観的に分析するには、実際に現場で働いている蔵人の話を聞いたり、自身で現場を見回ったりすることが必要です。
その上で、他の業界や他の酒蔵の事例を参考にして、さまざまな観点から職場の労働環境をチェックすることをおすすめします。
まとめ
ここまで、酒蔵の労働環境問題について深掘りさせていただきました。
「変わっていかなくちゃとは思っているんだけどねぇ…」
「現状を変えるとなると、なかなか腰が上がらなくて…」
ごもっともです。
誰でも変化は怖いですよね。
変化せずに事業継続できるなら、それはそれでいいと思います。
しかし、なかなかそれを許してくれる世の中ではなくなってきているのも事実…
ものは試しに一度現状分析だけでもなさってみるのも精神衛生上いいのではないでしょうか?
アンカーマンでは、今回、回答するだけであなたの蔵の現状がわかるチェックシートをご用意いたしました!
今すぐダウンロードして、セルフチェックしてみてください!
チェックシートのダウンロードはこちらから
働き方改革、労働環境の改善など、ご不明点やお困りごとがあれば、ご遠慮なくアンカーマンまでご連絡ください。
以下のお問い合わせフォームに簡単な必要事項を記入して、「送信する」ボタンをクリック!