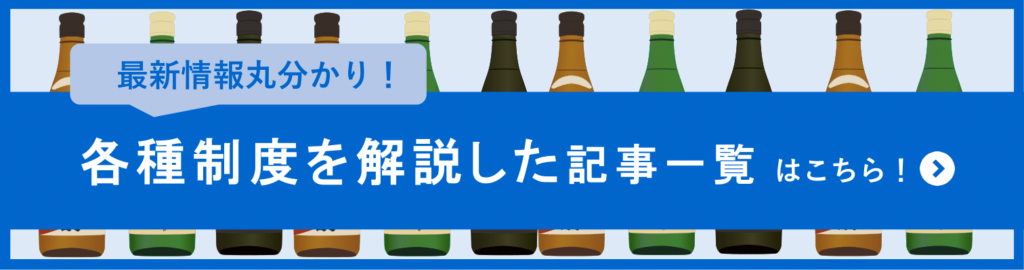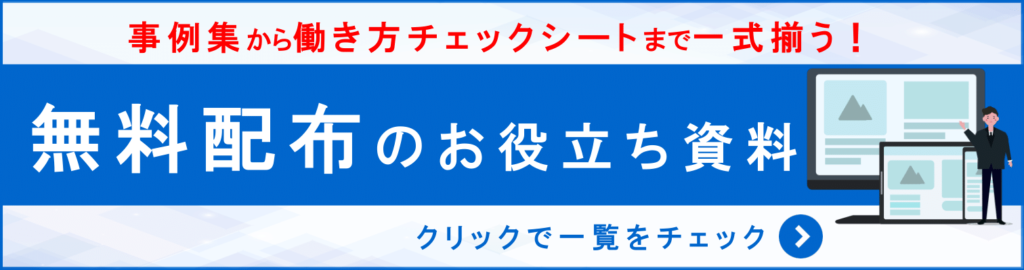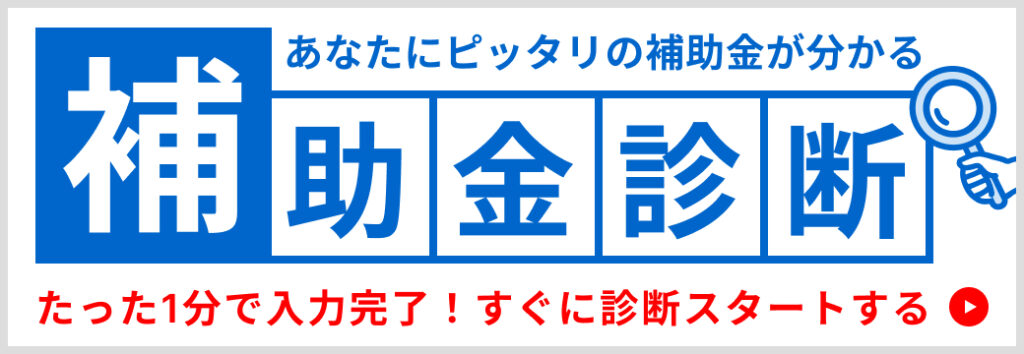造り手確保は「休む×⇒休む◎」のアップデートが重要ってホント?
※2025年2月6日更新

酒造業や酒販業など酒類事業において、造り手や売り手の確保は、将来的な安定経営を考える上でも、解決しなければならない重要な経営課題の1つです。
人材確保の課題を解決するためには、働き方改革の一環として、これまで日本人として当たり前のように染みついていた「休むことはよくないこと」といった既成概念を見直し、「休むことはいいことなのだ」とアップデートを図ることが重要だという考え方があります。
「え〜!!どうして?」と驚く経営者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、酒類事業者が人材を確保するためには、なぜ「休む×⇒休む◎」のアップデートが重要なのかを考察していきます。
なぜ日本人は休まないのか
「休む=悪」のような風潮が、日本の社会には蔓延しています。
ここでは、なぜ日本人は休まないのかということについて解説します。
休めない日本人
他国の人から見た日本人の特徴に対するアンケート調査結果を見ると、「日本人は礼儀正しい」に次いで多いのが「日本人は勤勉である」というイメージです。
また、日本人のセルフイメージのアンケート調査結果を見ても、「勤勉」は上位を占めています。
イメージだけでなく、「休み」の実態調査結果を見ても、「有給休暇の国際比較調査(世界最大の総合オンライン旅行会社エクスペディア・ジャパン2015年調査結果)」によれば、「有休取得に罪悪感を感じる」と回答した人の割合が世界ワースト1位という結果でした。
つまり、自他ともに「休めない(休まない)日本人」という認識は一致しているようです。
日本人はなぜ休めないのか
「日本人はなぜ休めないのか」という問いに対して、 DNAに組み込まれた国民性と考えている人もいるかもしれませんが、科学的に見てもどうやらそういったことでもないようです。
歴史的に見ても、「勤勉さ」というイメージを日本人のアイデンティティとして印象づけたのは、明治時代後期以降の話で、「二宮金次郎像で知られる二宮尊徳の逸話などを駆使して、時の政府が欧米諸国に追いつこうとするためのイメージ戦略」であったとのこと。
製造業が発展していく過程では、日本だけでなく他国でも構造的な超(長)時間労働が見受けられ、一般的にはさまざまな方法で克服されるものですが、日本においては、終身雇用・フルタイム雇用制度などの影響などにより、残存してしまっているとの考察が正しいようです。
日本の製造業の一部では、成果としての仕事の質や量よりも、勤務時間の長さを評価する傾向があったため、「休暇や休憩は取らず、長い時間働くほど評価が高い」といった風潮も見受けられました。
ともあれ、いまだに「休む=悪」という「職場や社会の空気」があることは確かで、「忙しいから休めない」「他の人に迷惑がかかる」などの理由で「休めない日本人」が大量発生しています。
休まないことのデメリット
休まないことのデメリットを科学的に考察してみましょう。
人間には仕事や生活に必要な作業をこなす上で必要な「ワーキングメモリ」という認知機能があります。
ワーキングメモリは、作業記憶や作動記憶とも呼ばれ、短時間に情報を記憶し、その情報をもとに処理する脳の機能のこと。
ワーキングメモリは疲労や睡眠不足によって容易に低下するため、休まないことのデメリットの1つとして、ワーキングメモリの働きが弱くなってしまうということが考えられます。
ワーキングメモリの働きが弱くなると、忘れやすくなる、集中力が続かない、生産性が下がるなど仕事をこなす上での不都合が生じてしまうのです。
また、休みを確保できないと、蓄積した疲労を回復できず作業パフォーマンスを低下させるばかりか、意欲や集中力を高める神経伝達物質のドーパミンで、崩壊寸前の脳を「まだまだ作業を続けられる」とだまし、体調を崩してしまうといったこともあるので注意しなければなりません。
さらに、休まないことのデメリットを、企業の職場環境の状況を見極めるといった観点から考察すると、「休みが確保できない=職場環境がよくない」と判断されてしまい、人材確保が難しくなるといったことも考えられます。
以上のように、「休まないこと」には、さまざまなデメリットがあることを押さえておきましょう。
人材確保にはなぜ「休む◎」のアップデートが重要なのか

日本人が休めない理由や休まないことのデメリットがわかった上で、人材確保になぜ「休む◎」のアップデートが重要なのかについて探っていきましょう。
「休むのはよくないことだと思いますか?」の質問に、「はい、よくないことだと思います」と、多くの日本人が答えるのではないでしょうか。
「休む×」という日本の企業において、働き方改革が注目されている今、「健康経営」というキーワードがポイントとなりそうです。
健康経営とは
「健康経営」とは、企業が従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法です。
従業員の健康を「投資」と捉え、健康増進に取り組むことで、生産性や収益性の向上、医療費の削減など、さまざまな効果が期待できます。
従業員の「休み」を確保することも、健康経営の一環です。
健康経営の取組みを促進するため、経済産業省が「健康経営優良法人認定制度」や「健康経営銘柄」などの制度を設けているほどです。
健康経営のメリット
健康経営には、以下のようなメリットがあると考えられています。
- 従業員の活力向上や生産性の向上
- 組織の活性化
- 業績向上や株価向上
- 企業価値向上
- 採用時の応募数増加
- 法令遵守やリスクマネジメント
特に、健康経営のメリットとして注目すべきは、会社側が、従業員に「休み」を確保させることで、休まないことのデメリットを排除できる点です。
健康経営を行い、「休み×」から「休み◎」のアップデートを行うことで、デメリットをメリットに変えることができ、働き方改革にもつながり、人材確保も容易になるといったことを押さえておくべきでしょう。
人材確保にはなぜ「休む◎」のアップデートが重要な理由
なぜ、従業員の「休む」を確保すると、優良人材を確保できるのでしょうか。
それは、企業の人材確保の観点からは、「休み」の確保ができるかどうかは、職場環境を判断する上での1つの指標となっているためです。
求職者が応募企業を判断する上で、「休みが確保できる企業=良好な職場環境の企業」と判断するため、「休みがしっかりと確保できる職場環境の企業に就職したい」ということで、求職者の応募が増加することが想定され、人材確保しやすくなるといったメリットが考えられます。
このように、企業が、これまで日本の社会で「休む×」と考えられていた風潮を「休む◎」にアップデートすることで、「休みを確保できる=良い職場の1つの指標」ということになり、「良い職場には、良い人材も集まり定着するため、さらに良い職場になる」といった好循環が生まれ、優良人材を確保できることにつながるのです。
「休む」を確保するには何をすべきか
優良人材確保のためには、「休む」を確保することが重要ということがわかった上で、「休む」を確保するには何をすべきかを考える必要があります。
ここでは、「休む」を確保するために必要なことについて解説します。
健康経営の取組み例
ます、「休む」を確保するために必要な健康経営の取組み例を見ていきましょう。
健康経営の取組み例には、以下のようなことが考えられます。
- 従業員の健康に関する取組みについての調査や分析
- 健康経営が経営理念や方針に位置づけられているかどうかの確認
- 健康経営に取り組むための組織体制の構築
- 健康経営に取り組むための制度の整備
- 健康経営の取組みを評価し、改善に取り組む
現状、健康経営に取り組んでいない企業が、健康経営に取り組むためには、現状分析を行い、組織体制や業務フローなどを見直し、業務改善に取り組むことが必要です。
たとえば、組織体制や業務フローの大幅な改善を必要としない取組みから着手することも選択肢の1つとなるでしょう。
酒類事業者が「休む」を確保するために必要な選択肢
酒蔵や酒販店など酒類事業者が「休む」を確保するためにまず行うべきことは、事業の洗い出し(現状分析)を行い、今すぐできる改善策と組織体制や業務フローの大幅な改善を必要とする改善策に分類することでしょう。
現状分析を行った上で、自社に適した改善策の選択肢を洗い出し、計画を立案することが必要です。
酒類事業者が「休む」を確保するために必要な選択肢として、設備投資を行うといったことも選択肢の1つに挙げられます。
「休み」を確保する選択肢としては、大きな決断かもしれませんが、蔵や店の将来を考えたとき、設備の更新をして、将来的な安定経営を図るというメリットも併せて考えることも必要でしょう。
設備投資をして、生産性を向上させ、空いた時間を従業員の「休み」に回すことで、職場環境の改善を図るといった選択肢も検討することをおすすめします。
補助金活用による設備投資
設備投資を行う上では、補助金の活用を検討することをおすすめします。
補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、短期間での設備更新が実現するからです。
設備投資をすることにより、経営の安定化と従業員の労働環境の改善を同時に図ることができ、最新の技術を取り入れることで、酒質向上にもつながり、消費者からの評価も高まることが期待できます。
さらに、補助金を活用して設備投資を行うことで、従業員が効率的に働ける職場環境を整えることができ、従業員が「休み」を確保することができるため、企業全体の生産性が向上することも押さえておきましょう。
従業員の健康と生産性の向上を両立させることが、企業の持続的な発展には欠かせません。
酒類事業者が「休む」を確保するための具体的取組み
酒類事業者が「休む」を確保するための健康経営の具体的取組みには、以下のようなものがあります。
・最新設備の導入:
自動化システムや最新の醸造技術の導入により、生産効率アップを図る
・休憩スペースの充実:
従業員がリフレッシュできる休憩スペースを設けることで、リラックスできる環境を提供する
・長時間労働の禁止:
醸造スケジュールや工程の見直しや、必要な設備投資などにより、早朝・深夜作業、泊まり込みの廃止などを図る
・健康管理プログラム:
定期的な健康診断やメンタルヘルスケアを行い、従業員の健康をサポートする
これらの取組みを通じて、酒蔵の働き方改革が進み、生産性向上と従業員の「休み」の確保が実現します。
まとめ

ここまで、酒類事業者が人材を確保するためには、なぜ「休む×⇒休む◎」のアップデートが重要なのかをさまざまな観点から考察させていただきました。
補助金を活用して、設備投資を行い、生産性アップを図ることで、時間に余裕が生まれ、空いた時間を「休み」に回すことが可能です。
健康経営の観点からは、従業員の「休み」が確保できている職場は、良い職場であるといった1つの指標となるので、良い職場には優良人材が集まり定着し、さらに良い職場になるといった好循環が生まれます。
こうして酒類事業者の経営課題である人材の確保が解決していくという道筋が見えてくるのです。
「休む×⇒休む◎」のアップデートの手段の1つとして、ぜひ補助金活用をご検討ください。
アンカーマンでは、補助金活用のご相談だけでなく、人材採用のご相談もお受けしています。
人材採用には、酒類事業に特化した人材紹介サポート「酒蔵エージェント」のご活用もご検討ください。
酒蔵ツーリズム インタビューはこちらから!
お酒メーカーに役立つ制度一覧はこちらから!
酒税法改定、事業再構築補助金など事業継続・事業拡大に関わる
大切な制度について詳しく解説している記事一覧はこちらから!
お役立ち資料はこちらから!
設備導入事例集やアフターコロナの今取るべき戦略、働き方チェックシートまで
知りたいことが一式揃うお役立ち資料一覧はこちらから!
補助金診断はこちらから!
おすすめの補助金がすぐに分かる補助金診断を試してみませんか?
1分で完了する補助金診断はバナーをクリック!
補助金申請無料モニター募集中!
株式会社アンカーマンで補助金申請サポートをまだ受けたことがない方を対象に、
補助金申請無料モニターを不定期で募集しています!
応募にご興味をお持ちの方は、下記をチェック!
無料相談はこちらから!