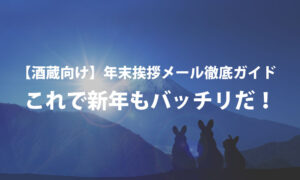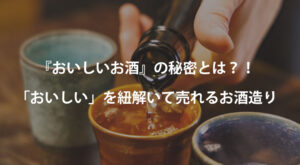【知らないと損をする】インボイス制度~あなたの蔵は大丈夫?2023年スタートのインボイス制度に備えよう!
※2023年1月8日更新
最近よく、「インボイス」というキーワードを耳にすることはありませんか?
「なんか、2023年からインボイス制度がスタートするらしいけど…」
「そもそも『インボイス』ってなに?」こんなお声を聞くことがあります。
「インボイス」とは、直訳すると「請求書」のこと。
「請求書なら、これまでも出してるけど…何が変わるの?」
皆さん、こう思いますよねぇ…
実は、消費税に関連して、皆さんが日常行っている商取引が少し変わります!
これが2023年10月1日からスタートするとあって、数年前から騒がれているんです。
(実は、消費税が現状の10%に決まった平成30年度税制改正により、経過措置を経て、消費税インボイス制度が導入されることが決まっていて、現在はまさに経過措置期間です。)
税金関連なので、国税庁を中心として、国民に周知徹底を図っているのですが、どの表現も難しくてわかりづらい…
そんなわけで、今回は、直近に迫った「インボイス制度」について、「インボイスってなに?」「酒蔵にはどんな影響があるの?」「どんな準備が必要?」などなど、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
今さら聞けない「インボイス制度ってなに?」

まずは、はじめての人でもわかるように、インボイス制度について理解していきましょう。
ここでは、インボイスやインボイス制度の概要、制度導入で何が変わるのかなどについて解説します。
インボイスってなに?
「インボイス(invoice)」とは、「請求書」や「送り状」のこと。
主に貿易など海外に貨物を輸送する通関業務などで登場します。
「請求書」として使用する場面では、一般的に価格の明細書、請求書、納品書などを兼ねますが、日常生活ではあまり聞き慣れませんよね?
しかし、ここ数年、「インボイス制度」という新しい制度が誕生したことにより、ビジネスの場面で耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
インボイス制度における「インボイス」とは、消費税に関する正確な適用税率や消費税額等を伝えるものと理解しておきましょう。
インボイス制度とは

「インボイス制度」とは、正式には「適格請求書保存方式(※1)」と呼ばれ、適格請求書(インボイス)(※2)を仕入先とやり取りすることで、「消費税の仕入税額控除」を受けられる制度です。
「インボイス制度」が今ひとつ理解できないという人が引っかかるポイントが、この「仕入税額控除」という税金の話になってしまうからです。
「税金のことは税理士さんにお任せ!」という方も多いので、わからないのは当然かと…
「仕入税額控除」とは、簡単に説明すれば、消費税が安く抑えられる「ありがたい仕組み」のこと。
「インボイス制度」とは、これまで普通に利用できた「ありがたい仕組み」が、「登録された事業者(適格請求書発行事業者※3)から受け取ったインボイスがないと、利用できませんよ」という制度です。
※1:適格請求書保存方式…現在利用されている「区分記載請求書等保存方式」という経過措置を経て、2023年(令和5年)10月から本格実施が予定されている制度の特徴は以下のとおり
・仕入税額控除の適用にはインボイスの保存が必要
・買い手からの請求により売り手はインボイスの交付義務あり、不正交付の罰則あり
・免税事業者の交付不可
・免税事業者との取引は仕入税額控除不可(ただし6年間の経過措置あり)
※2:適格請求書…以下の記載事項をすべて記載した請求書であり、相手事業者が消費税を納税することを証明する「納税証明書」の役割を果たすので、インボイスがあってはじめて消費税の仕入税額控除を受けられ、消費税が安くなる
・取引年月日・取引内容(軽減税率の対象品目である旨含む「※印等で記載可」)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
・税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額・地方消費税額の合計額)
・適格請求書発行事業者の氏名(名称)・登録番号
・適格請求書受領者の氏名(名称)
※3:適格請求書発行事業者…インボイスを発行できる事業者
適格請求書発行事業者になるには登録が必要:原則として、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請手続きをする必要あり(期限までに困難な事情で登録申請できなかった場合、2023年(令和5年)9月30日までは困難な事情を記載して登録申請可能)
・登録は任意
・登録は課税事業者であることが必要:免税事業者も登録できるが、「登録=課税事業者」となる
・買い手から預かった消費税を納税する義務あり
・インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は必ず消費税の申告をする事業者となる
※参照:インボイス制度の詳細は国税庁の特設サイトまで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
どうしてインボイス制度が導入されるの?
インボイス制度が導入される目的は、取引における正確な消費税率と消費税額の把握です。
消費税の税率は、現状、原則10%と軽減税率8%という2種類の税率が併存しています。
風数の税率に対応することが目的の1つです。
また、免税事業者は、消費税を買い手から徴収しても消費税納税義務がないため、合法的に本来納付すべき税額と差額(益税という)が生じます。
さらに、「受取消費税-支払消費税」の計算式で算出する原則とは違い、例外的な取扱いである「簡易課税制度」(受取消費税-受取消費税×仕入率)によっても合法的に「益税」が発生します。
これらの益税をなくすことも目的の1つです。
インボイス制度導入でどう変わるの?

インボイス制度が導入されると、請求書や領収書の発行・保存のルールが大幅に変わります。
具体的には、以下のような可能性が懸念されています。
・管理が大変になる
・納税額が増える
・取引相手が変わる
以上のようなことがあり、これまでの取引の慣例が変わってしまう可能性があるので、世間でも注目されているのです。
酒蔵は何を準備すればいいの?

インボイス制度が理解できたところで、酒蔵としてどんな準備を行えばいいのでしょうか。
ここでは、酒蔵がするべき「インボイス対応」について解説します。
酒蔵としてどうすべき?
酒蔵の事業の中で、仕入など買い手になる場面と、商品の売り手になる場面とがあるでしょう。
インボイス制度において、売り手と買い手の見直すべきポイントが異なるのでご紹介します。
【インボイス制度売り手と買い手の見直しポイント】
売り手側の事業者が見直すべきポイント
- 適格請求書発行事業者へ登録するか否かの決定
- インボイスに対応した機器やシステムの導入
買い手側の事業者が見直すべきポイント
- 仕入先・外注先が適格請求書発行事業者かどうかの確認および今後取引を継続するか否かの判断
- 簡易課税制度を適用するか否か(簡易課税制度を適用する場合、インボイスの保存は不要)
- 仕入・経費取引でインボイスが必要なものと必要ないものとの仕分け(3万円未満の交通費、日当などインボイス保存不要となる特例あり)
- 仕入先・外注先からの請求書がインボイスの記載事項を満たしているかの確認
- 請求書の保存・管理方法
- 帳簿への記載方法・仕入税額の計算方法
もっとも重要なポイントは、適格請求書発行事業者へ登録するか否かの判断でしょう。
既に課税事業者である場合には、今後の取引を考えて、登録するほうがよいでしょう。
問題となるのは、現在、免税事業者であるケースです。
登録要否の判断は、「取引先がインボイスを必要とするか」「免税事業者の場合には登録を受けると課税事業者としての申告が必要となるがそれでもよいか」など自社の事業内容などに応じて検討しましょう。
また、付随的なところでは、インボイス対応の受発注システム、請求書管理システムなどの導入・改修・入れ替えなどを見直すことも必要かもしれません。
担当税理士との打ち合わせも行いましょう。
何を準備すればいいの?

酒蔵として、インボイス制度対応への準備としては、以下のようなことが挙げられます。
- 適格請求書発行事業者への登録申請
- 請求書・領収書などの新様式への切り替え作業
- 仕入業者・外注業者の選定
- 消費税に関する担当税理士との打ち合わせ
- 電子帳簿保存法への対応
特に、仕入業者・外注業者の選定は重要です。
仮に、これまで取引してきた仕入業者や外注業者の中に免税事業者がいる場合には、消費税の「仕入税額控除」を受けられなくなるデメリットと、取引先としての信用などのメリットを比べて業者選定しなければなりません。
取引を継続する場合でも、自身の蔵が損しないように、消費税分(あるいはそれに近い分)の値引き交渉などが必要となってくるでしょう。
なお、この点に関しては、公正取引委員会から、消費税の値引行為をしないようにとの通達があることも念頭に置いておきましょう。
※参照:公正取引委員会「消費税転嫁対策コーナー」
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/
知っておいたほうがよいポイント
酒蔵のインボイス対応について、知っておいたほうがよいポイントがいくつかあります。
ここでは、インボイス制度導入にあたって、実際の取引に与える影響など、知らないと損をするポイントなどをご紹介します。
納税額が増えてしまうかも

誰でも支払う税金を安く抑えたいもの。
今回のインボイス制度の導入は、これまでの消費税の取扱いを変えるものです。
知らないでインボイス対応しないと、消費税の納税額が増えてしまうかもしれません。
具体的には、消費税の納税額を算出する際に、「仕入税額控除」という消費税の二重払いを回避して、消費税額を抑える仕組みを利用しています。
この制度は、課税業者が、商品・サービスの提供などにより、お客様から受け取った消費税から、仕入などにより取引業者に支払った消費税を差し引く制度です。
仕入先が免税業者であっても利用できていた「仕入税額控除」が、インボイス制度導入以降は、段階的(※)に利用できなくなることにより、その分、納める消費税額が増えてしまうことになります。
※段階的とは…以下のような経過措置があります。
・インボイス制度実施後3年間(2026年10月まで):80%控除可能
・インボイス制度実施後6年間(2029年10月まで):50%控除可能
・インボイス制度実施後7年目以降(2029年10月以降):控除不可
取引相手が変わるかも
慣れ親しんだ取引相手から仕入れたいとは誰しも思うこと。
しかし、インボイス制度が導入されると、「取引相手(インボイス非対応業者)によって消費税額が増えてしまうかもしれない」という懸念があるため、取引相手を変えなければならないかもしれません。
「同じものを買うなら税金が抑えられるインボイス対応業者にしよう」という考えが働くからです。
インボイスの電子保存は電子帳簿保存法の対応が必要

インボイスをPDFなどデータ化してメールで送るなど、電子的にやり取りする「電子取引」に該当する場合で「電子的に保存する場合」には、改正電子帳簿保存法に準拠して対応する必要があることを押さえておきましょう。
具体的には、インボイスを得意先に「電子的」に送る場合、以下のいずれかの対応が必要となります。
- タイムスタンプ付インボイスを送信
- インボイスを送信後、タイムスタンプを付与してインボイスを保存
- 訂正削除ができない、または履歴が残るクラウドサービスによりインボイスを送信(タイムスタンプは不要)
- 原則、訂正削除をせず、仕方なく訂正削除する場合には所定の申請書により社内承認を得るとした「社内規定」を整備
インボイス制度は消費税に関する制度、電子帳簿保存法は所得税法に関する制度です。
電子インボイスを作成したのに、「紙」で保存する場合、消費税の仕入税額控除は受けられますが、所得税に関しては、「適切に保存されたエビデンスがない」状況になり、申告漏れで重加算税を課せられるなどのリスクがあるため、電子インボイスを作成した場合には、電子帳簿保存法に準拠して保存することをおすすめします。
まとめ
ここまで、目前に迫ったインボイス制度に関して、酒蔵としてどのように対応すべきかについてご紹介させていただきました。
「インボイス対応、何からはじめればいいのかなぁ?」という方は、まずは、「適格請求書発行事業者」の登録をするか否かを決定するところからはじめましょう。
既に、登録申請受付は開始されていますので、登録をする必要がある方は、令和5年3月31日までの登録申請期限ギリギリではなく、早めに準備を開始することをおすすめします。
インボイス制度への対応については、受発注システムや経理システムなどが必要になってくるでしょう。
そのシステム、補助金で導入できます!
お気軽にアンカーマンまでご連絡ください。
以下の専用フォームに「インボイス対応補助金相談希望」とご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!
ご連絡お待ちしています。