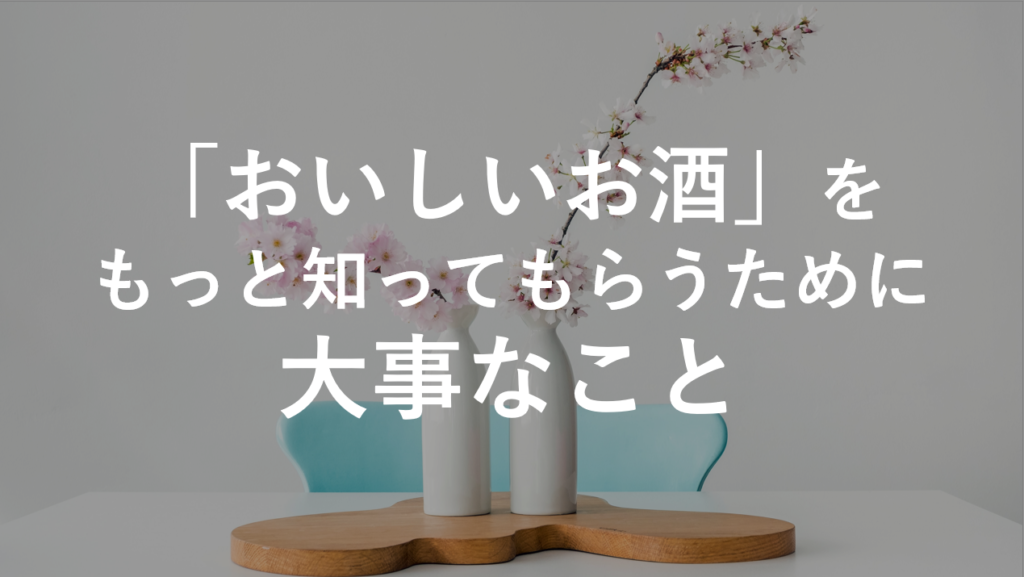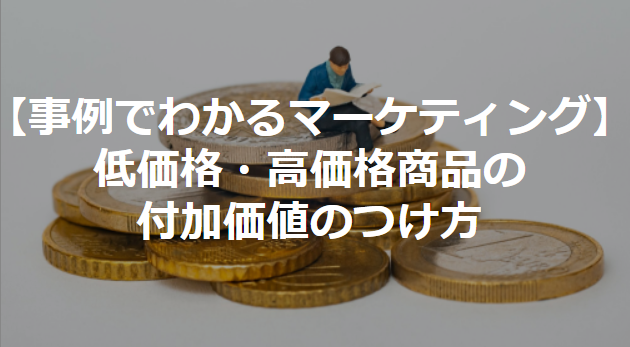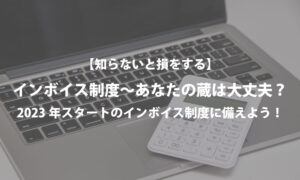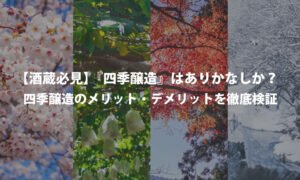『おいしいお酒』の秘密とは?!「おいしい」を紐解いて売れるお酒造り
「おいしいお酒を造れば売れる!」
本当にそうでしょうか?
そもそも「おいしい」とはなんなのか?
きちんと理解している人はどれくらいいるでしょう。
「おいしい」とは感情の一種といわれ、個人差、体調、環境などによって「おいしさ」が違うということがわかっています。
「人によって」「体調によって」「環境によって」おいしいの感じ方が違い、いつでも、誰でも、おいしいとか、絶対的においしいということがないのなら…
売れるお酒を造るには、「おいしい」を紐解いていく必要がありそうですね。
今回は、『おいしいお酒』の秘密について解説していきましょう。
「おいしい」を紐解く
「おいしい」を紐解く上で、「おいしい」の仕組みや要因を知る必要があります。
「おいしさ」を構成する2つの要因は、「飲食物側の要因」と「飲食する人側の要因」です。
ここでは、「飲食物側の要因」としての「おいしい」のメカニズム、「飲食する人側の要因」としての「5つのおいしさ」について解明していきましょう。
「おいしい」のメカニズム

飲食物を口に入れたときに感じる感覚を総称して「味」「味覚」といいますが、味覚は、生理学的に、5つの基本味(5原味)「甘味(甘い)」「旨味(うまい)」「酸味(すっぱい)」「塩味(しょっぱい)」「苦味(苦い)」から構成されています。
「あれ?味って他にもなかった?」
そうです、他にも味はあります。「香味」「渋味(渋い)」「辛味(辛い)」「えぐ味」「金属味」など。
しかし、5原味以外は、味覚細胞によって判断される味覚には含まれず、皮膚で感じる触覚です。
ただし、香味だけは香りを嗅覚でとらえて感じる味です。
「おいしい」のメカニズムは、次のとおりです。
- 飲食物が口の中に入ると、飲食物に含まれる味覚を引き起こす化学物質(味物質)が舌に触れます。味物質とは、甘味「糖」、旨味「グルタミン酸」、酸味「酸」、塩味「ナトリウムイオン」、苦味「キニン」などです。
- 接触する味物質が一定以上の濃度になると、舌にある味蕾(味細胞)を通じて、信号として脳に伝えられ、味(味覚)を認識します。
- 脳は、認識した「味覚」「舌触り・食感(触覚)」「香り(嗅覚)」「見た目(視覚)」「咀嚼音(聴覚)」などの感覚や食事の雰囲気や環境などを総合的に分析して、「快い(おいしい)」か、「不快(まずい)」かを判断します。
5つの「おいしさ」
飲食する人がおいしいと感じる要因には、「生理的」「習慣的」「精神的」「先天的」「環境的」の5つのおいしさがあります。以下、順に解説しましょう。
生理的おいしさ
「生理的おいしさ」とは、身体が本能的に欲するものを口にしたときにおいしいと感じるおいしさです。
たとえば、次のような事例があります。
- 空腹時に摂取するカロリーになりやすい「糖分」や「脂肪」。旨みのある濃醇で甘口の日本酒など。「空腹は最高の調味料」とも言われる。
- 喉が渇いているときに飲む冷たい水やビールなど。
- 汗などかいて身体の塩分濃度が低くなっているときの食塩など。
- 身体が疲れているときのクエン酸などの有機酸など。疲れると酸味を感じる味覚が弱まり、新陳代謝を促進させようとして、酸っぱいものがおいしく感じる。
- 精神的に疲れているときは、苦みの感覚が弱まるため、苦みの多い薬効成分のブラックコーヒーなどがおいしく感じる。
習慣的おいしさ
「習慣的おいしさ」とは、飲食に慣れているものを口にしたときにおいしいと感じるおいしさです。
飲食に慣れているものは、安心して飲食できるのでおいしく感じます。
たとえば、「お袋の味」などが代表例。
子供の頃、お母さんが作るお砂糖たっぷりの卵焼きを食べていた方は、大人になっても、だしや塩気の強い卵焼きよりも、甘くて黄色い卵焼きのほうが、好みの方は多いはずです。
お酒も飲み慣れている銘柄をおいしく感じるのは、この習慣的おいしさです。
精神的おいしさ
「精神的おいしさ」とは、精神的要因からくるおいしさです。
食品に関する情報から食べる前に味わいをイメージして、実際に口にしたときの感覚がイメージに合っていると「おいしい」と感じ、イメージと違っていると「まずい」と感じます。
情報とは、容器の色・形、ラベル、裏張りの説明文、周囲の反応・口コミ・評判などさまざまです。
また、感情や緊張によってもおいしさの感じ方が違うことがあります。
緊張して、味がよくわからないなどの事例も、精神的おいしさです。
先天的おいしさ
「先天的おいしさ」とは、人種・民族・年齢・性別・体質など人が生来持っている先天的要因からくるおいしさです。
子どもの頃はワサビやからしをおいしく感じないが、大人になるとおいしく感じられたり、お酒の強い・弱いだったり、先天的おいしさに関係するものは意外とあります。
環境的おいしさ
「環境的おいしさ」とは、食事のときの環境に関係してくるおいしさです。天候・気温・湿度などの気象状態、季節の寒暖、室内装飾や照明、食事している場所や食器などさまざまな環境要因によって、おいしさが違ってきます。
お酒も、おしゃれな店内で素敵なグラスで飲むと、より一層おいしいのは環境的おいしさです。
おいしいお酒の秘密とは

「おいしい」を紐解いたら、次のステップとして、いよいよ「おいしいお酒の秘密」に迫っていきましょう。
ここでは、お酒の独特のおいしさを紐解き、日本酒のおいしさのバリエーションも深掘りしていきます。
お酒の「おいしさ」を紐解く
お酒の「おいしさ」はある種、他の飲食物とは一線を画す独特のものがあります。
ここでは、お酒の「おいしさ」を紐解いていきましょう。
人間だけの特殊な嗜好
味覚や嗅覚は、本来、人間だけでなくすべての動物が生きていくために必要な感覚です。
味覚は、口に入れた飲食物が、栄養成分(「甘味」「旨味」「塩味」)なのか、または腐敗・有害成分(「酸味」「苦味」)なのかを見分け、飲み込むか吐き出すかを判断するための機能となります。
人間以外の動物は、甘味・旨味を好み、酸味・苦味を嫌うという本能的嗜好が備わっているのです。
しかし、人間だけは、本能的嗜好だけでなく、ビールの苦味やワインの酸味といった酸味や苦味を好む場合があります。
これは、本能的に危険だと感じながらも、経験的には安全だということがわかっているからです。
また、「嗅覚」に関しても、上立香(口に入れる前の香り)や口中香(口に入れたときの香り)により、経験から「おいしい」「まずい」を識別し、食べるかどうかを判断するための機能が備わっています。
このように、人間だけが特殊な嗜好性を持ち、味覚や嗅覚から、本能的嗜好以外の「おいしさ」を経験的に判断できるため、お酒など、本来動物が敬遠する酸味や苦みを伴う飲食物でも、人間は「おいしさ」を感じるのです。
そのためには、香りと味の調和も重要となってきます。
日本酒のおいしさには香りも重要
お酒のおいしさを極めるには香りも重要です。
日本酒の香りは、お米を削れば削るほど香り高くなるので、精米歩合が低いほど香りがよいとされています。
また、清酒には「吟醸香」「熟成香」という2つの香りがあります。
「吟醸香」とは、酵母が低温でゆっくり発酵することによって生成される果実のような香りです。
きれいで軽快な甘味と酸味であり、貯蔵中に増えることはないので、アピールするにはフレッシュさを維持する必要があります。
冷やして飲むとおいしいので、「冷酒」などに適しています。
「熟成香」は、貯蔵中に酒の中のアミノ酸や糖分が複雑に反応して、深み・コクなどの味わいと一緒に生成されます。
温めて飲むとおいしいので、「熱燗」などがおすすめです。
日本酒の味わい
日本酒は、米と麹と水を原料とする醸造酒の一種です。
糖化と発酵を並行して行い、日本独自の製法で作られる清酒。「吟醸酒」「大吟醸酒」「純米吟醸酒」などさまざまな種類があります。
仕込みには、「生もと」「山廃」などがあり、味わいも「薫酒」「爽酒」などさまざま。「冷」「熱燗」「常温」など温度によって香りや味わいに変化をつけられます。
日本酒でよくいう、「甘口」「辛口」とは、飲む人の感覚によるところが大きく、一般的には、米とアルコールの比重の差によって変わってきます。
「甘口」は、米の比重が多く、養分がたっぷり残っているもので、「辛口」は、アルコール分が多く、さっぱりとした味わいです。辛口といっても、からしのような辛さではなく、甘味が少ないものを辛口と呼びます。
甘辛度を表す単位は「日本酒度」(一般的に商品の裏張りに記載)で、日本酒度計で測定した日本酒度の(-)の数値が大きいほど甘く、(+)の数値が大きいほど辛いとされています。
市販されている一般的な清酒の日本酒度の平均値は(+)3ですが、(-)10から(+)15くらいまでの幅があるようです。
日本酒のおいしさのバリエーション
日本酒のおいしさのバリエーションを把握しておくこともおいしいお酒の秘密に迫るには重要です。
ここでは、日本酒のおいしさに関係する産地や若い世代のお酒の好み、日本酒のおいしい飲み方などを解説しましょう。
産地も重要

日本酒は、原料からお酒に合った品種を選んで製造するので、地域の気候や風土の特色が色濃く反映されることが多く見受けられます。
最近では、産地の料理とマリアージュするお酒も数多く、食とお酒のペアリングのバリエーションも拡大の傾向です。
若い世代のお酒の好み

若い世代のお酒の好みを把握しておくことも重要です。
若い世代には、ビールやワインが人気ありますが、その理由は、「オシャレだから」「健康にいいから」などなど。
日本酒も負けず劣らず人気があります。
その理由としては、「和食だけでなく、洋食にも合うから」「翌日に残らないから」「蔵元によって味の違いが感じられるから」「甘くて濃いお酒から、水のような味わいのお酒まで幅広いから」「旅先で地酒も飲める楽しみがあるから」「アルコールのきつさを感じなく飲みやすいから」などさまざまです。
特に、日本酒初心者には、「アルコール度数低め」「甘口」「香り高い」ものがおすすめとされていることから、若い世代にはこれらの特徴の日本酒の人気が高いようです。
お酒をおいしく飲むには?

日本酒のおいしい飲み方の情報を把握しておくことも、おいしいお酒造りに活かせるのではないでしょうか。
日本酒をおいしく飲むには、「水と共に」「食事と共に」「適正な量」というポイントがあります。
日本酒をおいしく飲む工夫の1つとして、「和らぎ水(チェイサー)」とともに飲むことがおすすめです。
日本酒と同量か1.5倍の常温水を日本酒と交互に飲むことで、体内のアルコール濃度を下げ、脱水症状を緩和し、口の中をリセットする効果があります。
日本酒を食事とともに飲むこともおすすめです。体内へのアルコールの吸収速度を遅らせ、二日酔い防止が期待できます。
日本酒をおいしく飲むには、適正な量を知っておくことです。性別、体質によって適正量は異なります。
「節度ある適度な飲酒」の目安としては、1日平均純アルコールで約20g程度、清酒(1合180㎖)であれば、アルコール度数15%で純アルコール量22gです。
参照:厚生労働省「21世紀における国民健康づくり運動<健康日本21/アルコール>/現状と目標/節度ある適度な飲酒」
売れるお酒を造るには
「おいしい」を紐解いて、おいしいお酒の秘密のドアを開くことに成功したあなたは、いよいよ売れるお酒造りのステップへと入ります。
ここでは、売れるお酒造りのノウハウに迫っていきましょう。
「おいしい」にはバリエーションがある
「おいしい」にはバリエーションがあり、「人によって」「体調によって」「環境によって」おいしいの感じ方が違い、いつでも、誰でも、おいしいとか、絶対的においしいということがないということは理解していただけたでしょうか?
このことを理解していない人は、「おいしいお酒を造れば売れる」という勘違いをしたままでしょう。
「おいしい」のバリエーションを理解したあなたは、もはや「おいしいお酒」の定義が変わっているはず…
「おいしいお酒」とは、すべての人にとっておいしいお酒ということではなく、個人差、体調、環境などさまざまな要素によって異なる「おいしさ」が数多くあるということを念頭に置いておきましょう。
「おいしい」のターゲットを絞ろう
「おいしい」にはバリエーションがあるので、あなたの蔵にとっての「おいしいお酒」=「売れるお酒」にするためには、数ある「おいしい」の中からターゲットを絞ることが重要です。
売れるお酒を造るために、「おいしさ」を追求するということは、うちの蔵では、どの「おいしい」に照準を合わせてお酒造りをするのかを選択することに他なりません。
たとえば、生理的おいしさにターゲットを絞って、夏季限定酒として、低アルコール&スパークリング(サイダーのようなもの)商品を開発する取組みなど。
また、外国へ輸出するときは、地域の味覚を研究して、好まれる味のお酒を造ることで、定番酒×リピーターの組み合わせで最強のファンにさせることが期待できます。
さらに、精神的おいしさの観点から、パッケージと味のイメージを一致させるお酒造りへの取組みなど、おいしいお酒の秘密を理解することで可能になるのです。
まとめ
ここまで、売れるお酒造りのために、「おいしい」を紐解いて、おいしいお酒の秘密に迫ってきました。
「おいしいお酒を造れば売れると思っていたけど、お酒のおいしさを細かく分析して、どのおいしいにターゲットを絞るのかが重要なんだね!」
もちろん、おいしいお酒を造るだけでなく、売れるお酒にするためには、「どれだけ世の中の人に知ってもらえるか」「指名買いしてくれる蔵のファンを増やせるか」などのブランディングやマーケティングが必要となってきます。
補助金サポートで知られているアンカーマンですが、おいしいお酒造りのためのブランディングやマーケティングのトータルサポートも行っています。
売れるお酒造りで、お困り事やご不明点等あれば、お気軽にアンカーマンにご連絡ください。
以下のお問い合わせフォームに無料相談希望とご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!
また、今回の記事が参考になった方は、『おいしいお酒』に関する次の記事もどうぞ!