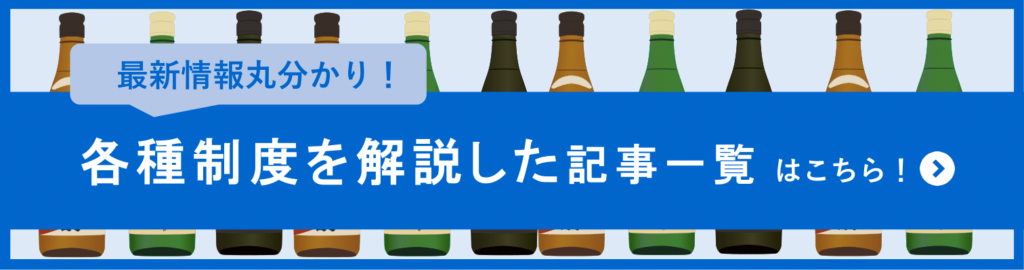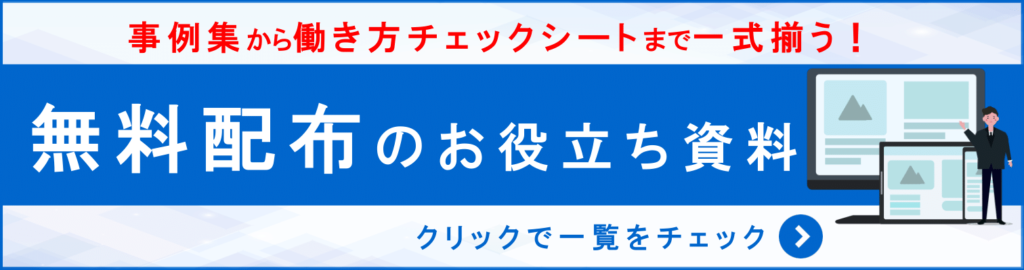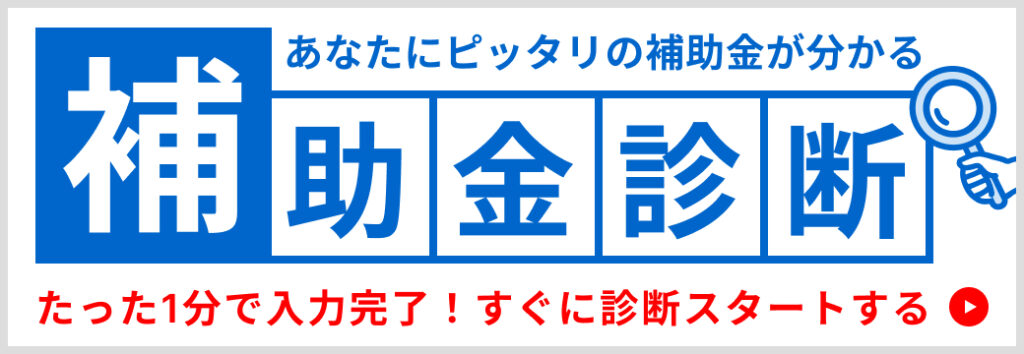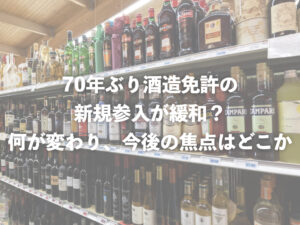どうなる酒業界!?飲み屋がヤバい!生き残りの鍵は販売チャネル改革
※2025年6月2日更新

日本の飲食業界にいま、大きな危機が訪れています。
コロナ禍が収束したにもかかわらず、飲み屋の閉店が後を絶ちません。
経済の不安定さや消費者のライフスタイルの変化が影響し、酒業界全体が厳しい局面を迎えています。
特に、飲食店への卸売に依存する酒造メーカーにとって、この状況はピンチであり、飲食店の減少と売上低迷により、酒類の流通が滞り、これまでのビジネスモデルでは生き残りが難しくなっているのです。
今こそ、ピンチをチャンスに変えるべく、新たな改革が必要です。
生き残りの鍵は、「販売チャネルの改革」!
EC販売の強化、サブスクリプションサービスの導入、体験型イベントの開催、さらには海外市場への展開など、新たな販路を開拓することで、酒業界は未来を切り拓くことができるはず。
本記事では、酒業界が直面する課題とその解決策についてくわしく考察していきます。
- 1. 飲食業界に吹き荒れる逆風、続く倒産の波
- 2. 販売チャネルとは
- 2.1. オンラインとオフライン
- 2.2. 直販・卸売・オムニ・海外
- 3. 【販売チャネル改革】卸売依存からの脱却が鍵
- 4. 酒造メーカーが取り組むべき販売チャネル多角化の戦略
- 4.1. ECサイトによる直販の強化
- 4.2. サブスクリプションサービスの導入
- 4.3. 体験型イベントの開催
- 4.4. 海外市場への進出
- 4.5. 飲食店との共同開発
- 5. 販売チャネルの多角化までのステップ
- 5.1. ステップ1:現状分析と課題の把握
- 5.2. ステップ2:ターゲットと戦略の設定
- 5.3. ステップ3:チャネルの選定と導入準備
- 5.4. ステップ4:マーケティングと集客戦略
- 5.5. ステップ5:運用と改善の継続
- 6. まとめ:今こそ販売チャネル改革を進めるとき
飲食業界に吹き荒れる逆風、続く倒産の波

コロナ禍の収束後、人々の生活も平穏な日常を取り戻し、外国人観光客やサラリーマンの「ちょいと一杯」需要が戻り、夜の街も賑わいを見せています。
この流れで、飲食業界もコロナ前の活況を取り戻すものと思われていましたが、なぜか酒を提供する飲み屋の倒産が止まりません。
直近の「東京商工リサーチの調査」によれば、2024年度の「飲み屋」業界の倒産件数は過去最多の276件に達しました。
これは前年度の235件から17.4%増となり、1989年度以降で最多を更新しています。
倒産の主な要因は、以下のとおりです。
| 要 因 | 内 容 |
| 値上げの難しさ | 物価高騰によるコストアップを価格転嫁できず収益が圧迫 |
| 食材・光熱費の高騰 | 円安の影響もあり、食材費や光熱費が上昇し、経営を圧迫 |
| 人件費の増加 | 従業員確保のための賃金アップが避けられず、コスト負担が増加 |
| 客足の戻りが鈍い | コロナ禍の影響が続き、特に小規模店舗では客足が回復せず、販売不振が倒産の約9割を占める |
特に「酒場・ビヤホール(居酒屋)」の倒産は185件(前年比6.9%増)、「バー・キャバレー・ナイトクラブ」は91件(前年比46.7%増)と大幅に増加しています。
飲み屋閉店の影響は、酒蔵など酒造メーカーにも及び、特に、飲食店への卸売に依存している場合、この倒産の波に巻き込まれやすくなるのです。
取引先である飲食店が減少すると、酒の流通量も落ち込み、売上が厳しくなります。
今後、酒類業界で生き残るためには、販売チャネルの改革が急務かもしれません。
販売チャネルとは
販売チャネルとは、商品やサービスを消費者に届けるための流通経路や方法のこと。
企業がどのように商品を市場に供給し、顧客へ販売するかを決定する重要な要素の1つです。
ここでは、販売チャネルの改革を行う前提として、販売チャネルの種類について解説します。
オンラインとオフライン
「販売チャネルを「ネット活用の有無」や「対面・非対面」で分類する方法として、「オンライン」と「オフライン」の2種類があります。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
| オンライン 販売チャネル | ・インターネットを活用して商品やサービスを提供 ・多くの人に大量の商品を販売できる | ECサイト、マーケットプレイス、SNS販売、サブスクリプションサービス、 ライブコマース、アプリ販売 |
| オフライン 販売チャネル | ・実店舗や対面販売を通じて商品を提供 ・直接顧客と接することで、ブランドの信頼性を高められる | 実店舗販売、卸売販売、イベント販売、訪問販売、直営店・フランチャイズ |
| OMO戦略 | オンラインとオフラインの融合 | ・「ショールーミング」(オンラインで商品を検索、オフラインの店舗で試して購入) ・実店舗で購入した商品をオンラインで再注文 |
直販・卸売・オムニ・海外
販売チャネルの分類方法として、流通経路に着目した分類もあります。
主な販売チャネルは、以下のとおりです。
| 種 類 | 内容 | 具体例 |
| 直接販売 (直販) | 企業やメーカーが、仲介業者を介さずに顧客へ直接商品を販売 | ECサイト販売、店舗販売、 サブスクリプションサービス |
| 間接販売 (卸売) | 企業が卸売業者や流通業者を経由して商品を販売 | 小売店への卸売、飲食店やホテルへの供給、流通業者や代理店を活用した販売 |
| オムニチャネル戦略 | 複数の販売チャネルを統合し、顧客がどこからでも購入できる環境を構築 | ・実店舗とオンライン販売の連携 ・SNSやアプリを活用したマーケティング ・店頭受取りや宅配サービスの組合わせ |
【販売チャネル改革】卸売依存からの脱却が鍵

これまでの酒造メーカーのビジネスモデルは、飲食店への卸売が主軸でした。
しかし、現在のような市場環境の変化に対応するためには、多角的な販売戦略を採用し、複数の収益源を確保することが重要になります。
販売チャネルの多角化には、次のようなメリットがあります。
| メリット | 内 容 |
| リスクの分散 | ・卸売に依存しないことで、特定の取引先の経営状況に左右されるリスクを軽減できる ・飲食店の閉店や売上低迷の影響を受けにくくなり、より安定した経営が可能になる |
| 新規顧客の獲得 | ・従来の卸売だけではアプローチできなかった消費者と直接つながることができる ・特に若年層や海外市場など、新しいターゲットに販売する機会が増える |
| ブランド価値向上 | ・酒造メーカーが直接販売することで、ブランドの魅力をより強く消費者に伝えることが可能になる ・SNSやECサイトを活用して認知度を高めることで、固定ファンの獲得につながる |
販売チャネル改革とは、従来の卸売依存という販売チャネルを見直し、販売チャネルの多角化を目指していくことです。
酒造メーカーが取り組むべき販売チャネル多角化の戦略
酒造メーカーが取り組むべき販売チャネル多角化には、どのような戦略があるのでしょうか。
ここでは、具体的に酒造メーカーが取り組むべき販売チャネル多角化の戦略について解説します。
【酒造メーカーが取り組むべき販売チャネル多角化の戦略】
- ECサイトによる直販の強化
- サブスクリプションサービスの導入
- 体験型イベントの開催
- 海外市場への進出
- 飲食店との共同開発
ECサイトによる直販の強化
近年、酒造メーカーが自社ECサイトを開設し、オンライン販売を強化する動きが加速しています。
これにより、直接消費者へ販売できるため、中間業者のコストを削減し、利益率を向上させることができます。
また、SNSとの連携を強めることで、ブランドの認知度を高めることが可能です。
InstagramやX(旧Twitter)などを活用し、酒造りの裏側や飲み方の提案などを発信することで、消費者とのコミュニケーションを活性化させることができます。
サブスクリプションサービスの導入
「毎月異なる日本酒をお届けする」などのサブスクリプションモデルは、安定した収益を確保する手段として注目されています。
季節限定酒のセットや特別醸造酒の定期配送を実施することで、消費者に新たな価値を提供でき、長期的な関係性を築くことが可能になります。
体験型イベントの開催
酒蔵ツアーや試飲イベントを企画することで、消費者が実際に酒造メーカーの現場を訪れ、製造過程を体験できる場を提供することができます。
これにより、ブランドに対する愛着が強まり、リピーターの獲得につながります。
海外市場への進出
日本酒の人気は国内にとどまらず、海外市場でも高まっています。
特にアメリカやヨーロッパでは、日本食ブームの影響で日本酒の需要が拡大しており、現地の飲食店との提携や海外向けECサイトを運営することで、新たな販路を開拓するチャンスが広がります。
飲食店との共同開発
酒造メーカーと飲食店が協力して、新たな商品を共同開発するという取り組みも有効です。
たとえば、特定の料理に合う日本酒を共同開発し、限定メニューとして提供することで、消費者の関心を引きつけ、売上向上につなげることができます。
販売チャネルの多角化までのステップ

販売チャネルの多角化を成功させるには、計画的なステップを踏むことが重要です。
以下の手順を参考にすると、スムーズに多角化を進めることができます。
【販売チャネルの多角化までのステップ】
- 現状分析と課題の把握
- ターゲットと戦略の設定
- チャネルの選定と導入準備
- マーケティングと集客戦略
- 運用と改善の継続
ステップ1:現状分析と課題の把握
まずは、現在の販売チャネルの状況を分析し、課題を明確にします。
ポイントや手順は、以下のとおりです。
- 既存の販売チャネル(卸売・直販・EC・店舗など)の売上構成を確認
- 主要顧客層の購買傾向や市場動向を調査
- 競合他社の販売チャネルと比較し、改善点を探る
- コスト面やリスクを評価し、多角化の必要性を明確化
ステップ2:ターゲットと戦略の設定
どの販売チャネルを拡充するかを決めるために、ターゲット層を明確にします。
検討する内容は、以下のとおりです。
- 新規顧客獲得を狙うのか、既存顧客の拡充を目指すのか
- オンライン販売を強化するか、オフラインの流通先を広げるか
- ブランドイメージと合う販売チャネルはどれか
- サブスクリプションや体験型販売など、新しい収益モデルの導入可能性を検討
ステップ3:チャネルの選定と導入準備
具体的にどの販売チャネルを活用するかを決め、導入の準備を行います。
具体的な行動内容は、以下のとおりです。
- ECサイトでの販売を強化する場合、サイト構築や運営体制の整備
- 直接販売を拡充するなら、物流や配送の仕組みを見直し
- 飲食店とのコラボやイベント販売を行う場合、パートナー企業と交渉
- 海外市場を狙うなら、代理店との契約や越境ECの準備
ステップ4:マーケティングと集客戦略
新しい販売チャネルを開拓する際には、適切なマーケティング戦略が不可欠です。
具体的な活動内容は、以下のとおりとなります。
- SNSやデジタル広告を活用して認知度を向上
- 期間限定キャンペーンや割引を実施し、初回顧客を獲得
- 体験型イベントを開催し、ブランドの魅力を伝える
- 口コミやレビューを活用し、信頼感を高める
ステップ5:運用と改善の継続
新しい販売チャネルを導入後、定期的に運用状況を確認し、改善を続けます。
以下のように、PDCAサイクルを回していきましょう。
- 売上データを分析し、効果的なチャネルを強化
- 顧客のフィードバックを収集し、商品やサービスを改善
- 市場の動向を把握し、必要に応じて販売戦略を見直し
- 新しいチャネルが軌道に乗れば、次の多角化ステップを検討
販売チャネルの多角化は、一度きりの施策ではなく、継続的な改善が重要です。
市場環境を見極めながら、柔軟に対応していくことで、より安定した経営を実現できます。
まとめ:今こそ販売チャネル改革を進めるとき

ここまで、酒業界が直面する課題とその解決策について、「販売チャネル改革」をテーマに考察してきました。
酒業界が厳しい状況にある今、酒造メーカーが生き残るためには、販売チャネルの多角化が欠かせません。
卸売中心のビジネスモデルから脱却し、EC販売の強化、サブスクリプションサービスの導入、体験型イベントの開催、海外市場進出、飲食店との共同開発など、さまざまな方法を組み合わせて市場の変化に対応することが必要です。
この変化をただ受け入れるのではなく、むしろ新たなチャンスと捉え、積極的に販路拡大を進めていくことが、酒造メーカーにとっての未来への鍵となります。
今こそ、一歩踏み出し、販売戦略を変革するときではないでしょうか。
アンカーマンでは、販売チャネルの多角化など販売チャネル改革をはじめとした酒蔵、酒販店ごとに最適な売れる仕組みを、クライアントごとの事情を丁寧にヒアリングしながら、一緒に作っていくスタイルのマーケティングサポートを提供しています。
酒類業界事情に詳しいマーケターにより、事業者さまごとの販売戦略立案をサポート。
「うちの蔵や店独自の売れる仕組みを作りたい!」
「将来まで続くサステナブル経営を行うには、いま何をすべきか?」
「1人でも多くの人に、うちのお酒を飲んでもらうには?」
など、酒類のマーケティングでわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にアンカーマンまでご連絡ください。
酒蔵で働きたい方向け:酒蔵エージェントはこちら!
酒蔵ツーリズム インタビューはこちらから!
お酒メーカーに役立つ制度一覧はこちらから!
酒税法改定、事業再構築補助金など事業継続・事業拡大に関わる
大切な制度について詳しく解説している記事一覧はこちらから!
お役立ち資料はこちらから!
設備導入事例集やアフターコロナの今取るべき戦略、働き方チェックシートまで
知りたいことが一式揃うお役立ち資料一覧はこちらから!
補助金診断はこちらから!
おすすめの補助金がすぐに分かる補助金診断を試してみませんか?
1分で完了する補助金診断はバナーをクリック!
補助金申請無料モニター募集中!
株式会社アンカーマンで補助金申請サポートをまだ受けたことがない方を対象に、
補助金申請無料モニターを不定期で募集しています!
応募にご興味をお持ちの方は、下記をチェック!
無料相談はこちらから!