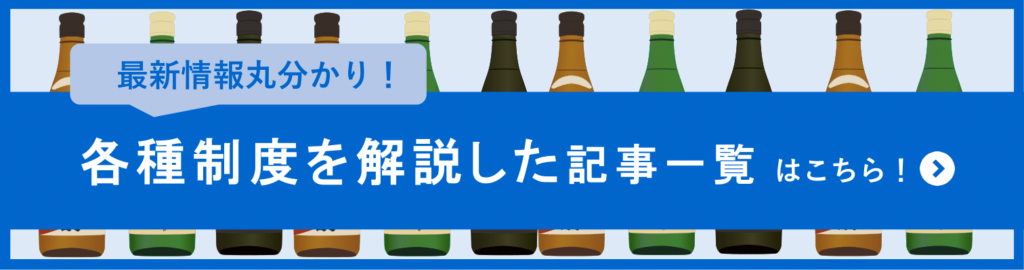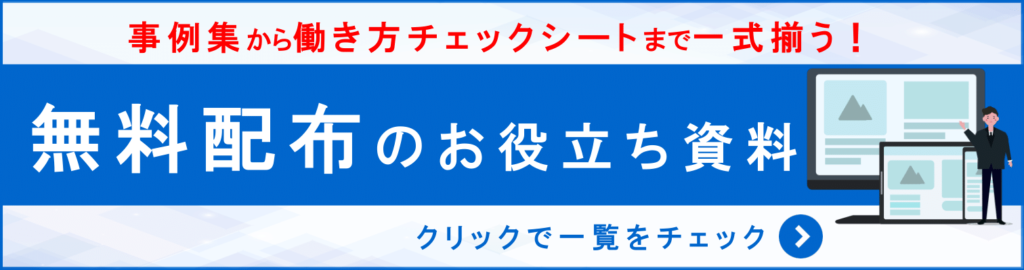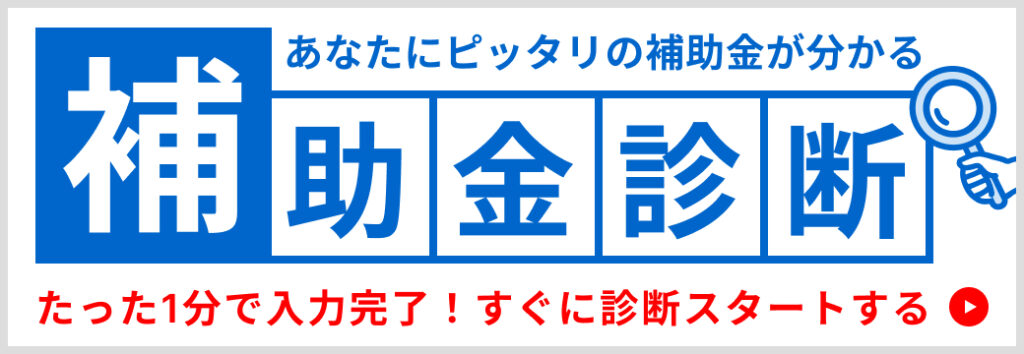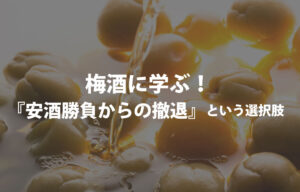酒蔵のM&Aが増えている理由とは?売却と買収によるメリット・デメリットを解説
※2023年8月21日更新
事業を100年以上続ける老舗も多い酒蔵に、近年、M&Aの波が押し寄せています。
「酒蔵のM&A」というキーワードを聞いたことはあっても、詳しく理解している蔵元さんは少ないのではないでしょうか。
今回は、酒蔵のM&Aに関して、なぜ今、酒蔵のM&Aが増えているのか、売却と買収によるメリットやデメリットを解説するとともに、酒蔵のM&Aの手続きや流れ、必要な費用、M&A以外で譲渡する方法やM&A事例なども併せてご紹介していきましょう。
- 1. 酒蔵のM&Aが増えている酒造業界の課題
- 1.1. 酒蔵のM&Aってどんなもの?
- 1.2. 酒蔵がM&Aされるのはどんなとき?
- 1.3. 酒造業界の課題から見る酒蔵のM&Aが増えている理由
- 2. 酒蔵のM&Aが進むことによる今後の酒造業界
- 2.1. 中小酒蔵でも戦える
- 2.2. 酒蔵の経営戦略が多様化する
- 2.3. 若手経営者・他業種からの参入が増える
- 2.4. 日本酒の消費者層が広がる
- 3. 【売却側】酒蔵のM&Aによるメリット
- 3.1. 廃業を回避して蔵やブランドを残せる
- 3.2. 対価(創業者利益)が得られる
- 3.3. 従業員の生活を守れる
- 3.4. 肩の荷を降ろせる
- 3.5. 担保や個人保証が外せる
- 4. 【売却側】酒蔵のM&Aによるデメリット
- 4.1. 蔵が第三者の手にわたってしまう
- 4.2. M&Aできなければ「廃業」となる
- 5. 【買収側】酒蔵のM&Aによるメリット
- 5.1. 酒造業免許を取得できる
- 5.2. 醸造設備や人材を引き継げる
- 5.3. 蔵のブランドやのれんを引き継げる
- 5.4. 酒造業に新規参入できる
- 5.5. 自身の本業とのシナジー効果が期待できる
- 5.6. 経営の多角化が図れる
- 6. 【買収側】酒蔵のM&Aによるデメリット
- 6.1. 従業員や取引先などから反発される可能性がある
- 6.2. 思ったとおりの利益や効果が見込めない場合がある
- 6.3. 簿外債務や偶発債務のリスクがある
- 7. 酒蔵のM&Aの手続きや流れ
- 7.1. 酒蔵の事業承継の形態の決定
- 7.2. M&Aのパートナー探し
- 7.3. M&A相手とのマッチング
- 7.4. 条件交渉・契約
- 7.5. デューデリジェンス
- 7.6. 最終条件交渉・正式契約
- 7.7. クロージング
- 7.8. PMI
- 8. 酒蔵のM&Aで必要な費用
- 8.1. アドバイザリー費用
- 8.2. 税金
- 9. 酒蔵をM&A以外で譲渡する方法
- 9.1. 事業承継
- 9.2. 廃業
- 10. 酒蔵のM&A事例
- 10.1. 酒造業免許取得のためのM&A
- 10.2. 本業とのシナジー効果を期待する異業種企業の買収事例
- 11. まとめ
酒蔵のM&Aが増えている酒造業界の課題
酒蔵のM&Aが増えている理由を探っていくために、酒造業界を取り巻く課題について見ていきましょう。
ここでは、酒蔵のM&Aとはどのようなものか、酒蔵のM&Aが増えている背景には酒造業界のどのような課題があるのかなどを解説します。
酒蔵のM&Aってどんなもの?
「酒蔵のM&A」とは、簡単に言えば、酒蔵を売ったり、買ったりすることです。
「酒蔵の事業の売買」と言い換えてもいいでしょう。
専門的に言えば、M&Aをする手法はさまざまで、会社法による合併や会社分割、株式譲渡・事業譲渡による買収などがあり、資本提携や業務提携を含むこともあります。
「酒蔵のM&A」は、酒蔵の事業承継の1つの形態ですが、特徴的なのは原則として第三者とのやり取りになるということを押さえておきましょう。
酒蔵がM&Aされるのはどんなとき?
酒蔵をM&Aで第三者に売却するのは、経営者が社内承継やM&Aを模索した結果、最終的に廃業を避けるためになされることが多いようです。
他方、なぜ酒蔵をM&Aで買収するのかという「買収側の動機」にも目を向けて見ると、「酒造業免許の取得が目的」だったり、「本業とのシナジー効果を期待」したりといったさまざまな動機が見受けられます。
このように酒蔵がM&Aされるのは、売り手と買い手双方の思惑が一致して、マッチングしたときです。
酒造業界の課題から見る酒蔵のM&Aが増えている理由
酒蔵がM&Aされるのは、売り手と買い手双方の事情がマッチングしたときですが、ではなぜ今、酒蔵のM&Aが増えているのでしょうか。
それは、まさに売り手となる酒蔵の経営者側にも、買い手となる企業側にも酒蔵をM&Aする課題があるからです。
売り手となる酒蔵の経営者側から見た酒造業界の課題としては、後継者問題や人材不足など酒造業の担い手が減っていることや、日本酒の国内消費の低迷や若年層の酒離れなど、時代の変化につれて日本酒を取り巻く環境も変わってきたことから、昔ながらの酒造りのやり方では生き残れないことなどが挙げられます。
買収側企業から見れば、世界的にも日本酒の魅力が注目され、消費者が海外にも見込めるため、新規参入するには魅力的な市場と言えるでしょう。
このように売り手側、買い手側双方から見た「酒造業界の課題」が、酒蔵のM&Aの増加に影響を与えていることは間違いないようです。
※「酒蔵の事業再生に向けての補助金の有効活用」は以下の関連記事を参照してください。
酒造業(酒蔵)の廃業回避や経営立て直しに向けてできることは?補助金を活用方法や活用事例を解説
酒蔵のM&Aが進むことによる今後の酒造業界
酒蔵のM&Aが進むことによって、今後の酒造業界がどのようになっていくのかは押さえておきたいところです。
ここでは、酒蔵のM&Aが進むことによる今後の酒造業界についての展望を掘り下げていきましょう。
中小酒蔵でも戦える
酒造業界においては、どうしても薄利多売で勝負できる大手酒蔵のマーケティング戦略が有利となり、日本酒全体の国内消費量が減ってパイの取り合いになれば、どうしても中小酒蔵の経営が厳しくなっていました。
結果として、酒蔵のM&Aは中小酒蔵に多い傾向が見てとれます。しかし、中小酒蔵におけるM&Aが進み、新規参入者がマーケティング戦略などを工夫することにより、中小酒蔵でも戦えるといった傾向が見受けられます。
このように、酒蔵のM&Aが進むことによって、酒造業界全体におけるマーケティング戦略の工夫などといった現象が広がることで、中小酒蔵でも戦える業界構図が生み出されることが期待できるでしょう。
酒蔵の経営戦略が多様化する
酒蔵のM&Aが進むことによって、酒造業界における自然淘汰も進み、生き残るために、酒蔵の経営戦略が多様化するといった傾向が見てとれます。
EC販売の強化、直売所の創設、酒蔵ツーリズムなど経営の多角化を図ったり、若者にウケる新商品の開発や高付加価値商品をラインナップに加えたりといったさまざまな経営戦略の工夫がなされていくことでしょう。
若手経営者・他業種からの参入が増える
酒蔵のM&Aによって、若手経営者や他業種からの参入が増えるといった傾向も見てとれます。
これまで、酒造免許の新規取得規制等で酒造業への新規参入に壁があったものが、酒蔵のM&Aが増えてくることにより、チャレンジ精神旺盛な若手経営者や、事業シナジーを活かした他業種からの参入組が増えて、酒造業界全体が活気づくといったことが予想されるでしょう。
日本酒の消費者層が広がる
若手経営者や他業種からの参入組の増加、酒蔵の経営戦略の多様化、中小酒蔵でも戦えるといった業界地図の改変などにより、既存の消費者層をさらに広げて、若者や女性にもウケる日本酒の開発などが活発になっていくことが期待できます。
現時点においても、フルーティーでフレッシュな、アルコール度数の低いこれまでの日本酒とは違ったテイストのさまざまな日本酒が登場してきたり、海外の消費者に向けて、料理とのペアリングを意識した高付加価値商品が人気を博したりといった風潮です。
このように、酒蔵のM&Aが進むことによって、結果として日本酒の消費者層が広がれば、日本酒全体の消費量も上がり、さらなる日本酒業界発展につながっていくことも期待できます。
【売却側】酒蔵のM&Aによるメリット
酒蔵のM&Aにおける売却側のメリットは、以下のとおりです。
【酒蔵のM&Aにおける売却側のメリット】
- 廃業を回避して蔵やブランドを残せる
- 対価(創業者利益)が得られる
- 従業員の生活を守れる
- 肩の荷を降ろせる
- 担保や個人保証が外せる
以下、順に解説します。
廃業を回避して蔵やブランドを残せる
酒蔵のM&Aによって、売却側には、廃業を回避して蔵やブランドを残せるといったメリットがあります。
酒蔵には老舗が多く、代々受け継がれてきた蔵やブランドを次世代に承継したいといった希望を抱く経営者が少なくありません。
しかし、後継者問題などで自身の子供や孫、親族などに酒蔵を承継できないケースでは、蔵やブランドなどを失ってしまう廃業というリスクがあります。
そのようなケースでは、酒蔵のM&Aという第三者への承継を選択することにより、廃業を回避して蔵やブランドを残せるといったメリットを享受することが可能です。
対価(創業者利益)が得られる
酒蔵のM&Aで、酒蔵を売却することにより売却側は、M&Aの対価である売買代金を得ることができます。売却側が創業者の場合には、創業者利益が得られるでしょう。
一般的に、酒蔵のM&A代金は、営業のノウハウや取引先といった資産(のれん)も「のれん代」として含まれることが多いため、高額になることもあります。
M&Aの対価である売買代金を得られることは、酒蔵のM&Aのメリットの1つです。
従業員の生活を守れる
酒蔵の経営状態が芳しくなかったり、後継者問題で酒蔵が廃業になってしまったりすれば、蔵人など従業員を解雇しなければならなくなり、従業員が途方に暮れてしまう事態を招いてしまいます。
その点、酒蔵のM&Aを選択することによって、従業員の雇用契約は第三者に事業とともに引き継がれ、従業員の生活を守ることが可能です。
酒蔵のM&Aによって、廃業を回避することで従業員の生活を守れるということは、売り手である酒蔵の経営者にとっては大きなメリットの1つとなるでしょう。
肩の荷を降ろせる
酒蔵のM&Aのメリットの1つとして、肩の荷を降ろせるいったことも考えられます。
経営者というものは、経営や責任という重荷を常に背負っているものです。酒蔵のM&Aによって、経営を第三者に承継できることにより、重荷を降ろすことができ、M&A後は平穏な暮らしができといったメリットがあります。
担保や個人保証が外せる
一般的に、M&Aでは、金融機関からの借入れによる代表者の担保や個人保証が外せることが多いようです。
酒蔵のM&Aでも、金融機関が納得すれば、担保や個人保証を外せることもでき、酒蔵の経営者にとっては、個人としても大きなメリットとなるでしょう。
【売却側】酒蔵のM&Aによるデメリット
酒蔵のM&Aにおける売却側のデメリットは、以下のとおりです。
【酒蔵のM&Aにおける売却側のデメリット】
- 蔵が第三者の手にわたってしまう
- M&Aできなければ「廃業」となる
以下、順に解説します。
蔵が第三者の手にわたってしまう
酒蔵のM&Aにおける売却側のデメリットとして、覚悟しておかなければなならないのは、蔵が第三者の手にわたってしまうということです。
M&Aといのは、事業を第三者に売却することであり、M&Aを実行してしまえば、事業も資産も第三者の手にわたってしまいます。資産の1つである蔵も当然ながら、第三者に引き継がれますので、どんなに愛着があっても手放さなければなりません。
酒蔵のM&Aを決断するときには、そのこともきちんと理解して熟慮しましょう。
M&Aできなければ「廃業」となる
酒蔵のM&Aにおける売却側のデメリットの1つとして押さえておかなければならないのは、買い手が見つからなかったり、条件が折り合わなかったりして、M&Aできなければ「廃業」になってしまうリスクがあるということです。
酒蔵のM&Aを決断したとしても、必ずしもM&Aが成功するとは限りません。相手が見つからずマッチングできない、売却代金や従業員の引継ぎなどに関して条件が合わないといったことはよくあることです。
M&Aができなければ「廃業」となるというリスクをしっかりと把握して、酒蔵のM&Aに向かうことが大切でしょう。
【買収側】酒蔵のM&Aによるメリット
酒蔵のM&Aにおける買収側のメリットは、以下のとおりです。
【酒蔵のM&Aにおける買収側のメリット】
- 酒造業免許を取得できる
- 醸造設備や人材を引き継げる
- 蔵のブランドやのれんを引き継げる
- 酒造業に新規参入できる
- 自身の本業とのシナジー効果が期待できる
- 経営の多角化が図れる
以下、順に解説します。
酒造業免許を取得できる
酒蔵のM&Aにおける買収側のメリットの1つに、酒造業免許を取得できるということがあります。
酒造免許は工場(酒蔵)に紐づいているため、酒蔵ごとM&Aによって手に入れることができれば、酒造業免許自体も取得できるのです。
原則として、地酒の酒造免許の新規取得は認められていないことから、酒造免許が紐づいている工場(酒蔵)をM&Aによって取得し、新規に酒造りに参入するといった買い手も多く見受けられます。
醸造設備や人材を引き継げる
酒蔵を1から作ろうと思えば、蔵の敷地や建物といった不動産、各種醸造設備や杜氏や蔵人といった酒造りの人材を備えなければなりません。
酒造りの経験やノウハウを持った人材を集めることは容易ではないところ、酒蔵のM&Aによって醸造設備や人材を引き継げるといったことは、買収側にとっては大きなメリットの1つです。
蔵のブランドやのれんを引き継げる
酒蔵を作るだけでは、酒造業はうまくいきません。蔵のお得意様や重要取引先、おいしいお酒造りの経験やノウハウといった蔵のブランドやのれんがあってこその成功です。
この点、酒蔵のM&Aによって、蔵のブランドやのれんを引き継げるということは、買収側にとって、酒蔵のM&Aを行う大きなメリットです。
1から酒蔵を立ち上げ、ブランドやのれんを構築するまでの時間をM&Aによって獲得することができます。
酒造業に新規参入できる
酒蔵のM&Aによって、酒造業に新規参入できるということも、買収側にとってのメリットの1つです。
本来なら、酒造業に新規参入していくためには、酒蔵を立ち上げ、酒造免許を新規に取得し、取引先やお得意様との関係を構築していかなければなりません。
酒蔵のM&Aによって、既に酒造業に参入している酒蔵を取得することで、すんなりと酒造業に新規参入できることは、買収側にとって酒造業で自身のポジションを築いていくためには、欠かせないメリットです。
自身の本業とのシナジー効果が期待できる
買収を行う企業が、異業種だった場合には、自身の本業とのシナジー効果が期待できるというメリットも見逃せません。
たとえば、食品事業を行っている企業が、酒造業を買収することで、自身の本業とのシナジー効果を期待する買収を行うことなどの典型例があります。
経営の多角化が図れる
酒造業を行っていない企業が、酒蔵をM&Aすることによって、スケールメリットを求めて経営の多角化を図る目的も達成できます。
さらに、海外企業が日本に進出する足がかりとして、地域と密着して信用を築いている酒蔵を買収することで、日本に進出しやすくなるというメリットもあるでしょう。
【買収側】酒蔵のM&Aによるデメリット
酒蔵のM&Aにおける買収側のデメリットは、以下のとおりです。
【酒蔵のM&Aにおける買収側のデメリット】
- 従業員や取引先などから反発される可能性がある
- 思ったとおりの利益や効果が見込めない場合がある
- 簿外債務や偶発債務のリスクがある
以下、順に解説します。
従業員や取引先などから反発される可能性がある
酒蔵のM&Aにおける買収側のデメリットの1つとして、従業員や取引先などから反発を受ける可能性があります。
やはり、従業員や取引先などからすると、自分たちの知らない第三者が突然現れ、経営陣が変わるとなるとすぐには信用できないものです。
充分な時間をかけて人間関係を構築していけなければ、酒造業のキーマンである従業員や取引先などから反発を受けることとなり、M&A後の経営がうまくいかないリスクもあります。
思ったとおりの利益や効果が見込めない場合がある
酒蔵のM&Aにおける買収側のデメリットとして、思ったとおりの利益や効果が見込めない場合もあるので注意が必要です。
こんなはずではなかったと思わないためには、M&Aの手続きを行う際に、専門家に依頼して、デューデリジェンス(相手企業の各種調査)をしっかりと行うことで、酒蔵の中身をできる限り正確に把握することが大切になってきます。
簿外債務や偶発債務のリスクがある
一般的に、M&Aにおいて、簿外債務や偶発債務のリスクがあることは充分注意しておきましょう。
簿外債務とは、貸借対照表に計上されていない債務であり、偶発債務とは、一定の条件で、将来債務となる可能性がある債務のことです。
簿外債務や偶発債務に関しては、入念なデューデリジェンスを行っても、リスクをゼロにすることはできません。酒蔵のM&Aにおける買収側のデメリットの1つとして、簿外債務や偶発債務のリスクがあります。
酒蔵のM&Aにおいても同様に、これらの予期できない債務のリスクがあることは念頭に置いた上で、M&A契約において簿外債務や偶発債務が発生した場合の責任の所在について明確にしておくなどの対処をしておきましょう。
酒蔵のM&Aの手続きや流れ
酒蔵のM&Aの手続きや流れの全体像を把握しておくことで、ポイントを押さえてしっかりと準備でき、酒蔵のM&Aをスムーズに進めることが可能になります。
酒蔵のM&Aの流れは、以下のとおりです。
【酒蔵のM&Aの流れ】
- 酒蔵の事業承継の形態の決定⇒「酒蔵をM&Aで売りたい」「酒蔵をM&Aで買いたい」
- M&Aのパートナーを選んで相談して相手を探す:酒蔵のM&Aの場合、酒造業に詳しいパートナーを選ぶことが重要
- 相手とのマッチング:売り手と買い手
- 条件交渉・契約=M&A覚書や基本合意書締結
- デューデリジェンス(相手企業の各種調査):専門家に依頼
- 最終条件交渉・正式契約(M&A契約書)
- クロージング(M&A実行=決済・引渡し)
- PMI(Post Merger Integration)=経営統合の取組み
以下、順に解説します。
酒蔵の事業承継の形態の決定
酒蔵のM&Aの手続きの入り口は、酒蔵の事業承継の形態の決定から行います。「酒蔵をM&Aで売りたい」「酒蔵をM&Aで買いたい」ということの決定です。
もちろん、前提として、「酒蔵の事業を承継したい」という際に、親族内承継を行うのか、第三者にM&Aで売るのかということを模索するでしょう。
また、酒造業に参入したいということで、1から酒蔵を作るのか、既存の酒蔵にOEMなどで提携するのか、酒蔵をM&Aで買いたいのかなども検討するはずです。
結果として、酒蔵のM&Aを選択した場合に、以降の手続きに進むことになります。
M&Aのパートナー探し
酒蔵のM&Aの意思決定をしたら、はじめにM&Aのパートナー探しを行いましょう。
M&Aのパートナーとは、M&Aの手続きを代行してくれたり、将来の事業計画を踏まえて、M&A相手を探したり、相手との条件交渉を行ったりしてくれるM&Aの仲介・コンサルティングの専門家や専門会社です。
特に、酒蔵のM&Aは特殊なので、酒造業に詳しいパートナーを選ぶことが何より重要となってきます。
M&A相手とのマッチング
酒蔵のM&Aでもっとも重要なのが、M&A相手とのマッチングです。売り手でも買い手でも、自身に適したM&A相手とマッチングできるかどうかで、酒蔵のM&Aの政府が決定すると言っても過言ではありません。
M&A相手とのマッチングを行うために、M&Aパートナーに自身の希望をはっきりと伝え、相手を探してもらいます。
ただし、気をつけなければならないのは、業界で酒蔵のM&Aで売却しようとしているという噂がたてば、事業の継続に支障をきたすこともあるので、はじめのうちは会社名が出ないように「ノンネームシート」という形で、酒蔵の概要とM&Aの希望条件だけを表に出して相手探しをすることが多いです。
条件交渉・契約
M&A相手とのマッチングに成功したら、いよいよ条件交渉の段階に入っていきます。
M&Aの売買価格、従業員引継の有無、承継する事業や資産・負債、その他M&Aに関する諸々の条件を、M&Aパートナーを介して交渉していくのです。
ある程度の条件が合致した段階で、M&A合意の契約を締結します。この段階では、M&Aの本契約はなく、合意書の段階となります。
デューデリジェンス
M&A合意書の締結が済んだら、本契約を行うためのデューデリジェンスを行ないます。デューデリジェンスとは、相手企業に関して、弁護士や会計士・税理士などの専門家に依頼して、各種調査を行うことです。
一般的には、買い手側が売り手側の企業から法的書類や会計資料を提出してもらい、買い手側から派遣された専門家がデューデリジェンスすることになります。
時には、売り手側が買い手側に充分な資金力があるかどうかを確かめるために、資金証明書などの提出を求めることもあるようです。
通常、M&Aの本契約には、デューデリジェンスを前提とした「表明保証責任条項」が付され、デューデリジェンスで精査した書類に嘘・偽りがあった場合に責任を追求するという規定が設けられるので、売り手・買い手とも、デューデリジェンスを信頼して契約に入っていくことになります。
最終条件交渉・正式契約
デューデリジェンスが完了して、売り手買い手とも問題がなければ、最終価格交渉も含めた最終条件交渉を行い、合意すればM&Aの本契約を締結することになります。
M&Aの本契約には、売却価格のほか、クロージング日、事業譲渡や株式譲渡等のM&Aの手法、承継する事業や資産・負債、手付金や違約金などM&Aに関する諸々の条件や手続きなどが記載されることになるので、専門家に依頼し慎重に作成していきましょう。
クロージング
M&A手続きの最終段階として、クロージングがあります。クロージングとは、M&Aを実行する日、つまり、売買代金決済および引渡しの日ということです。
クロージングは、多額の売買代金が振り込まれるので、銀行などの金融機関で行われます。当事者に加えて、M&Aパートナーや弁護士や司法書士、会計士、税理士などの専門家も立ち会い、引き渡される重要書類と引き換えに、売買代金決済が行われます。
クロージング日に酒蔵のM&Aが完了することになり、クロージング日から買収側に酒蔵が移転することになるのです。
PMI
酒蔵のM&Aは、売り手にしても、買い手にしても成功するか否かはM&A実行後が重要となってきます。
まず、酒蔵のM&Aの売り手に関しては、M&A実行後に第三者に蔵を引き渡したとしても、思ったとおりに従業員の生活を守ってくれるかどうかはわかりません。M&A実行後、経営がうまくいかず、従業員が解雇されたり、酒蔵の廃業に陥ったりするケースも珍しくないからです。
また、酒蔵のM&Aの買い手に関しては、M&A実行後に従業員との折り合いが悪くなり、思っていたように酒蔵の経営ができないというケースもあります。こんなときは、PMI(Post Merger Integration)=経営統合の取組みに注力すべきです。
具体的には、M&A実行後の事業再生に際して、経営管理体制や人事・財務、組織や各種規程、従業員の意識や企業風土の見直しなどのソフト面とIT・業務システム、醸造設備の見直しなどのハード面に気を配りましょう。財務面では、補助金の活用などもおすすめです。
酒蔵のM&Aを成功させるためには、売り手、買い手どちらの立場でも、M&A実行後のことも熟慮して、M&A実行計画を立てるとよいでしょう。
酒蔵のM&Aで必要な費用
酒蔵のM&Aで必要な費用に関しても押さえておくことにしましょう。
ここでは、酒蔵のM&Aに必要な費用として、M&Aパートナーに支払うアドバイザリー費用や税金のことなどについて解説します。
アドバイザリー費用
酒蔵のM&Aに関する費用として、最初に考えておかなければならないのは、M&Aパートナーに支払うアドバイザリー費用です。アドバイザリー費用は、M&Aパートナーによっては、コンサルティングフィーや仲介手数料といった呼び方をされることもあります。
M&Aパートナーによって、アドバイザリー費用に決まりがあるわけではありませんが、相場としては以下のような形が多いでしょう。
【アドバイザリー費用の相場】
- リテイナーフィー(着手金)として、数十万円~数百万円
- リテイナーフィーに加えて、成功報酬として、M&A売買代金の数%~数十%
M&Aパートナーによっては、着手金や相談料はかからず、完全成功報酬としているところもあるようです。
また、中間金として、相手を紹介した時点やM&Aの合意書を締結した時点でアドバイザリー費用がかかることもあります。
売り手と買い手で報酬形態を分けているM&Aパートナー会社もあるようです。
どちらにしても、どのくらいのアドバイザリー費用がかかるのか、依頼する際にはしっかりと確認しておきましょう。
税金
酒蔵のM&Aを行う際には、各種税金についても押さえておくことをおすすめします。
まず、酒蔵のM&Aで酒蔵を売却した売り手に関しては、所得税・法人税などの税金がかかることもありますので、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
これらの税金は、M&Aの手法(株式譲渡・事業譲渡など)や売買価格などにより異なります。
さらに、買収側に関しては、酒税の引継や酒税申告のタイミングや税額なども確認しておくようにしましょう。
酒蔵をM&A以外で譲渡する方法
「酒蔵のM&A」とは、第三者に酒蔵の事業を譲渡することですが、酒蔵をM&A以外で譲渡する方法もあります。
ここでは、酒蔵をM&A以外で譲渡する方法としての「事業承継」や「廃業」などについて解説しましょう。
事業承継
酒蔵の事業承継は、代々家業を子や孫などの親族に受け継がせる「親族内承継」や社内の従業員に引き継ぐ「従業員承継」など『社内承継』が一般的です。
他方、「酒蔵のM&A」は、事業承継する相手が社外の第三者ということで「社外承継(第三者承継)」という特徴があります。
廃業
「酒蔵の廃業」とは、それまで継続してきた「酒造業」をやめること、事業をたたんでしまうことです。
酒蔵の経営者として、事業継続を図ることは一番の命題ではないでしょうか。そのために、早期の段階では、酒蔵の事業承継の選択肢として、親族内承継や従業員承継など「社内承継」の道を模索するはずです。
しかし、社内承継が後継者問題などで難しくなると、残された選択肢は、社外承継となる第三者承継「酒蔵のM&A」か「酒蔵の廃業」しかありません。
これまで代々受け継がれてきた「ブランド」「取引先」「信用」「醸造技術などのノウハウ」「従業員の生活」「醸造設備」などを失ってしまう「廃業」を回避するために、「酒蔵のM&A」を選択するケースが多いでしょう。
酒蔵をM&A以外で譲渡する方法としての「酒蔵の廃業」とは、廃業の前後で第三者が酒蔵を引き取ってくれることも時としてあることから、ここでご紹介させていただきました。
酒蔵のM&A事例
酒蔵のM&Aには、どんな事例があるのか気になるところだと思います。
ここでは、酒蔵のM&A事例の一部をご紹介していきましょう。
酒造業免許取得のためのM&A
酒造業免許取得のためのM&Aの事例も多く見られます。
現時点では、酒造りをしたくても、原則として、地酒の酒造免許の新規取得は認められていません。
酒造免許は工場に紐づいているため、新規に酒造りをしようと思えば、酒造の許認可や人材、設備を含めた酒蔵ごと購入するのが現実的なのです。
酒造業免許取得のためのM&Aのケースでは、酒造免許のない酒屋が、酒造業に参入するため酒蔵を買収したり、異業種や海外企業からの新規参入を図ったりなどといった事例も多く見られます。
本業とのシナジー効果を期待する異業種企業の買収事例
本業とのシナジー効果を期待する異業種企業の買収事例をご紹介しましょう。
食品事業会社Aは、日本産酒類が海外でも注目を集めていることに魅力を感じ、自身の製造販売している食品ともシナジー効果があると考え、酒蔵BをM&Aにより買収しました。
このように、異業種企業が、本業とのシナジー効果を期待して、酒蔵をM&Aで買収する事例は増えています。
さらに、買収後、オリジナルブランドを作ったり、スケールメリットを求めて経営の多角化を図ったり、地域と密着して信用を築いている酒蔵を買収することで、日本に進出しやすくなるという目的で海外企業が買収したりといったケースなども見受けられるようです。
まとめ
酒蔵のM&Aに関して、ご理解いただけたでしょうか。
蔵の後継者問題で悩み、M&Aによる売却を考えている人、酒造業への新規参入を目指してM&Aによる蔵の購入を考えている人、皆さんそれぞれのご事情があることでしょう。
それぞれの事情から、酒蔵のM&Aを実行しようとしている人にとっては、パートナー選びも重要です。
酒蔵のM&Aは特殊です。酒造業に詳しくないパートナーを選んでしまうと、説明ばかりに時間がかかり、意図している相手とのマッチングも難しくなってしまうでしょう。
アンカーマンなら、酒造業に特化しており、180蔵以上のサポート実績から、酒造業の経営に詳しく、酒蔵のM&Aに関するご相談にも対応できます。
酒蔵のM&Aに関する売りたい・買いたいのご相談
事業再生にかかる設備導入等のご相談
酒蔵のM&Aに関連した補助金のご提案
用品店のパートナー紹介
などなど…
アンカーマンは、あなたの蔵の縁の下の力持ちとなり、「醸のバトン」を引き継ぐお手伝いをいたします。
酒蔵のM&Aのご相談なら、お気軽に酒造業特化のアンカーマンにご連絡ください。
お酒メーカーに役立つ制度一覧はこちらから!
酒税法改定、事業再構築補助金など事業継続・事業拡大に関わる
大切な制度について詳しく解説している記事一覧はこちらから!
お役立ち資料はこちらから!
設備導入事例集やアフターコロナの今取るべき戦略、働き方チェックシートまで
知りたいことが一式揃うお役立ち資料一覧はこちらから!
補助金診断はこちらから!
おすすめの補助金がすぐに分かる補助金診断を試してみませんか?
1分で完了する補助金診断はバナーをクリック!
補助金申請無料モニター募集中!
株式会社アンカーマンで補助金申請サポートをまだ受けたことがない方を対象に、
補助金申請無料モニターを不定期で募集しています!
応募にご興味をお持ちの方は、下記をチェック!
無料相談はこちらから!
アンカーマンに無料相談をご希望の方は、以下の専用フォームに「酒蔵のM&Aの相談」とご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!