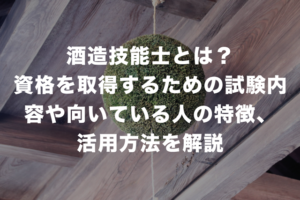日本酒検定とは?受験資格や申込みまでの流れ、必要な知識と関連資格との違いを解説

どのような職業に従事するにしても、取得しておいて困らないのが「資格」です。
酒造業や酒販業など酒類関連事業に従事する上で保有しておいたほうがよい「資格」もあります。
日本酒に関する資格として保有しておいたほうがいいのは、「日本酒検定」です。
ほかにも、酒類に関する資格としてよく知られている「唎酒師」などもありますが、「日本酒検定」とは特徴や内容が異なります。
今回は、日本酒検定とはどのような資格か、受験資格や申込みまでの流れ、必要な知識や勉強方法、資格取得のメリットや唎酒師などの関連資格との違いなどについて解説します。
日本酒に関する資格についてくわしく知りたい方は「日本酒の資格の種類とは?取得するメリットや効果的な勉強方法を解説」をご覧ください。
- 1. 日本酒検定とは
- 2. 日本酒検定の受験資格と申込み方法
- 2.1. 受験資格・年齢制限
- 2.2. 申込み方法
- 2.3. 受検料
- 3. 日本酒検定の出題範囲と難易度
- 3.1. 出題分野
- 3.2. 級別の難易度と合格基準
- 4. 日本酒検定で求められる知識レベル
- 4.1. 5級・4級で必要な知識レベル
- 4.2. 3級で必要な知識レベル
- 4.3. 2級で必要な知識レベル
- 4.4. 準1級・1級で必要な知識レベル
- 5. 日本酒検定の効果的な勉強方法
- 5.1. 公式テキストを中心とした学習
- 5.2. 問題集や過去問題での出題傾向の把握
- 5.3. 日本酒関連書籍での知識の幅を広げる
- 6. 日本酒検定に合格することのメリット
- 6.1. 接客やサービスの質が上がる
- 6.2. 日本酒関連イベントで活躍できる
- 7. 日本酒検定以外の日本酒関連資格と比較
- 7.1. 「唎酒師」の特徴と日本酒検定との違い
- 7.2. 「SAKE DIPLOMA」の特徴と日本酒検定との違い
- 7.3. 「酒匠」の特徴と日本酒検定との違い
- 8. 日本酒検定のまとめ
日本酒検定とは
「日本酒検定」とは、日本酒に関する知識と技術を評価するための民間の資格であり、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)が主催しています。
日本酒検定実施の目的は、一般消費者に向けて、日本酒の魅力を広く伝え、「日本酒をもっと楽しんでもらう」ことです。
「日本酒検定」には、5級・4級・3級・2級・準1級・1級といった段階があり、1級が最上位級となっています。
日本酒検定の受験資格と申込み方法
ここでは、日本酒検定について、受験資格、年齢制限、申込み方法、受検料などを解説します。
【日本酒検定の受験資格と申込み方法】
- 受験資格・年齢制限
- 申込み方法
- 受検料
受験資格・年齢制限
「日本酒検定を受検できるのは、20歳以上」という年齢制限があります。
また、3級~5級を受検する人は20歳以上という年齢制限だけですが、2級より上は、2級は3級合格者、準1級は2級合格者、1級は準1級合格者という受験資格が必要なので、3級合格以降は順番に取得していかなければなりません。
申込み方法
日本酒検定を受検するには、検定を所管する日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)に申し込みを行う必要があります。
はじめて受検する人は、5級・4級・3級のいずれの級からもチャレンジ可能です。
検定の形式は、5級・4級に関しては、インターネット上で24時間受検が可能な「ネット検定」で実施されます。
3級と2級に関しては、全国47都道府県のテストセンターで希望の日時・会場で受検できる「CBT試験」と、3月と9月の第2土曜日に指定された日時・会場で受験する「会場検定」の選択が可能です。
準1級と1級に関しては、「会場検定」のみでの検定となります。
受検料
日本酒検定を受検するためには、受検料が必要です。各級の受験料は以下のようになっています。
【日本酒検定の受検料一覧】
| 級 | 受検料(税込み) |
| 5級・4級ネット受検 | 1,100円 |
| 3級・2級CBT試験 | 7,100円 |
| 3級・2級・準1級・1級会場検定 | 6,000円 |
日本酒検定の出題範囲と難易度

日本酒検定を取得するには、どのような範囲の知識をどの程度学べばいいのでしょうか。
ここでは、日本酒検定の出題範囲や難易度について解説します。
【日本酒検定の出題範囲と難易度】
- 出題分野
- 級別の難易度と合格基準
出題分野
出題分野に関しては、「歴史・文化」「お酒の造り方」「モラル・マナー」「お酒の楽しみ方」「雑学」などです。
詳細は以下のとおりとなっています。
【日本酒検定の出題分野】
| 出題分野 | 詳細 |
| 歴史・文化 | 歴史、文化(飲酒文化や地域文化など) |
| お酒の造り方 | 原料(米・水・微生物)、製造方法 |
| モラル・マナー | 20歳未満飲酒の危険性や飲酒運転の撲滅など飲酒のモラル・マナー |
| お酒の楽しみ方 | 飲用温度、酒器、料理との相性、ラベルの読み方など |
| 雑学 | 生産量、消費量、海外事情、銘柄、醸造元など |
級別の難易度と合格基準
日本酒検定は、2010年より実施されており、現在までの合格者数は累計5,000人、2023年の受検者数は、年間1,500人超とのこと。
■参照:SSI「日本酒検定」
日本検定の合格率は開示されていませんので、級別の難易度は不明ですが、上位級になるほど、高い正答率が求められること、必要な知識レベルも上がること、1級合格者には日本酒名人が認定されることなどから、3級以上は難易度が上がります。
日本酒検定の級別の合格基準は、以下のとおりです。
【日本酒検定の級別の合格基準】
| 級別 | 合格基準 |
| 5級・4級・3級 | 正答率70%以上 |
| 2級 | 正答率75%以上 |
| 準1級 | 正答率80%以上 |
| 1級 | 正答率85%以上 |
合格基準に関しては、上位級になるほど、正答率の高さが要求されます。
日本酒検定で求められる知識レベル
日本酒検定に合格するには、どの程度の知識レベルが要求されるのでしょうか。
ここでは、日本酒検定で求められる知識レベルについて解説しましょう。
【日本酒検定で求められる知識レベル】
- 5級・4級で必要な知識レベル
- 3級で必要な知識レベル
- 2級で必要な知識レベル
- 準1級・1級で必要な知識レベル
5級・4級で必要な知識レベル
SSIが求めている5級・4級の合格者レベルの人とは、「日本酒の基礎知識・周辺知識を活用し、日本酒の魅力をご自身で楽しめる人」とされています。
ネット検定に合格すれば、合格者には「デジタル認定証」が即時に発行されること、不合格になっても受検期間内であれば3回まで再受験できることなどから、日本酒検定の入門レベルといっていいでしょう。
出題方式も、5級が正誤選択方式で30問、4級が二肢択一選択方式で30問となっており、日本酒を趣味で楽しんでいる人やある程度の日本酒に関する基礎知識・周辺知識の知識レベルがあれば合格することが可能です。
3級で必要な知識レベル
SSIが求めている3級の合格者レベルの人とは、「日本酒の基礎知識や周辺知識だけでなく、特徴や魅力を理解して第三者に伝えられる人」とされています。
3級からは四肢択一選択方式で50問の出題となり、必要とされる知識レベルも「第三者に伝えられる」程度となるため、趣味で楽しむ以上が要求されるでしょう。
2級で必要な知識レベル
SSIが求めている2級の合格者レベルの人とは、「日本酒の特徴や魅力を理解した上で、新たな楽しみ方を考案できる人」とされています。
2級では、「新たな楽しみ方を考案できる」程度の知識レベルが要求されるため、日本酒の歴史や文化、造り方といった知識に加えて、モラルやマナー、現状のお酒の楽しみ方などを前提とした深い知識が必要となるでしょう。
準1級・1級で必要な知識レベル
SSIが求めている準1級・1級の合格者レベルの人とは、「日本酒のあらゆることに精通し、後世へ適切に継承できる人」とされています。
特に1級に関しては、博識な合格者として、「日本酒名人」が認定されるほどの知識レベルが必要です。
「日本酒のあらゆることに精通」「後世へ適切に継承」などの知識レベルが要求されるということは、酒蔵の蔵元や杜氏レベルに近い知識レベルや考え方が必要になってくると考えておきましょう。
日本酒検定の効果的な勉強方法
どのように勉強すれば日本酒検定に合格できるでしょうか。
ここでは、日本酒検定の効果的な勉強方法について解説します。
【日本酒検定の効果的な勉強方法】
- 公式テキストを中心とした学習
- 問題集や過去問題での出題傾向の把握
- 日本酒関連書籍での知識の幅を広げる
公式テキストを中心とした学習
「日本酒検定」の試験は、マークシートによる択一選択方式です。日本酒に関する基礎知識を公式テキストを中心にインプットする学習が効果的でしょう。
「日本酒検定」には、SSIが推奨する公式テキストがあり、出題範囲を網羅するには、公式テキストに沿って学んでいくのが近道です。
SSIでは、日本酒検定5級~3級の公式テキストとして『酒仙人直伝よくわかる日本酒』、2級~1級の公式テキストとして『日本酒の基』を推奨しています。
問題集や過去問題での出題傾向の把握
「日本酒検定」に合格するための学習方法として、公式テキストによるインプットと併せて、問題集や過去問題などアウトプットをすることによって出題傾向を把握することも効果的でしょう。
SSIの「日本酒検定」公式HPでは、級別の検定問題例が掲載されていますので、参考にすることをおすすめします。
日本酒関連書籍での知識の幅を広げる
「日本酒検定」に合格するためには、日本酒関連書籍を読み、知識の幅を広げることも大切です。
日本酒に関する歴史や文化、酒造方法や雑学など、日本酒検定の出題分野ごとの日本酒関連書籍に触れて日本酒の見識を広げることも検定対策だけでなく、今後の酒類関連事業への就業にも役立つかもしれません。
日本酒検定に合格することのメリット
日本酒検定に合格し、資格を保有することによって得られるメリットにはどんなことがあるでしょうか。
ここでは、日本酒検定に合格することのメリットについて解説します。
【日本酒検定に合格することのメリット】
- 接客やサービスの質が上がる
- 日本酒関連イベントで活躍できる
接客やサービスの質が上がる
日本酒検定に合格することで、酒販事業における接客やサービスの質が上がるというメリットが考えられます。
たとえば、消費者が酒屋さんに行き、お酒に関する説明を受けたとき、胸のバッジを見ると、「日本酒検定2級」や「日本酒名人」などと書かれていれば、説得力が増すのではないでしょうか。
また、資格に裏付けされた豊富な日本酒に関する知識から、お客さまに適切な提案ができ、顧客満足度がアップすることが期待できます。
日本酒関連イベントで活躍できる
日本酒検定の資格を持っていれば、日本酒関連イベントで活躍できるといったメリットもあります。
たとえば、日本酒関連イベントで日本酒検定資格保有者としてセミナーの講師を務めたり、ブースで来場者にお酒に関する説明をしたりと引く手あまたでしょう。
また、学生のうちに日本酒検定に合格すれば、就職活動の面接や合同就職説明会などの就活イベントで採用担当者と話がはずむのではないでしょうか。
日本酒検定以外の日本酒関連資格と比較
日本酒関連資格には、日本酒検定以外にも、「唎酒師」「SAKE DIPLOMA」「酒匠」といった資格があります。
これらの資格は、どのような特徴があり、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、日本酒検定以外の日本酒関連資格と日本酒検定を比較して解説します。
【日本酒検定以外の日本酒関連資格と比較】
- 「唎酒師」の特徴と日本酒検定との違い
- 「SAKE DIPLOMA」の特徴と日本酒検定との違い
- 「酒匠」の特徴と日本酒検定との違い
「唎酒師」の特徴と日本酒検定との違い
「唎酒師」とは、SSが認定する「日本酒ソムリエ」の民間資格。「唎酒師」の資格を取得すれば、日本酒の提供・販売のプロフェッショナルとして、さまざまなビジネスシーンで活用できます。
「唎酒師」と「日本酒検定」との違いは、テイスティングがあるかどうかです。「唎酒師」の検定にはテイスティングがありますが、「日本酒検定」にはテイスティングがありません。
「SAKE DIPLOMA」の特徴と日本酒検定との違い
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」とは、一般社団法人日本ソムリエ協会(J.S.A.)が主催する日本酒・焼酎に関する民間の認定資格です。
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」の検定にもテイスティングがあり、お酒のソムリエを極める点が日本酒検定と違う点でしょう。
「酒匠」の特徴と日本酒検定との違い
「酒匠」は、「唎酒師」の上位資格として、SSIが認定する民間資格です。
高いテイスティング能力を活かして、日本酒・焼酎のセールスプロモーションを行うための資格である点が、日本酒検定とは異なる点でしょう。
日本酒検定のまとめ
ここまで、日本酒検定とはどのような資格か、受験資格や申込みまでの流れ、必要な知識や勉強方法、資格取得のメリットや唎酒師などの関連資格との違いなどをご紹介させていただきました。
酒造業や酒販業といった日本酒を含めた酒類関連業界で就業するのであれば、取得しておいたほうがいい資格が、「唎酒師」や「日本酒検定」です。
資格を保有しておけば、お客さまなど第三者に説明する上で、説得力が増すだけでなく、資格取得のための学習のプロセスで、酒類に関する豊富な知識を取得でき、日常の業務に生かすことができます。
今回の記事を参考にして、ぜひチャレンジしてみてください。
アンカーマンでは、酒類業界に就業を希望する人のための以下のような就活イベントなども企画しています。
また、アンカーマンでは、補助金サポート、経営サポートのほか、「唎酒師」や「日本酒検定」といった資格を活かして働きたい方をサポートしています!
新サービス「酒蔵エージェント」サイトをご欄ください!
無料相談はこちらから!
以下の専用フォームに「日本酒検定 相談希望」と必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!