【2025年版】日本酒の資格一覧!人気資格の選び方や費用・難易度とは?
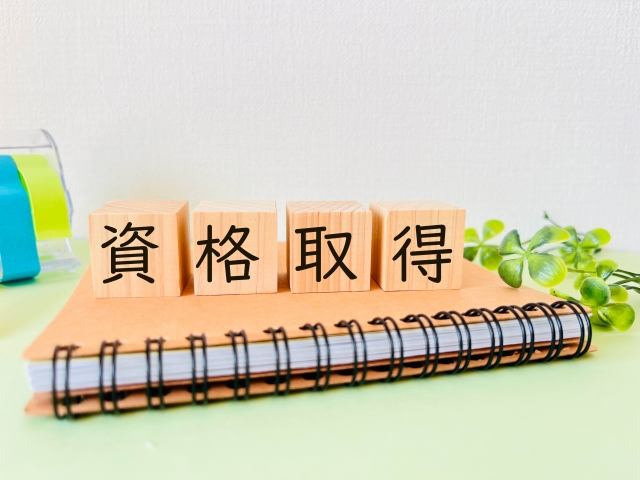
「日本酒の魅力に惹かれ、仕事として関わりたい」
そんな熱い想いを胸に抱いている方にとって、資格取得はキャリアの第一歩。
とはいえ、日本酒に関する資格といっても、さまざまな種類の資格があり、「どの資格を選べばいいの?」「費用や難易度は?」といった疑問も尽きないのではないでしょうか。
今回は、 酒類事業への就職・転職を志す方で、日本酒の資格取得に興味がある方に向けて、2025年最新の日本酒資格を網羅し、目標や働き方に合った資格選びの参考になる、各種日本酒資格の費用や難易度の比較、資格の選び方などを解説します。
【この記事でわかること】
- 2025年最新の日本酒資格の一覧および各資格の特徴や費用、難易度の比較
- 日本酒資格を選ぶための3つのポイント
- 資格取得の際の費用の抑え方、独学での勉強法、初心者向けの資格
- 仕事面やプライベート面での資格取得のメリット
- 1. おすすめの日本酒資格一覧|特徴や費用・難易度
- 1.1. 【日本酒検定】日本酒愛好家から飲食業界のプロまで幅広く対応
- 1.2. 【唎酒師(ききさけし)】日本酒の提供・販売で活用可能
- 1.3. 【日本酒ナビゲーター】日本酒入門編の資格
- 1.4. 【酒匠(さかしょう)】唎酒師の上位資格
- 1.5. 【SSI研究室 専属テイスター】日本酒テイスティングの専門家の資格
- 1.6. 【国際唎酒師】世界で通用する唎酒師の外国語版
- 1.7. 【日本酒学講師】唎酒師・焼酎唎酒師の上位資格
- 1.8. 【酒造技能士】唯一の酒造公的資格
- 1.9. 【SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)】仕事に生かせるきき酒資格
- 1.10. 【WSET SAKE】世界で通用する日本酒資格
- 2. 日本酒資格の選び方3つのポイント
- 2.1. ポイント1|仕事のためか趣味のためか目的で決める
- 2.2. ポイント2|かけられる費用と学習時間で絞り込む
- 2.3. ポイント3|テイスティング能力が必要かどうかで判断する
- 3. 【仕事】日本酒資格のキャリアや転職での生かし方
- 3.1. 転職や就職で有利に働く
- 3.2. 給料アップや昇進への影響
- 3.3. 独立や副業という選択肢
- 4. 【プライベート】日本酒の資格で暮らしや趣味がもっと豊かになる
- 4.1. 日々の晩酌がもっと楽しくなる
- 4.2. お店選びや旅行の楽しみが増える
- 4.3. 友人との会話や贈り物選びに役立つ
- 5. 日本酒の資格を取得するための効果的な勉強方法
- 5.1. 資格を取得する目的を決める
- 5.2. 必要な講座を受講する
- 5.3. インプットとアウトプットをバランスよく行う
- 5.4. ビジネスにどう生かすか考えよう
- 6. 日本酒の資格に関するよくある質問
- 6.1. 独学でも合格は可能ですか?
- 6.2. 費用を安く抑える方法はありますか?
- 6.3. 簡単な初心者向けの資格はどれですか?
- 7. 【まとめ】自分にぴったりの日本酒資格を見つけて一歩を踏み出そう
おすすめの日本酒資格一覧|特徴や費用・難易度
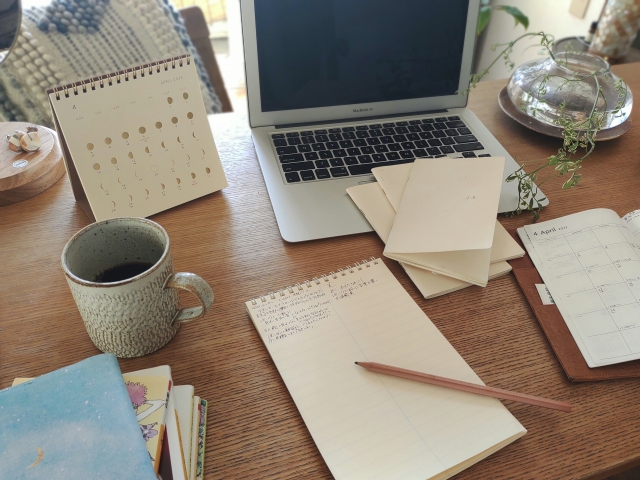
日本酒に関する資格には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、おすすめの日本酒に関する資格について、どのような資格があるのか、特徴や費用、難易度などをご紹介していきます。
以下、おすすめの日本酒資格の比較表です。
| 名称 | 費用(目安) | 難易度 | 特徴 |
| 日本酒検定 | 1,100〜7,100円 | ★☆☆☆☆ | 初心者向け。5級〜1級まであり、知識の幅を広げたい人におすすめ。 |
| 唎酒師 | 120,000〜160,000円(受講+試験+認定料)別途年会費15,900円 | ★★☆☆☆ | 日本酒のソムリエ的存在。飲食業界での信頼度が高く、合格率は約80%。 |
| 日本酒ナビゲーター | 数千円〜1万数千円(講座)+認定料2,640円 | ★☆☆☆☆ | 唎酒師の入門版。セミナー受講のみで取得可能。趣味や教養として人気。 |
| 酒匠 | 114,000円+認定料25,000円 | ★★★★☆ | 唎酒師の上位資格。テイスティングの専門家。認定者数は少なく希少性あり。 |
| SSI研究室専属テイスター | 非公開(酒匠取得後に選抜) | ★★★★★ | SSIから業務委託を受けるプロフェッショナル。極めて専門的な立場。 |
| 国際唎酒師 | 36,300~76,230円(受験+認定) | ★★☆☆☆ | 海外やインバウンド向けに日本酒を紹介するための資格。英語など多言語対応。 |
| 日本酒学講師 | 60,000~114,000円+認定料15,000~30,000円 | ★★★★☆ | セミナー開催やナビゲーター認定が可能。講師スキルも問われる。 |
| 酒造技能士 | 10,000円〜(都道府県により異なる) | ★★★★☆ | 国家資格。製造現場向けで、実務経験が必要。 |
| SAKE DIPLOMA | 32,900〜37,800円+認定料20,950円 | ★★★★☆ | 日本ソムリエ協会認定。合格率は約35%。ワイン的アプローチが特徴。 |
| WSET SAKE | 30,000〜100,000円(レベルにより異なる) | ★★★☆☆〜★★★★★ | 世界標準の酒教育。Level 1〜3まであり、英語中心。海外展開に強い。 |
【日本酒検定】日本酒愛好家から飲食業界のプロまで幅広く対応
日本酒検定は、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が主催する日本酒に関する知識と技術を評価するための資格試験です。この検定は、一般の方や日本酒業界の関係者が受けることができます。
日本酒検定には、5級・4級・3級・2級・準1級・1級といった段階があり、 はじめて受験する人は、5級・4級・3級からチャレンジすることができます。
試験の形式は、5級・4級がネット検定(インターネット上で24時間受験可能、不合格でも3回まで再受験可能)、3級・2級がCBT試験(全国47都道府県のテストセンターで希望の日時・会場で受験可能)または会場検定(3月と9月に指定の会場で受験)、準1級・1級が会場検定(3月と9月に指定の会場で受験)のみのいずれかであり、受験費用、出題形式・出題数、合格基準や受験資格などは、以下のとおりです。
| 各級試験 | 費用(税込) | 出題形式出題数 | 合格基準正答率 | 受験資格 |
| 5級ネット検定 | 各1,100円 | 正誤選択方式30問 | 70%以上 | 誰でも受験可能 |
| 4級ネット検定 | 2択選択方式30問 | |||
| 3級CBT試験 | 7,100円 | 4択選択方式50問 | ||
| 3級会場検定 | 6,000円 | |||
| 2級CBT試験 | 7,100円 | 75%以上 | 以下のいずれか ・3級合格者 ・唎酒師認定者 | |
| 2級会場検定 | 6,000円 | |||
| 準1級会場検定 | 6,000円 | 80%以上 | 以下のいずれか ・2級合格者 ・日本酒学講師 ・酒匠認定者 | |
| 1級会場検定 | 6,000円 | 85%以上 | 準1級合格者 |
なお、出題分野に関しては、歴史・文化(飲酒文化・地域文化など)、お酒の造り方(原料・製造方法)、モラル・マナー(20歳未満飲酒の危険性・飲酒運転の撲滅・飲酒のモラル・マナー)、お酒の楽しみ方(飲用温度・酒器・料理との相性・ラベルの読み方など)、
雑学(生産量・消費量・海外事情・銘柄・醸造元など)となっています。
※参照:日本酒検定(SSI)
【唎酒師(ききさけし)】日本酒の提供・販売で活用可能
唎酒師とは、「日本酒ソムリエ」として、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が認定する資格です。唎酒師の資格を取得することで、日本酒の提供・販売のプロフェッショナルとして、さまざまなビジネスシーンで活用できます。
酒販事業に生かせる点としては、お客様の好みに合わせて、日本酒を販売することができる点です。
注文された日本酒を軸に、提供温度・酒器・料理をコーディネートしたり、テイスティング能力を生かして、自社商品のラインナップを構成したり、日本酒情報をお伝えしたり、日本酒イベントに唎酒師として参加したりと資格を生かせる場面が多々あります。
唎酒師の資格取得者は国内外で5万人を超え、日本酒の提供・販売だけでなく、セミナー講師、コンサルタント、インフルエンサー、飲食店経営など、幅広く活躍しているようです。
唎酒師になるには、認定団体であるNPO法人日本酒サービス研究会(SSI)の「唎酒師養成講座」を受講して、課題または試験の結果が合格基準に達する必要があります。
「唎酒師養成講座(唎酒師取得プログラム)」のカリキュラムは、「飲食を提供・販売するプロとしての知識」「日本酒の基礎知識」「香味特性別分類(4タイプ)」「テイスティング」「セールスプロモーションの考案」の5つです。
唎酒師取得プログラムには、以下のようなコースがあり、自身のスタイルに合わせて選ぶことができます。
| 型 | コース名 | 受講受験料(税込) | 認定までの期間 | 内容 |
| 非通学/履修型 | eラーニングコース | 69,000円 | 最短3ヶ月 | オンラインで課題に取り組む |
| 通信コース | 79,000円 | 最短3ヶ月 | 手書きまたはデータで課題に取り組む | |
| 通信コース/短期集中プログラム | 99,000円 | 最短1ヶ月 | ||
| 通学/受験型 | 2日間集中コース | 79,500円 | 最短2日間 | 2日間で対策講座と試験を繰り返す |
| 1日通学コース/オンデマンド受講コース | 会場受験59,000円在宅受験77,000円 | 平均3ヶ月(最大6ヶ月) | 対策講座を受講(1日通学またはオンライン受講)後、試験を受ける |
資格取得費用としては受講受験料に加えて、別途資格認定諸費用59,900円(税込、内訳①認定料25,000円、②NPO法人日本酒サービス研究会入会金19,000円、③初年度年会費15,900円)が必要になります。
なお、2年目以降は年会費15,900円が資格維持費としてかかることに注意が必要です。
唎酒師の合格率は、資格取得コースによって差(約70〜92%)があり、平均すると84%となっています。
※参照:唎酒師(SSI)
【日本酒ナビゲーター】日本酒入門編の資格
日本酒ナビゲーターは、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が主催する日本酒の入門編の資格であり、唎酒師の弟分の位置づけの資格として、飲食業界から一般の方を対象として、日本酒の魅力をより深く、幅広く学ぶことができる資格です。
日本酒ナビゲーターになるためには、SSI公認の日本酒学講師が主催する「日本酒ナビゲーター認定セミナー」を受講する必要があります。日本酒ナビゲーターは、試験などはなく、約数時間の講座を受講するだけで資格取得が可能です。
「日本酒ナビゲーター認定セミナー」には、全国各地の会場で開催される「会場受講」と好きな時間、好きな場所で受講が可能な「オンデマンド受講」といった2つのスタイルがあり、自身の都合でどちらの受講も可能です。
日本酒ナビゲーターには、受講資格などはなく、誰でも受講することができ、受講手順としては、①セミナー動画の視聴→②認定問題にチャレンジ→③「日本酒ナビゲーター」に認定という流れになっています。
日本酒ナビゲーターを取得するための費用として、「会場受講」「オンデマンド受講」とも講師や会場ごとに料金が異なりますが、概ね数千円から1万数千円程度の受講料とSSIの認定登録料2,640円(税込)が必要です。
※参照:日本酒ナビゲーター(SSI)
【酒匠(さかしょう)】唎酒師の上位資格
酒匠は、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が認定しており、唎酒師の上位資格の位置づけです。高いテイスティング能力を生かして、日本酒・焼酎のセールスプロモーションを行うための資格となっています。
酒匠になるためのファーストステップは、味の要素の理解や、香りの表現例の習得などにより高度なテイスティング能力を身につけることを目的とした指定の講習会(2日間連続で約17時間)の受講です。
次のステップでは、以下のような指定の試験(第1〜4次)を受け、認定基準に達していることが必要になります。
| 出題形式 | 試験内容 | |
| 1次試験 | 【筆記】選択・記述式 | テイスティングの専門知識 |
| 2次試験 | 日本酒・焼酎の高度な専門知識 | |
| 3次試験 | 【テイスティングを伴う筆記】選択・記述式 | 日本酒・焼酎の原料、製法による香味特性の識別。劣化した日本酒・焼酎の識別 |
| 4次試験 | ・日本酒・焼酎の香味特性の視覚化および数値化(日本酒のポジショニングMAPおよび同軸グラフ作成、焼酎のポジショニングMAP作成) ・日本酒・焼酎の特性を伝えるべくテイスティングコメント作成 |
なお、酒匠の受講受験資格として、「唎酒師」および「焼酎唎酒師」の資格を有し、指定のSSI主催セミナー等への参加履歴などが求められています。
酒匠の資格取得費用は、講習会の受講費用および試験費用で114,000円(税込)、認定登録料は25,000円(税込)となっています。
なお、酒匠の合格率は、公式には公開されていませんが、SSI認定の資格の中でも上位資格であるため、受験者層が限られており、難易度が高いです。
ちなみに、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が認定する日本酒・焼酎関連の資格の位置づけは、以下のとおり。

※参照:酒匠(SSI)
【SSI研究室 専属テイスター】日本酒テイスティングの専門家の資格
「SSI研究室専属テイスター」とは、「酒匠」から選抜されて、SSI研究室に所属し、SSI研究室からテイスティングに関する業務を一部委嘱された日本酒のテイスティングの専門家です。
「酒匠」認定後、SSIが定めるプログラム「日本酒・焼酎テイスティングトレーニングセミナー」(SSI主催)に参加し、より専門性の高いトレーニングを積み、かつ選考会で、酒類全般の知識、高度なテイスティング能力のみならず、知識・経験を踏まえ、消費者視点に立った評価と消費者への提案力やもてなしの心、日本酒の提供・販売環境の向上に対する熱意や相応しい能力を有すると認められた者のみが「SSI研究室専属テイスター専属テイスター」を名乗れる非常にハードルの高い資格です。
卓越したテイスティング能力とその評価力により、日本酒、焼酎を取り扱うビジネス分野における酒類マネジメントのプロフェッショナルである「SSI研究室専属テイスター」は、2024年10月現在99名となっています。
なお、費用や難易度等は非公開となっています。
【国際唎酒師】世界で通用する唎酒師の外国語版
「国際唎酒師」とは、「Sommelier of Sake」(日本酒ソムリエ)=「日本酒の提供・販売のプロフェッショナル」として、海外における、また、日本国内での訪日外国人の方への「日本酒のセールスプロモーションにおける戦略・戦術の企画立案、実施」に資する能力を活かして、ツーリズムやメディアなどで、日本酒関連の情報をさまざまな場面で発信できる資格です。
「国際唎酒師」は、日本語での認定試験を前提とする「唎酒師(SSI認定)」の「外国語版」として、外国語で認定試験を実施する資格制度でSSIインターナショナルが主催しています。
「国際唎酒師」ができたことにより、海外の方が「外国語」で日本酒の提供・販売について学べる機会が増えたこと、日本国内でも、外国人の方への日本酒の提供・販売に資する資格としてビジネスシーンで活用する機会が増えました。
日本国内で日本語での活動を主とする方は「唎酒師」、海外や日本国内での外国人の方への外国語での活動を主とする方は「国際唎酒師」のような棲み分けができています。
「国際唎酒師」の資格を取得するためには、以下のように「【中級】日本酒ソムリエ(検定コース)」「【中級】日本酒ソムリエ(遠隔講座)」の2つのコースがあり、自身のスタイルに合わせて選べるようになっています。
| コース | 費用(税込) | 内容 |
| 【中級】日本酒ソムリエ(検定コース) | 公式テキスト付【英語版】 一般36,300円 SSI認定会員19,470円 公式テキスト付【中国語版】 一般39,050円 SSI認定会員22,550円 | ・自主学習して指定の時間・場所(東京・大阪・その他日本国内)で会場受験するコース ・言語は、以下のとおり【日本で受験】英語、中国語【提携校で受験】英語、中国語、韓国語、スペイン語 ・試験期限:申込日の翌月から1年以内 |
| 【中級】日本酒ソムリエ(遠隔講座) | 公式テキスト付【英語版】 一般73,480円 SSI認定会員38,060円 公式テキスト付【中国語版】 一般76,230円 SSI認定会員41,140円 | ・時間や場所を選ばず学べ、最短3カ月で資格取得が目指せるコース ・受講は英語、中国語 ・試験はなく、課題を提出し、合格基準を満たす必要あり |
「検定コース」の試験に関しては、以下のような内容になっています。
| 試験時間 | 12:30〜15:20 |
| 1次試験 | 【筆記】選択式(一部記述式) ・日本酒に関する専門知識 ・酒類をはじめ飲食全般における基礎知識 |
| 2次試験 | 【筆記】記述式(一部選択式) ・日本酒のサービス、セールスプロモーションに関する設問 (季節別、香味特性別分類(4タイプ)別の企画立案を含む) |
| 3次試験 | 【テイスティングを伴う筆記】記述式(一部選択式) ・日本酒のテイスティングを通じた品質の評価、個性の抽出(香味特性別分類含む) |
| 合格基準 | 各試験の正答率70%以上 |
国際唎酒師の合格率は公表されていませんが、唎酒師の資格に加えて、外国語能力と日本酒に関するより深い知識・スキルが求められるため、合格率は唎酒師よりも低くなる可能性があります。
【日本酒学講師】唎酒師・焼酎唎酒師の上位資格
「日本酒学講師」とは、NPO法人日本酒サービス研究会(SSI)が指定する3日間の講習を受け、試験に合格して「講師」として認定されると、國酒である日本酒と焼酎を正しく伝えることができる資格です。
日本酒学講師」は、「唎酒師」または「焼酎唎酒師」の上位資格として位置づけられ、「唎酒師」または「焼酎唎酒師」の方のみが受講受験可能です。
「日本酒学講師」には、日本酒ナビゲーター認定セミナーが主催できる「日本酒ナビゲーター認定講師」と、焼酎ナビゲーター認定セミナーが主催できる「焼酎ナビゲーター認定講師」とがあります。
「唎酒師」の資格保有者は「日本酒ナビゲーター」を、「焼酎唎酒師」の資格保有者は「焼酎ナビゲーター」を認定することができます。
「日本酒学講師」の受講受験資格は、以下すべての要件を満たすことが必要です。
- 「唎酒師」または「焼酎唎酒師」の資格を有すること
- 認定講師であること
- 講習会エクステンションプログラム「映像で学ぶ蔵元見学プログラム」の受講または指定のSSI主催セミナー等への参加履歴があること
「日本酒学講師」を取得するための費用は、以下のとおりです。
| プラン | 費用(税込) |
| 認定講師同時取得プラン | ・受講受験料:114,000円 ・認定料:30,000円 |
| 日本酒学講師(認定講師)+焼酎唎酒師 受講受験パック | ・受講受験料:114,000円+焼酎唎酒師受講受験料(コースにより異なる) ・認定料 ①日本酒学講師30,000円 ②焼酎唎酒師12,500円 |
| 日本酒学講師のみの取得の場合 | ・受講受験料:60,000円 ・認定料:15,000円 |
2025年7月現在、600名以上の日本酒学講師が認定され、日本酒関連の店舗での従業員教育、飲食店舗でのアイドルタイムに常連客向けのセミナー開催等でのマーケティング業務、各種媒体による「日本文化を広める」セミナーの実施など、国内外のさまざまなビジネスシーンで資格を生かして活躍しています。
※参照:日本酒学講師(SSI)
【酒造技能士】唯一の酒造公的資格
「酒造技能士」は、厚生労働省が所轄・主催する日本酒の製造に関する技能を認定する国家資格であり、お酒造りに関する資格では唯一の公的資格です。
酒造に関する学科及び実技試験を受験して、合格した者が取得できます。受験資格は20歳以上であることと、原則として実務経験が必要になります。
「酒造技能士」には、1級と2級とがあり、1級が上位資格です。実技試験では、白米の精米判定から、きき酒による判定まで、酒造の各工程を実践します。
蔵人や杜氏として働くために、必ずしも「酒造技能士」の資格が必須というわけではないのですが、日本酒製造の仕事を希望するのであれば、取得しておくべき資格でしょう。特に「酒造技能士」1級を保有していれば、どこの酒蔵でも歓迎されると思います。
試験は、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)が実施しています。
1級合格者は職業訓練指導員 (発酵科)試験の実技試験と学科試験の関連学科が免除、2級合格者は実技試験が免除です。
酒造技能士試験概要は、以下のとおりです。
| 受験資格 | 20歳以上かつ以下の実務経験 ・1級:7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験 ・2級:2年以上の実務経験 ※1級2級とも学歴により必要な実務経験年数が異なる |
| 試験内容 | 1級・2級とも同内容 【学科試験】 ・清酒製造法 ・微生物および酵素 ・化学一般 ・電気 ・関係法規 ・安全衛生 【実技試験】 ・清酒製造作業 |
| 試験頻度 | 年2回 |
| 願書受付 | 【1回目】4月上旬~中旬 【2回目】10月上旬~中旬 |
| 試験日程 | 【1回目】実技:6月上旬~9月中旬、学科:7月中旬~9月上旬 【2回目】実技:12月上旬~2月中旬、学科:1月下旬~2月上旬 |
| 合格発表日 | 【1回目】10月上旬【2回目】3月中旬 |
| 受験地 | 指定の試験場 |
| 受験料 | 学科試験:3,100円 実技試験:18,200円 ※都道府県によって異なる場合あり |
【SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)】仕事に生かせるきき酒資格
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」とは、一般社団法人日本ソムリエ協会(J.S.A.)が主催する日本酒・焼酎に関する認定資格です。
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」の試験は、20歳以上であれば誰でも受験可能です。
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」の資格取得までの流れは、以下のとおりです。
- 【申込・支払】一般社団法人日本ソムリエ協会(J.S.A.)のホームページにアクセス→募集要項の内容を確認→出願フォームに必要情報を入力→支払い→協会から「教本」と「会場予約ID・パスワード」の送信→一次試験日時・会場をインターネットから予約
- 【受験】(指定日時・会場)認定試験(一次)の受験→合格→認定試験(二次)の受験→合格
- 【認定登録の手続き】
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」の試験内容は、第一次試験が「CBT試験(コンピューターで解答)」、第二次試験が「テイスティング試験/論述試験」となっています。1次試験は、2回まで受験可能です。
「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」の資格取得費用は、以下のとおりです。なお、一次試験は2回受験でき、二次試験は一回のみ受験できます。
(※金額はすべて税込)
| 会員 | 一般 | |||||
| 一次試験から受験 | 1回受験 | 23,700円 | 32,900円 | |||
| 2回受験 | 28,600円 | 37,800円 | ||||
| 3月入会 | 4月入会 | 5月入会 | 6月入会 | 7月入会 | ||
| 同時入会 | 1回受験 | 41,200円 | 39,950円 | 38,700円 | 37,450円 | 36,200円 |
| 2回受験 | 46,100円 | 44,850円 | 43,600円 | 42,350円 | 41,100円 | |
| 【免除】二次試験から受験 | 7,300円 | 14,210円 | ||||
| 同時入会 | 3月入会 | 4月入会 | 5月入会 | 6月入会 | 7月入会 | |
| 24,800円 | 23,550円 | 22,300円 | 21,050円 | 19,800円 | ||
なお、合格後、別途認定登録料20,950円が必要となります。
【WSET SAKE】世界で通用する日本酒資格
「WSET SAKE」とは、世界最大のワイン教育機関であるWSET(Wine & Spirit Education Trust)が提供する日本酒の国際資格です。
WSET SAKEは、日本酒の基礎知識から応用までを、世界標準のメソッドで体系的に学ぶことができ、初心者から専門家まで、幅広いレベルの人が受講できます。
WSETの認定資格は、世界中で認められており、日本酒の知識を証明する資格としても有効です。
日本国内で資格を取得するためには、WSETが指定する講座の受講および試験の合格が必要であり、WSETロンドン校でのオンライン受講・受験や日本国内にある認定校での受講・受験が必要となります。
WSET SAKEは、Level 1・2・3と3段階に分かれており、目的や難易度、試験形式などは以下のとおりです。
| 項目 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| 対象者 | 初心者・愛好家 | ・基礎を学んだ人 ・業界関係者 | ・専門家志望 ・業界経験者 |
| 言語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 (提供校による) | 英語のみ |
| 講座時間 | 1日(7時間) | 3日間集中 | 約6か月(全9回) |
| 学習内容 | 日本酒の基礎・スタイル・用語 | 原料・製法・分類・ラベル表示 | 原料・製法・品質評価・論理的説明 |
| 試験形式 | 4択30問 | 4択50問 | 4択50問+記述3問+ブラインドテイスティング2種 |
| 合格基準 | 正答率70%以上 | 正答率70%以上 | 各セクション55%以上 |
| テイスティング試験 | なし | なし | あり(SAT方式) |
| 費用(目安) | 約30,000~40,000円 | 約70,000~80,000円 | 約80,000~100,000円 |
| 難易度 | 入門 | 中級 | 上級 |
酒類関連の仕事に活用するためには、WSET SAKE Level 2またはLevel3の取得が必要になってくるでしょう。
※参照:WSET・資格・酒
日本酒資格の選び方3つのポイント

数ある日本酒資格の中から、自分に合う資格をどのように選んだらよいのでしょうか。
ここでは、日本酒資格の選び方3つのポイントについて解説します。
【日本酒資格の選び方3つのポイント】
- ポイント1|仕事のためか趣味のためか目的で決める
- ポイント2|かけられる費用と学習時間で絞り込む
- ポイント3|テイスティング能力が必要かどうかで判断する
ポイント1|仕事のためか趣味のためか目的で決める
自分に合う資格を選ぶためには、「仕事のため」か「趣味のため」か、資格取得の目的を決めることがポイントの1つです。
資格を仕事に生かしたい場合には、「 唎酒師」「SAKE DIPLOMA」「酒匠」「日本酒学講師」などが考えられます。
他方、趣味として楽しみたい場合の資格は、「日本酒ナビゲーター」や「日本酒検定」などです。
ポイント2|かけられる費用と学習時間で絞り込む
日本酒資格を選ぶ際には、費用と学習時間の観点から絞り込むことで、自分に合った資格が見つけやすくなります。
以下、費用と学習時間の観点から日本酒資格を比較しましたので、参考にしてください。
| 資格名 | 費用の目安 | 学習時間の目安 |
| 日本酒ナビゲーター | 数千円〜1万数千円 | 1日(セミナー受講のみ) |
| 日本酒検定 | 1,100〜7,100円 | 5〜20時間程度 |
| 唎酒師 | 120,000〜160,000円 (受講+試験+認定料)別途年会費15,900円 | 20〜40時間程度 |
| SAKE DIPLOMA | 約32,900〜37,800円+認定料 | 50〜100時間以上 |
| 酒匠/日本酒学講師 | 約114,000円+認定料 | 18〜30時間+実技 |
たとえば、予算が限られている場合には、「日本酒ナビゲーター」や「日本酒検定3級」からスタートしたり、短期間で取得したい場合には、セミナー型の「日本酒ナビゲーター」や在宅受験可能な「検定」がおすすめです。
また、将来的に仕事に生かすための「唎酒師」や「SAKE DIPLOMA」など資格取得に時間を要する場合には、段階的に準備を考えなければなりません。
ポイント3|テイスティング能力が必要かどうかで判断する
日本酒資格の選択をする場合に、テイスティング能力の有無で判断するという方法もあります。
テイスティング能力を養うとすれば、相当な時間と費用をかけてテイスティングの実践が必要です。
テイスティング能力が求められる資格は、それなりに資格取得に労を要する資格ともいえます。
以下、テイスティングが必要な資格と不要な資格を整理しましたので、参考にしてください。
| テイスティング能力必要 | ・唎酒師 ・SAKE DIPLOMA ・酒匠 ・SSI研究室 専属テイスター |
| テイスティング能力不要 | ・日本酒ナビゲーター ・日本酒検定 ・日本酒学講師 |
【仕事】日本酒資格のキャリアや転職での生かし方
日本酒資格を取得する最大のメリットは、仕事で生かせるということです。
ここでは、日本酒の資格取得の仕事面でのメリットとして、日本酒資格のキャリアや転職での生かし方について解説します。
【日本酒資格の仕事面でのメリット】
- 転職や就職で有利に働く
- 給料アップや昇進への影響
- 独立や副業という選択肢
転職や就職で有利に働く
日本酒関連の資格は、酒類業界への就職・転職を目指す方にとって、知識の証明と熱意のアピールという両面で大きなメリットがあります。
たとえば、「酒造技能士」の資格を保有していれば、酒蔵や大手酒造メーカーへの転職や就職で有利に働くでしょう。
また、「唎酒師」や「SAKE DIPLOMA」は、業界内での認知度が高く、即戦力として評価されやすいです。
さらに、資格取得は「日本酒への関心」「学習意欲」「探求心」の証であることから、飲食業界や観光業、酒造メーカーなどでは、熱意と専門性を兼ね備えた人材として好印象を与えられます。
給料アップや昇進への影響
日本酒関連の資格取得メリットとして、給料アップや昇進に直結する可能性があり、実務的な武器になるといったことが挙げられます。
特に、酒類業界や飲食・観光業界では、資格があることで「専門性」「信頼性」「提案力」が評価されやすくなるからです。
たとえば、「唎酒師」や「SAKE DIPLOMA」などの資格は、専門知識を持つ人材として上位職への推薦材料になり、販売・接客・企画職では、資格保有者がリーダーや教育担当に抜擢されるケースもあります。
また、資格取得によって業務の幅が広がることで、給与アップの交渉材料になったり、「資格手当」が支給されたりすることもあるようです。
独立や副業という選択肢
日本酒関連の資格は、独立や副業の可能性を広げる強力なツールにもなります。
酒類業界への就業を目指している方にとって、資格を生かした柔軟な働き方は魅力的な選択肢です。
以下、副業・独立で生かせる日本酒資格の活用例となります。
| 資格名 | 活用シーン | 独立・副業の可能性 |
| 唎酒師 | 飲食店でのアドバイザー、 講座開催、イベント企画 | ◎(副業・講師・コンサルなど) |
| SAKE DIPLOMA | 海外向けセミナー、 インバウンド対応、執筆活動 | ◎(国際展開・専門家としての活動) |
| 酒匠/日本酒学講師 | 教育・研修・専門講座の運営 | ◎(講師業・スクール運営) |
| 日本酒検定/ナビゲーター | SNS発信、趣味講座、 地域イベント | ◯(趣味副業・地域活動) |
【プライベート】日本酒の資格で暮らしや趣味がもっと豊かになる

日本酒資格を取得することで、仕事だけでなくプライベート面でもメリットがあります。
ここでは、日本酒の資格取得のプライベート面でのメリットとして、暮らしや趣味がもっと豊かになるということについて解説しましょう。
【日本酒の資格取得のプライベート面でのメリット】
- 日々の晩酌がもっと楽しくなる
- お店選びや旅行の楽しみが増える
- 友人との会話や贈り物選びに役立つ
日々の晩酌がもっと楽しくなる
日本酒資格取得の隠れたメリットとして、「日々の晩酌がもっと楽しくなる」といったこともあります。
たとえば、精米歩合や酵母の種類、酒米の特徴など資格を通じて得た知識により、「このお酒はこういう味なんだ」と味の違いがわかるようになったり、「脂の乗った焼き魚には純米酒」「さっぱりした冷奴には吟醸酒」など、料理とのペアリングを楽しんだりといったことが増えるでしょう。
また、お酒を選ぶ際にも、 酒蔵や銘柄にくわしくなり、季節や気分に合わせて選べるようになり、日常の楽しみ方にも深みを与えてくれるはずです。
お店選びや旅行の楽しみが増える
日本酒資格のプライベート面でのメリットとして、日本酒に関する知識が増えることで、お店選びや旅行先での体験が格段に豊かになるといったことも挙げられます。
たとえば、銘柄や造りの特徴を理解していると、レビューやメニューから「ここは自分に合いそう!」と判断しやすくなり、自分好みの店を見つけやすくなるでしょう。
また、資格取得で知識が豊富になると、酒蔵巡りや地域ごとの酒文化を味わい、地元の人との交流が生まれるなど、旅行がぐっと楽しくなります。
友人との会話や贈り物選びに役立つ
日本酒資格を取得すると、知識があることで、友人との会話が弾み、贈り物選びにもセンスが光るようになります。
たとえば、友人との会話の中で、銘柄や造りの話題で盛り上がったり、季節や料理に合わせた提案ができたり、日本酒イベントや酒蔵巡りの話題が広がったりといったことが期待できるでしょう。
また、贈り物を選ぶ際にも、相手の好みに合わせた銘柄選びができたり、ラベルや造りの背景を語ることで、贈り物の価値をぐっと上げたり、季節限定や希少酒など、特別感のある選択ができたりといったメリットが考えられます。
日本酒の資格を取得するための効果的な勉強方法
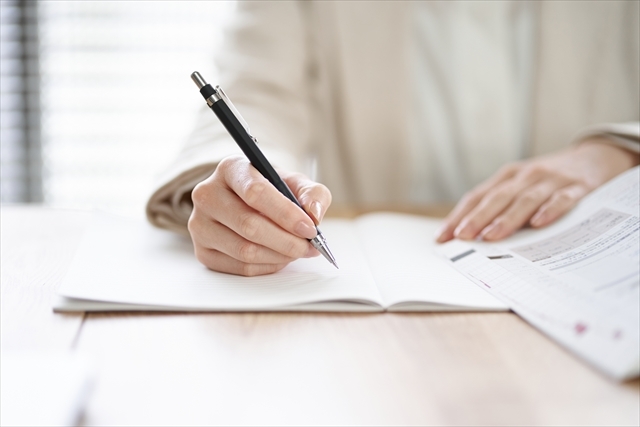
日本酒の資格を取得するためには、どのような勉強法が効果的なのでしょうか。
ここでは、日本酒の資格を取得するために効果的な勉強方法についてご紹介します。
【日本酒の資格を取得するための効果的な勉強方法】
- 資格を取得する目的を決める
- 必要な講座を受講する
- インプットとアウトプットをバランスよく行う
- ビジネスにどう生かすか考える
資格を取得する目的を決める
を取得すればいいのか、自身が資格を取得する目的を決めましょう。
目的を決める際には、「仕事のため」か「趣味のため」か、仕事に活用する場合には、「酒造業か」「酒販業か」「接客業か」など自身が目指す方向性を想定することが重要です。
資格を取得する目的を決定することにより、数ある日本酒関連資格の中から、自分に適した資格を選択することができるでしょう。
必要な講座を受講する
日本酒関連資格の中には、主催団体が指定する講座を受講しなければ受験資格が得られないなどの資格もあります。
資格を取得する目的が決まったら、取得したい資格を選び、資格の取得に関する要項を読み込み、講座受講が受験要件となっていれば、必要な講座を受講するようにしましょう。
講座受講が要件となっていない場合でも、効率的な学習のため講座を受講するか、費用を抑えるために独学で学習するかを選択する必要があります。
自分に合った方法を選びましょう。
インプットとアウトプットをバランスよく行う
試験がある資格に関しては、インプットとアウトプットをバランスよく行うことが重要になってきます。
受験する際には、インプットした知識をアウトプットしなければいけません。
たまに、受験勉強でインプットばかりしている人がいますが、インプットだけしてアウトプットに慣れていないと、うまくアウトプットできなくなってしまいます。
また、インプットとアウトプットをバランスよく繰り返すことで、知識の定着も早く確実になり、効率的に学習が進むでしょう。
資格の学習をする際には、インプットとアウトプットをバランスよく行い、インプットしているときはアウトプットのことを考えて、アウトプットでうまくいかなかったときは、再びインプットに戻るということを繰り返し行いましょう。
ビジネスにどう生かすか考えよう
日本酒関連業界への就業を希望する人で、仕事のために日本酒関連資格を取得したいと考えるのであれば、学習段階からビジネスにどう生かすかを常に考えておくことも重要です。
資格取得により、就職や転職での面接対応を有利に進めたり、資格取得で得られる知識が、自分が目指す仕事の場面で活用できたりと、ビジネスにどう生かすかを常に考えることで、自然と勉強にも力が入り、知識も定着していきます。
資格のビジネスへの活用方法を考えながら学習することが、日本酒の資格を取得するための効果的な勉強方法になるでしょう。
日本酒の資格に関するよくある質問

日本酒資格に興味のある人は、どのような疑問を抱くのでしょうか。
ここでは、日本酒の資格に関するよくある質問について解説します。
【日本酒の資格に関するよくある質問】
- 独学でも合格は可能ですか?
- 費用を安く抑える方法はありますか?
- 簡単な初心者向けの資格はどれですか?
独学でも合格は可能ですか?
資格によっては、主催団体が指定する講座の受講が必須である資格もありますが、それ以外の資格では、独学で合格することも可能です。
【独学で合格するためのポイントを押さえよう】
- 公式テキストを徹底的に読み込む
- 過去問で出題傾向を把握する
- まとめシートやキーワード表を作る
- テイスティングがある場合は実践練習を重ねる
- インプットとアウトプットをバランスよく行う
- ビジネスにどう生かすかを常に考えておく
費用を安く抑える方法はありますか?
費用を抑えて日本酒資格を取得する方法はいくつかあります。
【参考にするポイント】
- 自治体や団体の補助制度を活用する
- 通信講座やオンライン講座を選ぶ
- 早期申込割引やキャンペーンを利用する
- 複数資格をまとめて学べる講座を選ぶ
- 独学で挑戦する
たとえば、「SAKE DIPLOMA」と「唎酒師」など、関連資格をセットで学べるコースもあり、個別に受講するよりも割安になることがあります。
また、公式テキストや参考書を使って独学し、過去問や模擬試験を活用すれば、講座費用の節約も可能です。
資格取得費用に関しては、工夫次第で負担を軽減できるでしょう。
簡単な初心者向けの資格はどれですか?
初心者向けで比較的取り組みやすい日本酒の資格として、以下のものが挙げられます。
| 資格 | おすすめポイント |
| 日本酒検定 | ・初級者向けの資格 ・5級〜1級まであり、自分のレベルに合わせて選択可能 |
| 日本酒ナビゲーター | ・唎酒師の入門版 ・セミナー受講のみで取得可能 ・試験はなく、1日で完結する講座もある ・気軽にスタートしたい方にぴったり |
| 唎酒師 | 試験は選択式が中心で、通信講座も充実しているため、初学者でも取り組みやすい |
ちなみに、SAKE DIPLOMAに関しても、本資格自体はやや難易度が高めですが、初級者向けの対策講座が各スクールで用意されており、段階的に学べる仕組みがあります。
【まとめ】自分にぴったりの日本酒資格を見つけて一歩を踏み出そう
ここまで、2025年最新の日本酒資格に関して、各資格の特徴、費用や難易度の比較、資格の選び方のポイント、資格取得のメリット、効果的な学習法などを解説してきました。
日本酒の資格を生かして酒類業界で活躍したい人にとって、「どのような資格があるのか」「自分の目的に合った資格は何か」「どのようにアプローチすれば取得できるのか」などを把握することが重要です。
さらに、日本酒資格を生かして酒類業界で活躍するためには、自分に合った仕事を見つけることも重要であり、そのためには、アンカーマンの酒造業特化・人材紹介サポート「酒蔵エージェント」の活用をおすすめします。
アンカーマンの酒造業特化・人材紹介サポート「酒蔵エージェント」はこちら!
加えて、 酒蔵の現場の声が直接聞ける「飲める!酒蔵合同就職説明会2025(2025年夏開催予定)」に参加すれば、自分が働く現場のイメージをつかめるでしょう。
日本酒資格を生かして酒類業界で活躍したいと思っている方は、ぜひご参加ください!
アンカーマンが主催する酒造業特化の「飲める!酒蔵合同就職説明会2025」はこちら!
アンカーマンでは、酒売場作りに活用できる補助金のご相談や、マーケティング戦略に関するご相談など、酒販店さんへのサポートも行っていますので、お気軽にご連絡ください。
以下の専用フォームに「無料相談希望」とお書き添えの上、必要事項を記入して、「送信する」ボタンをクリック!
無料相談はこちらから!
以下の専用フォームに必要事項と相談内容をご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!



