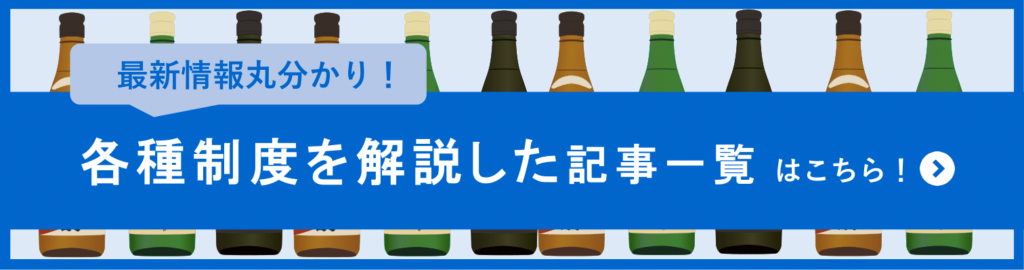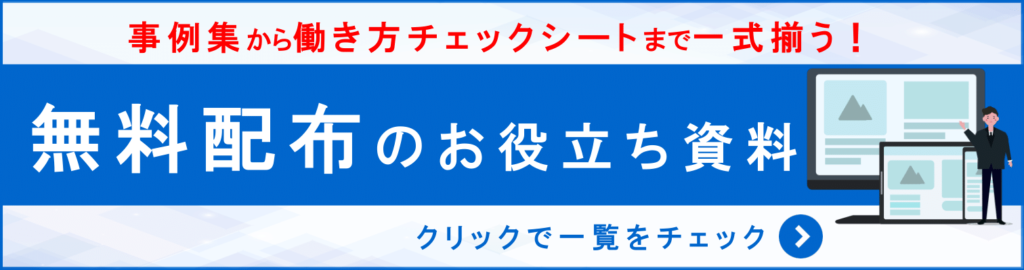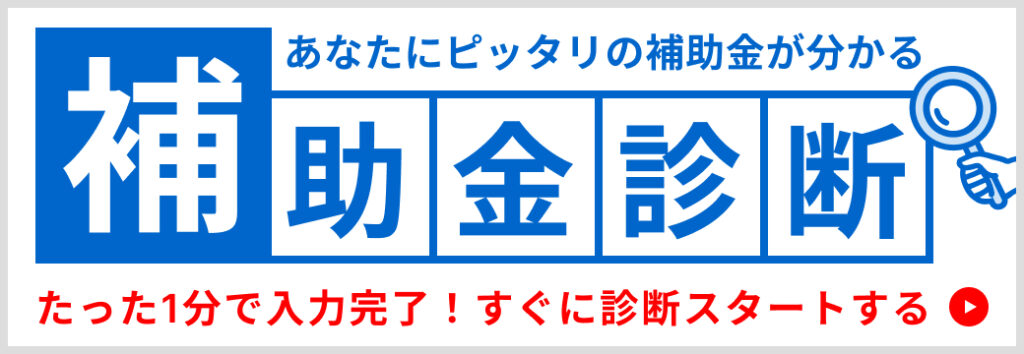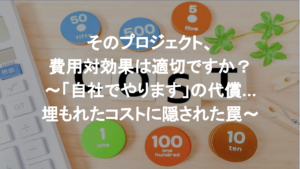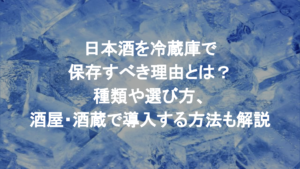令和5年酒税法等の改正とは?概要やスケジュール、新制度の内容や手続きについてわかりやすく解説
今般、令和5年度所得税法等の税制改正(令和5年3月31日公布、同年4月1日から施行)で、酒税法の特例措置が盛り込まれている租税特別措置法の改正(以下「酒税法等改正」といいます)も行われました。
「酒税法等に改正があるって聞いたけど、どう変わるの?」
「事業にどんな影響があるの?」
酒造業や酒販事業を営まれている方は、こんな心配をされているのではないでしょうか。
令和5年度酒税法等の改正は、酒税の納税義務者である酒類製造者の皆さまにとっては、酒造事業に影響するとても大きな改正です。
今回アンカーマンでは、令和5年度酒税法等改正につき、改正の概要やスケジュール、令和5年酒税法等の改正による新制度の内容について詳しく説明します。
令和5年の酒税法等の改正とは
まずはざっくり、令和5年にどんな酒税法等の改正が行われたのか概要、経緯について解説します。
※令和5年度酒税法等改正について、くわしく知りたい方はこちらを参照してください⇒国税庁「租税特別措置法第87条関係について」
酒税法等の改正の概要
令和5年の酒税法等改正は、中小規模の酒類製造者を保護するため、これまで長年行われてきた本来の税負担を軽減する措置を抜本的に見直す改正となっています。
具体的には、租税特別措置法(以下「租特」といいます)で規定されている「中小特例(租特87条)」や「地ビール特例(租特87条の4)」、震災特例法(以下「震特」といいます)で規定されている「被災酒類製造者に対する清酒等の特例(震特43条、実質5%の上乗せ措置)」などが適用期限をもって廃止される代わりに、新たな酒税の税率の特例措置が創設されることになりました。
令和5年の酒税法等改正では、これまで「対象品目(限定7品目)」ごとの前年の課税数量に応じた軽減割合の適用(ただし年間200㎘までの酒税を軽減)であった「旧制度」が、承認を受けた中小企業者が製造する全品目に軽減割合を適用するとした「令和5年酒税法等の改正による新制度」へと変更されたのです。
酒税の軽減税率の適用を受ける「対象」に着目すると、軽減対象が「品目」から「製造者」となり、令和5年酒税法等の改正による新制度下では、これまで軽減税率の対象でなかったウィスキー、リキュール、スピリッツなどの品目を製造する事業者も酒税の軽減措置の対象となり得ます。
酒税法等の改正の経緯
酒税法等の改正前の旧制度である「中小特例」「地ビール特例」「被災酒類製造者に対する清酒等の特例」などは、いずれも適用期限が令和5年3月31日でしたが、「制度創設時の目的は既に達成しており、制度の役目は終えている」など、制度をめぐるさまざまな指摘がありました。
これらの指摘を踏まえた上で、税制改正に向けた意見交換会(酒類業中央団体連絡協議会からの要望等)を経て、中小規模の酒類製造者の保護を継続するため、これまでとは体系が異なる新制度創設という改正がなされたのです。
令和5年酒税法等の改正のスケジュール
酒税法等の改正に関するスケジュールは、以下のとおりとなっています。
【酒税法等の改正に関するスケジュール】
| 令和5年4月~ | ~令和5年12月31日 | ~令和6年3月31日 | 令和6年4月~ |
| 準備期間(継続して現行制度適用可) | 令和5年酒税法等の改正による新制度適用のための税務署への申請 | 審査 ⇒承認or却下 | 令和5年酒税法等の改正による新制度開始(期間:5年間) |
酒税法等の改正前の制度は、令和5年3月31日の適用期限到来をもって廃止となり、令和5年4月からは本来は新制度が開始するのですが、適用猶予期間(準備期間)※が1年あるので、酒類事業者は何らの手続きを要せず、令和6年3月31日までは、引き続き現行制度の適用が可能です。
令和6年4月1日以降は、新制度が適用されることになるので、準備期間中(令和5年12月31日まで)に、新制度の適用を受けたい事業者は、所管税務署へ事業計画書を作成し申請する必要があります。
申請書提出後は、税務署によって審査が行われ、令和6年3月31日までに申請者に対して承認または却下の通知がなされる予定です。
令和5年酒税法等の改正による新制度の内容
令和5年の酒税法等の改正では、「酒類業の健全な発達に資する取組を行う中小事業者に対して支援を行う観点」から、新たに「承認酒類製造者(経営基盤の強化に資する施策を計画・実施する意欲的な酒類製造者として認められた者)に対する酒税の税率の特例措置」が創設されました。
令和5年酒税法等の改正による新制度で酒税の税率軽減の対象となる品目は、「中小企業者が製造する全品目」です。
ここでは、令和5年酒税法等の改正による新制度に関する「適用対象者」「軽減措置」「経過措置」の内容を解説します。
適用対象者
令和5年酒税法等の改正による新制度の適用対象者は、以下の2つの要件をいずれも満たす者です。
| 「中小企業者」企業規模・生産規模 | 酒類の製造免許を受けている者で前年度総課税移出数量が3,000㎘以下の者(資本金等3億円超かつ従業員300人超の法人・個人等、みなし大企業を除く) |
| 「承認酒類製造者」 | 経営基盤の強化のための「事業計画書」を提出し、特例の適用を受けるための承認を受けた酒類製造者 |
これらの要件に加え、さらに、酒税滞納処分等の欠格事由に該当していない者であることも必要となります。
軽減措置
承認酒類製造者には、製造者単位で最大1,400万円まで、以下の「酒税累計額」の区分に応じ、段階的に軽減割合を縮減する「酒税の軽減措置」が認められます。
| 酒税累計額 | 軽減割合 | 最大軽減額 |
| 5,000万円以下 | 20% | 1,000万円 |
| 5,000万円超~8,000万円以下 | 10% | 300万円 |
| 8,000万円超~1億円以下 | 5% | 100万円 |
ただし、いずれか1つの品目の前年度課税移出数量が以下の数量となった場合には、以下のの割合を本来の軽減割合に乗じた軽減割合となることも押さえておいてください。
| 前年度課税移出数量 | 本来の軽減割合に乗じる割合 |
| 400㎘超~1,000㎘以下 | 75% |
| 1,000㎘超~1,300㎘以下 | 50% |
| 1,300㎘超~ | 25% |
※参考【特定品目要件が適用される場合の軽減割合】
| 酒税累計額 | 本来の軽減割合 | 400㎘超~1,000㎘以下 | 1,000㎘超~1,300㎘以下 | 1,300㎘超~ |
| 5,000万円以下 | 20% | 20%×75%=15% | 20%×50%=10% | 20%×25%=5% |
| 5,000万円超~8,000万円以下 | 10% | 10%×75%=7.5% | 10%×50%=5% | 10%×25%=2.5% |
| 8,000万円超~1億円以下 | 5% | 5%×75%=3.75% | 5%×50%=2.5% | 5%×25%=1.25% |
経過措置
令和5年の酒税法等の改正には円滑に新制度へ移行するための「経過措置」があり、新制度の適用(令和6年4月1日以降)によって税負担が増えてしまう酒類製造者は、改正前の制度の軽減税率に次の割合を乗じた軽減税率を選択的に適用することが可能とされています。
| 令和5年度~令和8年度 | 100% |
| 令和9年度 | 90% |
| 令和10年度 | 80% |
たとえば、清酒製造の特例のケース(現行制度の軽減割合20%)では、以下のようになります。
| 中小特例 | 震災特例上乗せ | |
| 令和5年4月1日~令和9年3月31日 | 20%×100%=20% | 6.25%×100%=6.25% |
| 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 20%×90%=18% | 6.25%×90%=5.625% |
| 令和10年4月1日~令和11年3月31日 | 20%×80%=16% | 6.25%×80%=5% |
なお、旧制度を選択する場合でも、「旧特例選択届出書」を提出して、さらに、新制度と同様、「事業計画書」及び「実績報告書」も提出する必要があることにも注意が必要です。
このように、新特例制度の適用要件を判定した結果、要件を満たす酒類製造者については、新特例制度を選択するか旧特例を選択するかは、製造者自らの判断で選択することができ、要件を満たさない酒類製造者については、「旧特例選択届出書」を提出して、経過措置の適用を受けることになります。
令和6年4月1日以降の新制度下での酒類製造者の選択をまとめた表は以下のとおりです。
【新制度適用後の酒類製造者の選択】
| 要件満たす | 新制度選択 | 新制度を選択した後に、旧制度を選択することは不可 |
| 旧制度選択 | 【経過措置適用】 ・新制度移行後も必要な手続き(「旧特例選択届出書」等の提出<期限:令和6年3月31日>)をすれば旧制度の選択可 ⇒ただし、経過措置により、令和9年度以降は段階的に改正前の制度の軽減税率が順次減少されて適用 ・旧制度の選択後も、要件を満たしていれば、「旧特例選択不適用届出書」を提出(前年度3月31日期限)することで新制度への移行可 | |
| 要件満たさない | 旧制度選択 |
※参考【共同蔵置法人に関する経過措置】
製造免許を有していない「共同蔵置法人」からの課税移出について引き続き税額の軽減が受けられるための経過措置として、「施行日前1年以内において酒税法28条(未納税移出)の適用実績があること等」および「適用を受ける旨の届出書の提出(令和6年3月31日期限)」などの特例要件を満たせば、「構成員の有する製造免許と同一品目の製造免許を有する酒類製造者とみなす」または「承認申請をしてして、承認酒類製造者」となるかどちらかにより特例が適用できるとしています。
令和5年酒税法等の改正による新制度の適用を受けるための手続き
令和5年酒税法等の改正による新制度の適用を受けるためには、所管税務署に対して、以下の手続きが必要です。
【令和5年酒税法等の改正による新制度の適用を受けるために必要な手続き】
- 「承認酒類製造者」の承認:「新制度適用承認申請書」+「事業計画書」+「要件誓約書」の提出
- 毎月の納税申告書(「適用酒類=製造免許を受けた酒類と同一の品目」について、軽減措置を適用)
- 「実績報告書」の提出
以下、順に解説します。
「承認酒類製造者」の承認
新制度の適用を受けようとする酒類製造者は、所管の税務署長宛てに、「新制度適用承認申請書」のほか、「事業計画書」「要件誓約書」などの必要書類を提出して、「承認酒類製造者」の承認を受けなければなりません。
なお、承認申請書の様式等は、現在国税庁で作成中であり、2023年の夏以降に国税庁のホームページで公表予定となっており、申請の受付等が行えるようになるとのことです。
申請後、審査を経て、申請日の翌日から3ヶ月以内に「承認」または「却下」となります。
※参考①【承認申請手続きの却下要件】
- 申請書・事業計画書に「不備・不実の記載」がある場合
- 承認取消の日から1年を経過していない者
- 申請前2年以内に「酒税の滞納処分」を受けた者
- 酒造免許の取消要件に該当する者
- 公正取引基準違反に該当する者
※参考②【軽減の対象外となる酒類製造者】
- 企業規模要件(常時使用従業員数300人超、資本金3億円超、みなし大企業)
- 生産規模要件(前年度総課税移出数量3,000㎘超、令和5年4月1日以降の組織再編により完全支配関係が成立したグループ合算含む)
- 免許による制限(酒造免許がない、試験製造免許のみ)
- 欠格事由(申請前2年以内に酒税の滞納処分、免許取消事由、酒税組合法の命令違反)
事業計画書
事業計画書には、経営基盤の強化のために「取り組むべき具体的な内容」、その取組みについての「計画期間」「目標」「目標達成するための措置」「その他の事項」などを記載します。
事業計画書の作成は、令和5年中に行うことになりますが、事業計画書を作成するにあたって注意すべきポイントは、事業計画書が税務署長の審査においてどのような役割を果たすのかを把握しておくことです。
「承認酒類製造者」の承認を受けられるのは、事業計画書の記載から「酒類業の健全な発達に資する取組」を適正かつ確実に行うことができると認められた酒類製造者となります。
したがって、事業計画書に記載する「目標」に関しては、事業者それぞれの「事業規模」=「酒税軽減額」に基づいて、事後的に「酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができるかどうか」を客観的に評価できる「目標」を設定することが重要です。
具体的には、「経営基盤の強化に繋がるか」という観点から目標を作成すること、5年間の中期的な期間を想定した目標にすることなどがポイントとなってきます。
事業計画書に記載する「目標」に関しては、国税庁より以下のような目標例が公表されていますので参考にしてください。
【事業計画書の目標例】
- 商品単価を令和10年度末までに●%向上させる。具体的には、熟成による高付加価値化や既存商品のプレミアム化を実施する。
- 醸造技術の向上の観点から、国内外の複数の品評会に参加する。毎年1つ以上入賞することにより、商品のブランド化に結び付け売上を●%増やす。
- 外国語が堪能な人材を雇用し、輸出向けの商談会等に年1回参加。新しい販路を開拓し、輸出金額を令和5年度比で●%増やす。
- 製造工程の効率化により、生産コストを令和5年度比で●%引き下げ、従業員の賃金アップに回す。
- コロナ禍により販売数量が毎年●%程度減少している。事業継続の観点から、コロナ禍前の販売数量(●キロリットル)への回復を図るため、社長自ら取引先を年●回訪問し、取引基盤の強化・拡大を行う。
- 遊休蔵を酒蔵ツーリズムの拠点として整備し、蔵に訪れる観光客数の●%増を目指す。
- 教育機関と連携した職業体験を年1回実施し、若年層やUターン者の採用につなげ、地元の雇用を●人に増やす。
- 地元産原料の使用割合を●%に高める。軽減額相当の購入金額の増加を図り、地域貢献を行う。
- SDGsの観点や、将来にわたって仕込み水を安定確保するため、水源林の維持活動に参画する。具体的には、酒類の販売の際、1本当たり●円の寄付(総額◆円)を行い、企業のイメージアップを図る。
※参照:国税庁「酒税法等の改正のあらまし(令和5年度税制改正)」
要件誓約書
申請書の添付書類の1つである「要件誓約書」は、製造免許申請時に提出した「誓約書」と同様の書面であり、法令上の要件に適合しているかどうかをチェックリスト方式で定め、「欠格要件に該当しないこと」を誓約するための書面です。
欠格事由は、以下のとおりです。
- 軽減税率適用年度の前年度の末日以前2年内において酒税の滞納処分を受けた者
- 免許の取消事由に該当する製造者
- 酒税保全のための勧告又は命令や公正な取引の基準に関する命令等に違反した者
毎月の納税申告書
現行制度と同様、新制度下でも毎月の納税申告書の提出が必要ですが、申告の対象となるのは、酒税の軽減措置が受けられる「適用酒類(製造免許を受けた酒類と同一の品目)」ということになります。
実績報告書
酒類製造者は、毎年度、事業計画書に記載した「目標の達成状況などを記載した書面」=「実績報告書」を翌年度の5月31日までに税務署長に提出する必要があります。
期日までに実績報告書の提出をしないと、軽減措置が適用できなくなりますので注意しましょう。
なお、実績報告書作成の事務負担軽減のため、既存の「酒類業実態調査」に回答して提出することにより、実績報告書に必要な項目の一部を提出したものとして取り扱うという運用もありますので、ご活用ください。
なお、実績報告書の提出により、目標未達成だったとしても、必要な取組みを行ったということがわかれば目標未達成を理由に承認が取り消されることはありません。
令和5年酒税法等の改正関連で押さえておくべきポイント
ここからは、令和5年酒税法等の改正関連で、押えておくべきその他のポイントについて解説します。
輸出酒類販売場制度における即時徴収の対象者の追加
消費税の輸出物品販売場制度が見直されたことから、それに合わせて輸出酒類販売場制度の見直しも行われるというものです。
令和5年の見直しは、令和3年10月に免税販売手続が電子化され、国内で免税品の譲渡・横流しが疑われるケースが散見されるようになったことが改正の背景となっています。
本来、免税品は国内における譲渡・転売が禁止されており、仮に転売して、免税品購入者である非居住者(譲渡人)の帰国により酒税の即時徴収ができないケースでは、酒類の譲渡人が判明しているか否かにかかわらず、譲受人(ブローカー)にも酒税の即時徴収が可能とするように見直されました。
輸出酒類販売場制度の見直しは、令和5年5月1日以後に適用されますので、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、把握しておくようにしましょう。
酒税率の改正
令和5年10月1日より実施が予定されている「酒税率の改正」についても把握しておきましょう。
平成29年度税制改正により、3回に分けた税率改定が10年間かけて実施されることになっていますが、その2回目の改定が令和5年10月1日よりより実施されていることになっています。
令和5年10月1日より実施される酒税率の改定では、「清酒」に関しても、果実酒との区別がなくなり、「醸造酒類」として、1㎘当たり一律100,000円となりますので、要注意です。
【酒税率の改定表】
区分 | 税率(1㎘当たり) | ||||
| ~令和5年9月 | 令和5年10月~令和8年9月 | 令和8年10月~ | アルコール分1度あたりの加算額 | ||
| 発泡性酒類 | 200,000円 | 181,000円 | 155,000円 | ー | |
| 発泡酒 | 麦芽比率25~50%未満 | 167,125円 | 155,000円 | ||
| 麦芽比率25%未満 | 134,250円 | 134,250円 | |||
| 新ジャンル | ー | ||||
| その他の発泡性酒類 | 新ジャンル | 108,000円 | ー | ー | |
| ホップ等を原料としない酒類※ | 80,000円 | 80,000円 | 100,000円 | ||
| 醸造酒類 | 120,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ー | |
| 清酒 | 110,000円 | ー | ー | ||
| 果実酒 | 90,000円 | ー | ー | ||
| 蒸留酒類 | (アルコール分21度未満)200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | (アルコール分21度以上)10,000円 | |
| ウイスキー・ブランデー・スピリッツ | (アルコール分38度未満)370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | (アルコール分38度以上)10,000円 | |
混成酒類 | (アルコール分21度未満)200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | (アルコール分21度以上) | |
| 合成清酒 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ー | |
| みりん・雑酒(みりん類似) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ー | |
| 甘味果実酒・リキュール | (アルコール分13度未満)120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | (アルコール分13度以上) | |
| 粉末酒 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 | ー | |
※発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類の税率を適用できるアルコール分の制限は、令和8年10月1日から11度未満(現行:10度未満)となります。
また、酒税率改定(酒税率の引上げ・引下げ)の調整作業として、令和5年10月1日の午前0時時点で流通段階にある酒税法等の改正前の旧税率で課税済みの対象酒類に対して、新旧税率の差額を調整する手持品課税(戻し税)が必要となるほか、新税率の課税額と戻し税額を差し引きしたことによる追加納付、還付申告等も令和5年10月31日までに必要となるので押さえておきましょう。
酒販事業者におかれましては、令和5年10月1日午前0時時点の対象酒類の在庫数量のチェックが必要です。
まとめ
ここまで、令和5年度酒税法等改正につき、酒類事業者が押さえておくべきポイントをご紹介させていただきました。
現行制度の酒税に関しては、間接税と流通税であり、納税義務者は「酒類の製造者」もしくは「酒類を保税地域から引き取る者」となっていますが、実質的な税負担は最終消費者となっています。
酒造業・酒販事業の酒類事業者としては、商品であるお酒の価格に影響を及ぼす令和5年の酒税法等改正のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
アンカーマンでは、酒税を踏まえたブランディングやマーケティングサポート、補助金サポートを日本で唯一、酒類事業者向けに特化してご提供しています。
新制度の適用を受けたい事業者は、所管税務署へ事業計画書を作成し申請する必要があります。
アンカーマンでは、新制度適用の申請手続きや事業計画書作成の代行を行います。
本制度に関するご不明点やご要望等あれば、お気軽にアンカーマンまでご連絡ください。
また、新制度についての疑問・質問なども受け付けております。
アンカーマンでは新制度適用の申請手続きや事業計画書の作成について、オンラインセミナーを開催いたします!
開催日時 9月7日(木)16:00~17:00
お申し込みはこちらから
アンカーマン主催、酒税法改正セミナーのアーカイブ配信を行っています!
ご視聴はこちらから!
お酒メーカーに役立つ制度一覧はこちらから!
酒税法改定、事業再構築補助金など事業継続・事業拡大に関わる
大切な制度について詳しく解説している記事一覧はこちらから!
お役立ち資料はこちらから!
設備導入事例集やアフターコロナの今取るべき戦略、働き方チェックシートまで
知りたいことが一式揃うお役立ち資料一覧はこちらから!
補助金診断はこちらから!
おすすめの補助金がすぐに分かる補助金診断を試してみませんか?
1分で完了する補助金診断はバナーをクリック!
補助金申請無料モニター募集中!
株式会社アンカーマンで補助金申請サポートをまだ受けたことがない方を対象に、
補助金申請無料モニターを不定期で募集しています!
応募にご興味をお持ちの方は、下記をチェック!
無料相談はこちらから!
アンカーマンのサポートをご希望の方は、以下の専用フォームに「酒税法新制度について」とお書き添えの上、必要事項を記入して「送信する」ボタンをクリック!