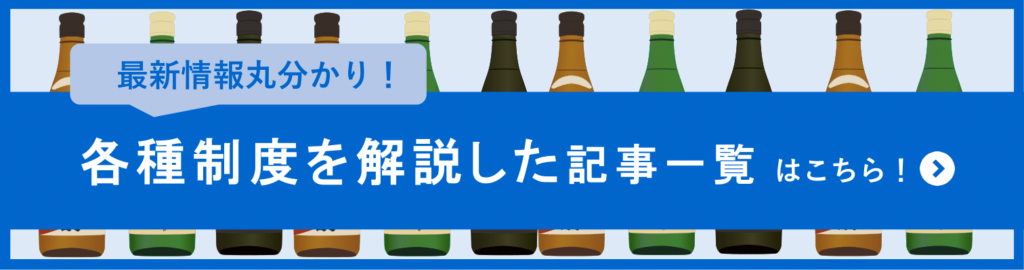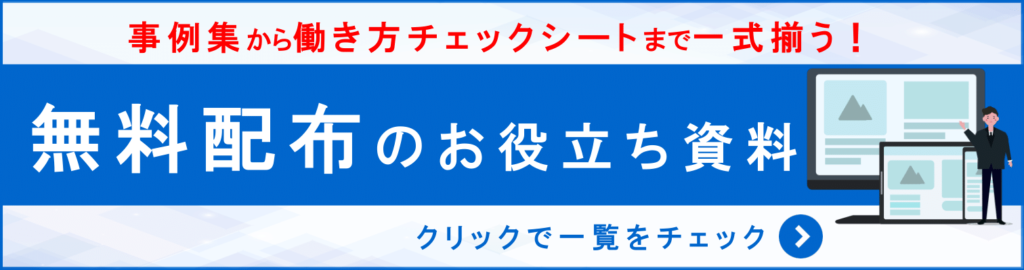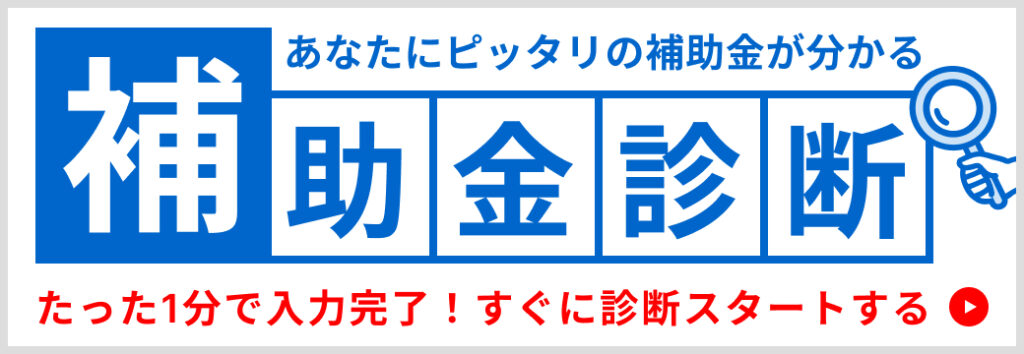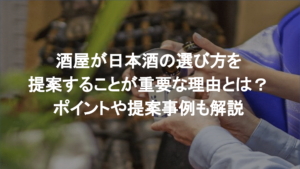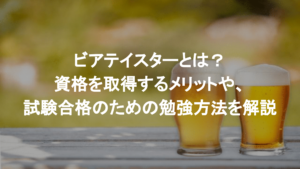客単価とは?業界別基準や計算方法、単価を上げるための方法を解説
売上をアップするためには、「客単価」をアップするのも1つの方法ということが言われています。
「客単価」というキーワードをよく聞きますが、一体どういうことなのか、どうすれば客単価アップが図れるのか、自信を持ってマーケティング戦略を構築して実行している酒類事業者さんはどれくらいいるのでしょうか。
今回は、売上アップや安定した経営に欠かせない「客単価」に関して、業界別基準、計算方法、客単価を上げるための方法やメリット、ツール、客単価が下がる原因や客単価を上げることができない外的要因などを解説します。
- 1. 客単価とは
- 2. 客単価の業界別基準
- 2.1. 小売業の客単価の基準
- 2.2. 飲食業の客単価の基準
- 2.3. 酒販業の客単価の基準
- 3. 客単価を上げるメリット
- 3.1. 売上・利益アップにつながる
- 3.2. ブランディングにつながる
- 3.3. 経営が見直せる
- 4. 客単価の計算方法
- 5. 客単価を上げる方法
- 5.1. 商品単価アップ
- 5.2. まとめ買い
- 5.3. アップセル
- 5.4. クロスセル
- 5.5. 松竹梅の価格設定
- 6. 客単価を上げるためのツールの活用
- 6.1. CRMの導入
- 6.2. AIの導入
- 6.3. チャットボットとの連携
- 7. 客単価が下がる原因
- 7.1. 購入金額の減少
- 7.2. 購入個数の減少
- 8. 客単価を上げることができない外的要因
- 8.1. 地域による消費傾向
- 8.2. 市場の価格競争
- 9. まとめ
客単価とは
そもそも「客単価」とは、「顧客単価」「平均客単価」とも呼ばれ、「顧客(消費者)1人が1回の買い物で購入する(支払う)金額(平均額)」のことです。
酒販事業をはじめ、どのような業界、どのようなビジネスにおいても、「売上=(平均)客単価×購入客数」ということになっています。
ここで、「購入客数」とは来店したお客さまの中で、実際に商品をお買い上げいただいたお客さまの数です。
売上目標(KGI)を達成するために、プロセスを管理するための定量的な評価指標(KPI)として、「(平均)客単価」や「購入客数」が考えられますが、もう少し細かくKPIを設定するなら、「購入客数=来店客数×購買率」ということになります。
つまり、売上が、「(平均)客単価」「来店客数」「購買率」などの要因で決定することから、売上をアップするには、「来店客数を増やす」「購買率をアップさせる」「(平均)客単価を上げる」などということが言われているのです。
なお、今回の記事では、「客単価=平均客単価」として、以降「客単価」で統一表記させていただきます。
客単価の業界別基準
酒造業や酒販事業を営む場合、「客単価」をどの程度に設定して、マーケティング戦略や事業計画を立てればいいのでしょうか。
「客単価の基準」が気になるところです。
ここでは、酒類業界を含めて、小売業や飲食業など客単価の業界別基準をご紹介します。
具体的には下記について説明します。
- 小売業の客単価の基準
- 飲食業の客単価の基準
- 酒販業の客単価の基準
それぞれについて見ていきましょう。
小売業の客単価の基準
中小企業庁の統計調査によれば、小売業の原価率は平均値で約70%程度となっています。もちろん人件費の関係で、規模が小さい企業のほうが原価率は低いです。
また、総務省が実施した「2022年(令和4年)個人企業経済調査/結果の概要」によれば、「卸売業・小売業」の年間営業利益率は約7%(「飲食料品小売業」は約5%)となっています。
小売業の客単価の目安は、以下のとおりです。
【小売業の客単価の目安】
| 小売業の種類 | 1店舗1日当たりの平均客単価 |
| コンビニエンスストア | 711.5円 |
| スーパーマーケット | 2,838円 |
| ホームセンター | 2,621円 |
ご参考にしてください。
飲食業の客単価の基準
飲食業の営業利益率は、5%〜8%程度です。仮に、月商1,000万円とすれば、50万円〜80万円程度の営業利益しか残りません。
売上目標を達成できたとしても、客単価が高すぎれば、「あのお店は、おいしいけれど、少し高いよね」ということで、中長期でみれば、リピート客が獲得できないということになってしまいます。
自身が考えるベストオーダーを組んで、ターゲットの客層の属性や曜日、立地に応じて客単価を考えることが大切です。
個人飲食店の場合、年間1,000万円〜2,000万円の売上が必要になると言われています。「1日の売上=客単価×席数×回転数」であることから、日曜日が定休日で席数30席のオフィス街にある飲食店の場合、以下のような売上シュミレーションとなります。
【飲食業の売上シュミレーション】
| 1日の売上 | 月間営業日数 | 月間売上 | |
| 平日昼 | 800円×30席×0.8回転 | 26日 | 499,200円 |
| 平日夜①月~木 | 3,000円×30席×0.6回転 | 18日 | 972,000円 |
| 平日夜②金・土 | 4,000円×30席×0.9回転 | 8日 | 864,000円 |
| 合計 | 2,335,200円 |
ご参考にしてください。
酒販業の客単価の基準
酒販業の客単価の目安を考える際には、業務用酒販店か家庭用一般消費者向け酒販店かによって分けて考える必要があります。
一般的に、以下のような線引きをして考えましょう。
【客単価の目安】
| 目標ライン | 業務用酒販店 | 家庭用一般消費者向け酒販店 | |
| 店頭売り | 宅配中心 | ||
| 手応えあり | 得意先10店舗×月額3万円 | 1,800円×600人/月 | 月1回注文100世帯×5,000円 |
| 堅調 | 得意先30店舗×月額3万3,000円 | 1,900円×800人/月 | 250世帯×月額1万円 |
| 安定経営 | 得意先40店舗×月額5万円 | 2,000円×1,000人/月 | 400世帯×月額12,000円以上 |
なお、国税庁の「酒類小売業者の概況(令和3年度分)」によれば、一般酒販店の経営状況の全国平均(1者平均)は、以下のようになっています。
【一般酒販店の経営状況】
| 損益項目 | 金額(千円) |
| 総売上高 | 125,598 |
| 売上総利益 | 35,542 |
| 営業利益 | 1,816 |
客単価を上げるメリット
客単価を上げると、以下のようなメリットがあります。
【客単価を上げるメリット】
- 売上・利益アップにつながる
- ブランディングにつながる
- 経営が見直せる
以下、順に解説します。
売上・利益アップにつながる
客単価を上げるメリットの1つは、何といっても、売上アップや利益アップにつながるということでしょう。
売上や利益は購入者数×客単価で決まります。購入者数が変わらないとしたら、客単価をアップすれば、必然的に売上や利益がアップすることになるのです。
具体例で見ていくと、1ヶ月で400人の購入者数がいるとして、客単価が3,000円、利益率が3割だとすると、売上は400(人)×3,000(円)=1,200,000(円)、利益が1,200,000(円)×0.3=360,000(円)となります。
客単価を4,000円に上げられれば、売上は400(人)×4,000(円)=1,600,000(円)、利益が1,600,000(円)×0.3=480,000(円)となるので、客単価を上げたことによって、売上・利益の向上が図られるのです。
ブランディングにつながる
客単価を上げるために、客単価を分析することでブランディングにつながるというメリットもあります。
売上だけを注視すると、購入商品・購入数の変化や商品ごとの単価を分析できません。客単価を分析して、商品単価が適正なのか、売れ筋の商品は何なのかなどを把握し、店の特徴を前面に出していくことで、ブランディングすることが可能になります。
経営が見直せる
客単価を上げるには、客単価を分析する必要があります。
客単価を分析することは、商品単価が適正か、店のブランディングに沿った経営ができているかということを分析する必要があるので、経営を見直せるというメリットがあるのです。
事業計画どおりに経営ができているのかを、客単価を上げるための客単価の分析で確認することができます。
客単価の計算方法
客単価の計算方法に関しては、以下のとおりです。
【客単価の計算方法】
- 客単価=売上高÷購買客数
客単価の計算は、数式で表してしまえば簡単なように思えますが、実際は「購買客数」をどのように算定するかが問題となってきます。
「購買客数」とは、実際に商品をお買い上げいただいたお客さまの数です。あくまで、お客様の数なので、算定する期間内に同じお客さまが複数回お買い上げいただいたケースでは、お客さまの数を1人として算定しなければならないことに注意が必要です。
このケースを具体例で説明しましょう。
たとえば、ある日、Aさんというお客さまが来店され、2,000円のお買い物をしたとします。翌日、Bさんというお客さまが来店され、3,000円をお買い上げになり、さらにその翌日、Aさんが再来店していただき、4,000円のお買い物をしていただいたとしましょう。
このケースにおける3日間の「客単価」の計算式は以下のようになります。
客単価(円)=(2,000+3,000+4,000)÷2
客単価(円)=4,500
購入頻度は3回、購買延べ客数は3人ですが、1人のお客さま(Aさん)が複数回購入されているので、「購買客数」は1人とカウントするため、「購買客数」は2人となるからです。
実際に、店頭で一定期間の「購買客数」をカウントするケースでは、お得意様であればスタッフが記憶しておくこともできるでしょうが、目視でカウントして、データを取得するのは容易なことではありません。
そのため2つの方法があります。1つは、「購買客数」=「来店客数」×「購買率」を活用して、来店客数だけカウントし、店ごとに「購買率」を決めておき、算出する方法です。
また、もう1つの方法は、お得意さま(リピート客)を店側で把握(販売管理システムなどに登録)しておき、自動的に購買客数を1人とカウントする方法もあります。
お店に合った方法で、「購買客数」のカウントルールを決めておきましょう。
ちなみに、「客単価」の別の算定方法として、理論上は、「客単価」=「平均購入商品数」×「平均商品単価」という方法でも「客単価」を算出することもできますが、これは、「購買客数」をカウントする以上に、大変ではないでしょうか。
何らかの方法で、KPIとして、「平均購入商品数」が求められるのであれば、可能かと思いますが、これもお店に合った方法を選択することをおすすめします。
客単価を上げる方法
客単価をアップさせるには、以下のような方法があります。
【客単価を上げる方法】
- 商品単価アップ
- まとめ買い
- アップセル
- クロスセル
- 松竹梅の価格設定
以下、順に解説します。
商品単価アップ
客単価を上げる方法の1つに、商品単価を見直して商品単価をアップするという方法があります。
ここで気をつけなければならないのは、むやみに値上げしただけでは、顧客離れを起こしてしまうといったリスクが発生するということです。
商品単価をアップする際には、お客さまに向けて、商品の付加価値を訴求するなど、お客さまに購入するメリットを感じてもらう工夫が必要になってきます。
たとえば、「これまで以上に原料にこだわり、高品質となりました!」「希少価値の地酒です!他ではなかなか手に入りません!」などのPOPを付けて、付加価値を演出しましょう。
まとめ買い
お客さまに「まとめ買い」を提案して、客単価を上げる方法もあります。
「地酒飲み比べセット」「若者限定!自分に合うお酒を見つけよう!はじめての日本酒セット」など、提案型のセット商品を販売したり、「今ならよりどり3品で10%OFF!」「5,000円以上お買い上げで自宅までお届けします!」などのお得感を演出したまとめ買いの提案をしたりすることが効果的です。
また、「夏酒セット」「おとそセット」「祝い酒セット」「花見酒セット」など、季節やイベントに応じたまとめ買いの提案も、客単価を上げるには有効になってきます。
アップセル
「アップセル」とは、お客さまに、現在検討している商品よりも上位ランク・上位価格帯の商品をおすすめする提案手法です。
具体例で見ていきましょう。
お客さまが見ている2,000円の地酒Aの隣に、3,000円の地酒Bを陳列します。
「地酒Bは、地酒Aよりも精米歩合が低く、高級な酒米を使って、手間のかかる搾り方をしています!雑味がなくクリアな味わいで香りがいいです!今なら、通常価格3,000円のところ、10%OFFの2,800円でご購入いただけます!この機会にぜひ1ランク上の味わいをご堪能ください!」
このようなPRをすることで、本来購入予定の商品よりも、高単価な商品を購入してもらうことで客単価を上げることができます。
上位ランク・上位価格帯の商品を購入してもらうほかにも、「単発買い」を「まとめ買い」や「頒布会」などに変更してもらうことも、「アップセル」に当たるので、さまざまな工夫で客単価アップを目指しましょう。
クロスセル
「クロスセル」とは、お客さまに「ついで買い」を促すような、関連商品を提案する手法です。
たとえば、お酒を購入してもらったお客さまに、「このお酒にはこのおつまみが合います!」などのPOPとともに、おすすめのおつまみを隣に陳列して購入を促すといったような事例が「クロスセル」です。
ECサイトでは、「この商品を購入したお客さまは、こんな商品も購入しています」などの案内をして、関連商品をおすすめすることができます。
ビールを購入したお客さまに、「2杯目はこちらをどうぞ!」のPOPをつけて、別のお酒を隣に陳列したり、レジの近辺に、ちょっとしたおつまみを置いておくなども「クロスセル」として客単価アップにつながるでしょう。
松竹梅の価格設定
「松・竹・梅」の価格設定にすることも、客単価を上げる手法の1つです。
「松・竹・梅」の価格設定にしてあると、「高すぎず安すぎずほどほどのものを選ぶ」ため、多くの人が「竹」を選択するといった「人の心理(松竹梅の法則)」を利用した客単価アップの方法となります。
たとえば、お酒を「並・上・特上」「本醸造・吟醸・大吟醸」に分けて陳列するなどの工夫をすることで、客単価アップにつながるでしょう。
客単価を上げるためのツールの活用
客単価アップを図るには、客単価を上げるためのツールを活用することも選択肢の1つです。
客単価を上げるためには、以下のようなツールの活用が効果的と言われています。
【客単価を上げるためのツールの活用】
- CRMの導入
- AIの導入
- チャットボットとの連携
以下、詳細をご紹介させていただきます。
CRMの導入
CRMとは、顧客管理システムのこと。CRMを導入することにより、顧客情報をデータベース化して、顧客情報の検索、顧客ごとの購買履歴の閲覧や管理などを行うことができるようになります。
CRMツールを活用して、ターゲットとなる顧客を選定し、ニーズに合った提案をすることで客単価を上げることができるようになるでしょう。
酒造業向けの販売管理システムの機能を使い、データの分析をすることで、CRMとしての機能も果たすことができます。酒造業向けの販売管理システムには、たとえば以下のようなものがあります。ここでは、簡単に比較してみましょう。
【酒造業向けの販売管理システム】
| 名称 | 種類 | 目的 | 概要 |
| 『五合』HANJYO | 酒造業向け販売管理システム | 酒蔵の特殊性に対応した販売管理をトータル支援 | 酒税管理から販売在庫管理まで |
| 酒仙i販売管理 | 酒造業向け業務管理システム | 独特の製法や酒税法などの特有の管理業務に対応 | 売上管理から税務管理まで酒造業務に必要な機能のほとんどをカバー |
| 三酒の神器 | 酒造業向け業務管理システム | 酒造業特有の販売/蔵内/購買/原価の管理のIT化 | カスタマイズ型のパッケージシステムなので、導入後それぞれの酒蔵・メーカーの特徴に合わせた調整も可能 |
酒販業者の場合は、酒造業向けの販売管理システムではなく、全業種対応のCRMや小売向けの販売管理システムなどが適しています。自社の状況を踏まえ、最適なものを選びましょう。
AIの導入
AI(人工知能)を導入して、客単価を上げるという方法もあります。
たとえば、店舗入り口と店舗内にAIを組み込んだカメラを設置することで、「20代の男性が入店した」「入店後最初にビールの陳列棚に向かった」「商品Aを購入した」など、画像に写った顧客の属性や店内の行動パターンを解析することが可能です。
CRMツールなどと連携させることで、顧客のニーズを把握することができたり、顧客の動線に合った陳列棚づくりや売れやすい商品の組み合わせを把握することができたりします。
チャットボットとの連携
EC販売を強化している酒販店にとっては、チャットボットとの連携を図ることで客単価を上げることができます。
クレジットカード決済に対応したチャットボットを導入することで、顧客をスムーズに決済まで導いてくれるだけでなく、チャット内で自然な形でアップセルを行うことで、お客さまにストレスを感じさせることなく、客単価アップを行えるのです。
最近では、対話型AIを導入したAIチャットボットなども注目を集めており、客単価を上げるために導入を検討してもいいかもしれません。
チャットボットの種類には以下のようなものがあります。
【チャットボットの種類】
| 種類 | 特徴・仕組み | メリット |
| シナリオ型 | 事前に想定問答を用意し、ユーザーが選択肢から選んで回答が得られる | シナリオ通りの会話進行によりユーザーを回答へ誘導、各種アクションにつなげられる |
| AI型 | 事前にAIに学習させたデータや過去の対話ログのデータを解析し、適切な回答を表示 | 過去の対話ログの蓄積によりAIの精度アップ、より幅広いジャンルの質問にも対応可能 |
| 辞書型 | フリーワード入力された質問文を解析し、事前に用意された辞書と照合し回答 | フリー入力のため、ユーザーにとっては、自然な会話で即座に回答へたどり着ける |
チャットボットには、上記のような種類で選ぶほか、導入目的に合わせた機能や導入の容易さ、外部ツールとの連携の可否、導入前のトライアルの有無、メンテナンスやサポート体制の充実度、セキュリティの度合いなど、いくつかのポイントを押さえて、自社に適したチャットボットを選択するようにしましょう。
客単価が下がる原因
ここまで、客単価アップの方法などをご紹介させていただきましたが、反対に客単価が下がる原因についても把握しておく必要があるでしょう。
客単価が下がる原因としては、以下のようなことが考えられます。
【客単価が下がる原因】
- 購入金額の減少
- 購入個数の減少
以下、詳しく見ていきましょう。
購入金額の減少
客単価が下がる原因の1つに、お客さま各人の購入金額の減少といったことが挙げられます。
購入金額の減少には、売り手側が商品単価を値下げしたケースや売れ筋商品が低価格商品に推移したケースなどがあるでしょう。
商品単価を下げるケースとしては、販促による割引やクーポンなどの活用があります。しかしこれらの施策は、新規顧客やリピーターの獲得など集客戦略としては効果がありますが、売上や利益を減少することになるため、慎重に行うことが大切です。
売れ筋商品の低価格化に対応するためには、付加価値の高い商品をPRして、売れ筋商品の再構築を行うなどの工夫が必要になるかもしれません。
購入個数の減少
客単価が下がるもう1つの要因として、お客さま各人の購入個数の減少が考えられます。
お客さまの商品購入点数が減る原因として、購入したいと思わせる魅力的な商品が減ったケースや値上げなどにより購入を控えたなどのケースも考えられます。
購入個数の減少に対する対応策として、商品の付加価値を訴求したり、まとめ買いやクロスセルを実行したりする方法があるので検討しましょう。
客単価を上げることができない外的要因
客単価が下がる原因の把握とともに、客単価を上げることができない外的要因についても把握しておくことが大切です。
客単価を上げることができない外的要因には、次に挙げるようなことが考えられます。
【客単価を上げることができない外的要因】
- 地域による消費傾向
- 市場の価格競争
以下、順に解説します。
地域による消費傾向
客単価を上げることができない外的要因の1つに、地域による消費傾向といったことが挙げられます。
酒販店がある地域の消費傾向によって、客単価を上げることができないケースの例として、富裕層が少ない地域のため、高価格帯の商品が購入されにくいケースなどが典型例ではないでしょうか。
近隣に安売りの小売店が多いケースでも、地域住民が全体的に安売りの商品を購入する傾向にある地域でも、客単価を上げることができないケースに該当します。
市場の価格競争
市場の価格競争も、客単価を上げることができない外的要因の1つとして考えられます。
近隣の競合店舗で、価格競争が激しいケースでも、客単価を上げることができないでしょう。
最近は、ネット販売も含めて競合相手となり得るので、客単価を上げるために値上げした場合、ネットで購入されてしまうリスクがあるので値上げできないなどといったケースが典型的です。
まとめ
ここまで、「客単価」に関して、業界別基準、計算方法、客単価を上げるための方法やメリット、ツール、客単価が下がる原因や客単価を上げることができない外的要因などをご紹介させていただきました。
売上目標、マーケティング戦略、事業計画などを作成する際には、あなたの蔵や店に適した「客単価」を設定することが必要になってきます。
現状の「客単価」が適正かどうかを客観的に分析して、「客単価」アップが図れるかどうか、「客単価」アップを図るためには、どのような経営改善を図るべきかなどを常にPDCAサイクルを回して考えていくべきでしょう。
アンカーマンでは、あなたの蔵や店の経営状況を現状分析し、適正な「客単価」、「客単価」アップを含めた売上改善、あなたの蔵や店の将来を考えたマーケティング戦略の策定などをサポートする「マーケティングサポート」をご用意しています。
アンカーマンというと、「補助金サポート会社でしょう?」と思われがちですが、近時は酒類事業者に特化したサポート実績200社以上のノウハウを活かして、サポートの幅を広げているので、お気軽にご連絡ください。
「売れる仕組みづくりを教えてほしい!」
「客単価をアップしてリピーターを増やすにはどうしたらいいのか?」
などなど、マーケティングに関するお悩みやご要望をお持ちの方は、アンカーマンまで!
お酒メーカーに役立つ制度一覧はこちらから!
酒税法改定、事業再構築補助金など事業継続・事業拡大に関わる
大切な制度について詳しく解説している記事一覧はこちらから!
お役立ち資料はこちらから!
設備導入事例集やアフターコロナの今取るべき戦略、働き方チェックシートまで
知りたいことが一式揃うお役立ち資料一覧はこちらから!
補助金診断はこちらから!
おすすめの補助金がすぐに分かる補助金診断を試してみませんか?
1分で完了する補助金診断はバナーをクリック!
補助金申請無料モニター募集中!
株式会社アンカーマンで補助金申請サポートをまだ受けたことがない方を対象に、
補助金申請無料モニターを不定期で募集しています!
応募にご興味をお持ちの方は、下記をチェック!
無料相談はこちらから!
アンカーマンの補助金サポートにご興味のある方は、以下の専用フォームに「マーケティング 相談」と必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリック!